ASCO2006・肺がんの術後化学療法、ガイドライン変更の必要なし
新しい治療法のリスクとベネフィットを正しく知り、悔いのない選択を

東京医科大学
外科第1講座講師の
坪井正博さん
世界で最大規模のがん関連学会、米国臨床腫瘍学会(ASCO)の第42回年次大会(ASCO2006)における、肺がん治療に関するトピックスを、東京医科大学外科第1講座講師の坪井正博さんに伺った。
ここ数年で化学療法の評価一変

坪井さんが語るのは、肺がんの中でも全体の8割を占める非小細胞肺がんに対する術後補助化学療法についての最新報告だ。
たとえ手術可能であっても、ほとんどの症例に再発・転移のリスクがあり、化学療法を含む何らかの全身治療が欠かせないのが肺がんの特徴、と坪井さんは語る。
「肺がんは、早期がんでも微小転移があるケースがとても多い。したがって、治療は手術や放射線といった局所療法と、全身治療である抗がん剤治療とを組み合わせて行う必要があります。とくに肺がんの場合、手術したからといって治癒するとは断言できないので、再発のリスクを減らすための術後化学療法が非常に重要になってきます」
しかし、小細胞肺がんは抗がん剤に対する感受性が高く、化学療法の効果が見込めるのに対して、抗がん剤への感受性が低いため、化学療法の効果もあまり期待できないとされてきたのが非小細胞肺がんだ。このため、従来は手術でがんが切除できたら治療は終わり、というのが一般的で、術後の補助化学療法は長らくその効果が証明されていなかったこともあり、臨床試験ベースの治療が行われてきたという現実があった。
ところがここ数年、ASCOを舞台に、非小細胞肺がんに対する化学療法の評価を一変させる出来事が起こってきた。その背景には、この10数年の間に、いくつもの新しい抗がん剤が開発される一方、副作用を軽減する薬もさまざまなものが登場してきたことがあげられるが、日本を含む各国で、大規模臨床試験が行われた結果、非小細胞肺がんに対する術後化学療法に有用性があるとの研究報告が、03年から05年にかけて開催されたASCOで相次いで発表されたのだ。
これらの報告を受けて、欧米各国は術後化学療法を標準治療に組み入れるようになり、日本でも、日本肺癌学会が昨年秋、治療指針(ガイドライン)を改訂し、術後病期1B、2、3A期の非小細胞肺がんの完全切除例に対して、術後化学療法を標準的な治療法として推奨するようになってきた。
具体的には、1B期の患者に対してはUFT(一般名テガフール・ウラシル)もしくはプラチナベース併用療法が、2期と3A期の患者にはプラチナベース併用療法がエビデンス(根拠)にもとづく治療法として推奨されている。ただし、第3世代の抗がん剤を含むプラチナベース併用療法に関しては、日本ではエビデンスとして評価されるだけのデータが不十分ということで、実際の医療現場では薬剤の選択、治療のケアには慎重な対応を指摘されているのが現状である。
“焼き直し”発表が注目される理由
さて、2006年のASCOではどんな報告があったかというと、非小細胞肺がんの術後化学療法については、(1)04年のASCOで発表されたCALGBというアメリカのグループが行った臨床試験についての解析、(2)シスプラチン(商品名ブリプラチン、ランダ)ベースの補助化学療法に関する大規模試験のメタアナリシス(複数の研究結果のデータを統合して分析する手法)、(3)カナダのグループが行ったJBR10という臨床試験のサブ解析で、高齢者を対象とした試験の結果、(4)補助化学療法のエビデンスを構築する基礎ともなったIALTという臨床試験についての解析で、どういう患者にシスプラチンを用いた補助化学療法が有効か、ERCC-1というDNA修復遺伝子に関する発表――という4つの大きな発表があった。
いずれも、すでに03年から05のASCOで報告されたデータをさまざまな角度から見直す発表であった。そういう意味では古いデータの“焼き直し”といえるが、“その焼き直し”の発表が注目されたという。その理由を、坪井さんはこう語る。
「03年から05年に発表された5つの試験は、術後補助化学療法の評価を高めるものでしたが、病期別のサブ解析をみると、評価が分かれています。とくに1B期については、たとえばJBR10は全体的には術後補助化学療法の有用性を報告していますが、病期別にサブ解析してみると、1B期はあまり効果ありといえないが、2期は効果ありとなっています。日本でも、UFTの1期全体のデータがあって、1A期では一部の患者の効果にとどまるが1B期の患者さんには非常に効果があるとか、ANITAでは、1B期の患者さんにはあまり効果がみられないが、2期、3期の患者さんにはそこそこ効果があると発表しています。このように、病期によって評価が分かれている問題をあらためて解析するためのメタアナリシスや、あるいはとくに1B期の評価が分かれているため、これのみを対象とした試験の結果が評価され、今年の発表となっています」
「全生存」で差なし、「無再発生存」でリスク減少
そこで、坪井さんが今年のASCOのトピックのひとつとしてあげるのは、CALGBの臨床試験についての解析。この試験は、1B期*T2NOMOの非小細胞肺がんの完全切除例に対するもので、タキソール(一般名パクリタキセル)とパラプラチン(一般名カルボプラチン)の2剤併用による術後補助化学療法を実施した群と、手術単独群とを比較した試験。04年に発表されたときは観察期間34カ月だったが、今年の発表では57カ月となり、5年近い観察期間となった。
「全生存率」では、術後化学療法群のほうが高い傾向にあったが有意差は認められず、5年生存率でみると術後化学療法群は59パーセントだったのに対して手術単独群は57パーセントで、その差は2パーセントしかなかった。ただし、3年生存率では79パーセント対71パーセント、2年生存率では90パーセント対84パーセントで、それぞれ8パーセント、6パーセントの上乗せ効果があった。また、「無再発生存期間」でみると、術後化学療法群のほうが有意差をもって再発のリスクを減少できることが示めされたとしている。
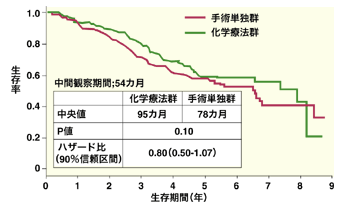
[術後化学療法の治療成績(無再発生存)]
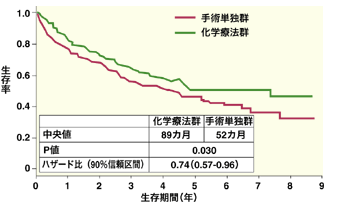
また、腫瘍が4センチ以下だと術後化学療法群と手術単独群と比べても差はないが、4センチ以上だと術後化学療法群の成績が手術単独群のそれを上回ると報告している。
「これらのことから、無再発生存と3年生存率では術後化学療法群に有意なベネフィット(利点)があり、今のエビデンスを覆すものではない、と今回の発表ではまとめています」
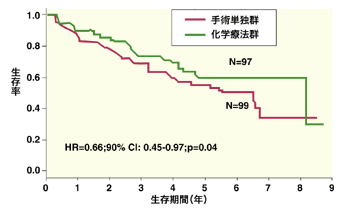
[腫瘍の大きさが4cm以下の場合の治療成績]
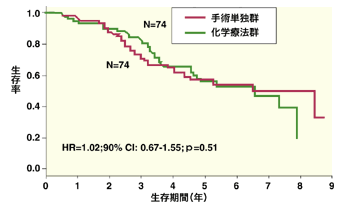
*T2NOMO=Tは腫瘍の大きさ、Nはリンパ節転移、Mは遠隔転移を表し、T2は腫瘍の大きさが3cm未満、主気管支への進展が気管分岐部から2cm以内の場合をいう
同じカテゴリーの最新記事
- 空咳、息切れ、発熱に注意! 肺がん治療「間質性肺炎」は早期発見が大事
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!
- 免疫チェックポイント阻害薬と体幹部定位放射線治療(SBRT)併用への期待 アブスコパル効果により免疫放射線療法の効果が高まる⁉
- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に
- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 肺がんの基礎知識 自分の肺がんのタイプを理解する 肺がん丸わかり基礎
- 過不足のない肺切除を実現!注目の「VAL-MAP」法



