じっくりと患者の話に耳を傾け、泣ける場を作る
乳がん体験者ががん患者を支える 患者の悩み、必要なサポートとは?

西貝圭子さん
西貝圭子さんは治療後20年以上を経た乳がんサバイバーであり、日本のがん闘病現場で*ピア・サポートを担ってきた草分けの1人。現在も手術直後の患者を病室に訪ねる「病院訪問ボランティア」などの活動を続けている。患者が抱えている悩みとは何か?それに対して必要なサポートとは?多くの患者の声を聴いてきた西貝さんに話をうかがった。
*ピア・サポート=同じような立場の人によるサポートのこと。同じ課題に直面する人同士が互いに支え合うことを意味する場合もある
病院訪問ボランティアの立ち上げから参加
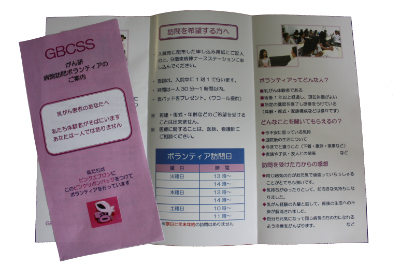
西貝さんが乳がんの診断を受けたのは38歳のとき。テレビのレポーターなどの仕事をしながら、3歳の男の子と9カ月の女の子を育てる忙しい時期だった。乳腺症を患い、検査も受けていたので、しこりを見つけ、がんと診断されても早期だろうと安心していた。当時はまだ少なかった乳房温存(部分切除)手術ができる病院として癌研究会付属病院(現・がん研有明病院)を選んだのもそのためだった。しかし、手術前日に知らされたのは、温存は不可、術式はハルステッド手術ということだった。当時定型手術と言われ、乳房だけでなく大胸筋も小胸筋もすべて切除する、患者への心身の負担が極めて大きい手術だ。
自分の病気をもっと知りたいという気持ちから、退院後、全国組織の乳がん患者会「あけぼの会」に入会。会員がみな自分の病状に詳しく、専門用語が飛び交うことに驚き、自身も勉強会や啓発活動などに参加するようになる。
病院訪問ボランティアは、1994年あけぼの会がオーストラリアの例に学び、聖路加国際病院などで始めた活動。がん研有明病院では、2007年に活動開始。その後あけぼの会の活動を離れ、SBCSS(Seiroka Breast Center Support Service:聖路加がん研病院訪問ボランティア)、GBCSS(Ganken Breast Center Support Service:がん研病院訪問ボランティア)として独立し、活動を継続している(写真1)。西貝さんは1995年から病院訪問ボランティアに参加し、現在GBCSSのコーディネーターをしている。
病院訪問ボランティアは名前の通り、乳がん手術直後の患者の病室に訪ね、話を聴き、情報を提供する活動だ。がんの患者会が相談会を開き、参加者を募ることはよくあるが、入院中の患者のところにボランティアが出向き、1対1で話をする活動はごく珍しいと言えるだろう。例えば、がん研有明病院では現在、週3日(火木土)、1日2人の枠をとっている。基本は初発の患者が対象で、時間は40分から1時間ほど。直近では、1年間(2015年7月~2016年6月)で約20人のボランティアスタッフが129人の患者のもとを訪問した。
同じ経験をしたからこそ話せる
では、乳がん患者が手術直後に、医療者でもなく親しい友人でもなく、初めて会う乳がん体験者と話すことの意義はどんなところにあるのだろうか。西貝さんは言う。
「1つは『あなたは1人ではありません』ということです。患者さんは、退院後孤独を感じることがあります。乳がんと聞いて『死んでしまう病気だ』と腫れ物に触るように接せられても、逆に『今はいい治療法があるから大丈夫よね』と簡単に考えられても、どちらも違和感があり、ママ友やご近所の方に病気を打ち明けるべきか悩む方も多いです。また手術を受けた直後の患者さんは、自分が今後どうなるのか思い描けなくて不安です。
なぜ私ががんになったのかという怒りもあれば、心配をかけたくないからと親や子に話せない、会社に言ったらクビになるのではないかなど、1人ひとりがそれぞれの背景、課題を抱えています。私たちサバイバーはがんと言われた時の思いや再発への不安など、同じ気持ちを経験しているので、患者さんからすると『あ、同じなんだ』と一気に敷居が低くなり、この人ならわかってくれる、と色々なことを打ち明けて下さるのだと思います。
私たちは医療者ではないので医療的な質問には答えられませんが、乳がんを体験した生活者としての質問には答えられます。そして何より、こうして私たちが元気に活動をしていることで、『自分もやがてそうなれる!』という気持ちになれる。それは私たちでなければできないことで、患者さんにとって目に見えない励ましになっていると感じます」
基本は患者の話を聴くこと
病院訪問での基本は、患者の話を聴くこと。
「皆さんそれぞれに色々な背景、ストーリーがあって、それを誰かにわかってもらいたいという人が多いのです。例えば、医療的な話であれば、医師や看護師に聴くこともできますが、『夫婦仲がうまくいっていないが、病気になってしまっては生活できないので離婚が出来ない』『自分が死んだら障害のある子はどうなってしまうのか』といった、誰に話せばいいのかわからない悩みを抱えている方も中にはおられます。ですので、まずはじっくりと患者さんの話に耳を傾けます」
そして最後に、何かあったらここに連絡して下さい、と個々の連絡先を記した名刺を置いていく。
「こういった活動で、個人の連絡先を伝えるというのは、あまりないかもしれません。ただ、患者さんにとっては、その連絡先があるだけでほっとされるようです」
毎回、訪問した際の記録は「ボランティアレポート」として記載し、医療者側に伝える。また、患者が医療者に直接言いにくいことについても、要望を聞き、それを病棟の看護師に伝え、患者と医療者の橋渡しも行うことがあるという。
思い切り泣ける場を提供する
体験者と話すもう1つの意義を、西貝さんは「思い切り泣ける場を提供できること」と話す。
「乳がん患者さんの多くは、『頑張って』と言われても『病気は頑張らないからなったわけでもないし、頑張れば治るのか』という思いがあります。ですから、私たちも絶対に『頑張って』とは言いません。『肩の力を抜いて頑張り過ぎないで』『頑張っちゃってるけれど、私たちの前では我慢しなくていいんですよ』と声をかけると、ほっとして泣かれる方も多いです。小学校の先生から、訪問して1年後『おかげさまで今元気に過ごせています。あの時泣かせてもらったことで、再生の1歩を踏み出せました』というメールをいただいたこともあります」
体験者ならではの生活のアドバイスも
現在、西貝さんは、がん研有明病院での病院訪問ボランティア以外に、東京・練馬区に在住しているあけぼの会の有志会員で、「あけぼの-NERiMA-」という会を立ち上げ、練馬区と一緒になって乳がんに関する様々な活動を行っている。
「乳がんの検診率を上げる活動の一環として、学校のPTAや育児サークル、図書館と連携しながら乳がん出張講座を開いています」(写真2)
そうした活動の中で、今年(2016年)5月からは、乳がんの悩みを気軽に話せる場として、月1回、サロンを開く活動を始めた(写真3、図4)。
「これまでの活動に参加して下さった方から『身近に乳がんについて相談する所ってないですか?』と聞かれたことがきっかけです。確かに小さなお子さんがいる場合、相談したくても、電車に乗って遠くまで行くことは難しいです。話をすることで、少しでも肩の荷が下りれば、ということで始めました」
参加者は乳がん体験者やその家族など。ここでは体験者ならではの生活のアドバイスを行うことも多い。
例えば、化学療法を始めたのだけれども、髪の毛はいつごろから抜け、いつ生えてくるのか、ウイッグはいつ用意したらいいのか、下着はこれまでのものが使えるか、いつから温泉に入れるのか?そもそも温泉には入れるのか、趣味のマラソンは出来るようになるか、などなど、術後の生活にまつわる心配事も、患者によって様々だ。
「『夏場は特製パッドは蒸れるから、ストッキングを利用するといい』「子供が小さい時は胸に抱いて湯船に入ると目立たない」なんて答えることもあります。こうした個人的なちょっとした工夫をそれぞれ話の中で出し合ったりしています。参加した方は、『気持ちが楽になった。また来ます』とおっしゃる方も多いです。体験者ばかりのサロンなので気軽に来てほしいですね」
日本人女性の12人に1人は乳がんになる時代。乳がんは決して珍しい病気ではなくなった。だからこそ「あなた1人ではありません。私たち体験者がそばにいます」。西貝さんら体験者の持つ言葉は、特別な意味合いを持っている。
「乳がん出張講座」
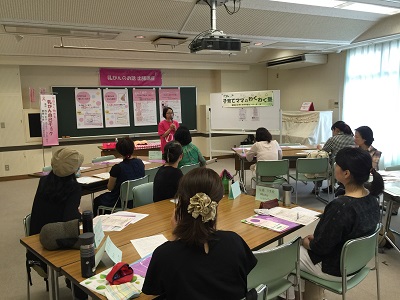
「ピンクリボンin NERiMA サロン」


同じカテゴリーの最新記事
- 高齢者乳がんに対する診療の課題 増える高齢者乳がん~意思決定支援を重視した診療を
- 納得した乳がん治療、療養生活を選ぶために アドバンス・ケア・プランニングの取り組み
- 乳がんサバイバーの職場復帰:外来通院中の患者さんを対象に意識調査 職場復帰には周囲の理解と本人の自覚が大切
- 診療放射線技師:治療計画から機器の管理まで幅広く行う 患者さんの不安を取り除くことも大切
- 義肢装具士:失った手足を取り戻し、日常生活を支援 早期訓練で、患者さんもより早く社会復帰へ
- 理学療法士:訓練ではなく日常を楽にするがんの理学療法 患者さんの体と思いに寄り添う
- 臨床研究コーディネーター:薬の開発を患者さんの立場からサポート 医師、製薬会社、患者さんの橋渡しを担う
- 音楽療法士:がん患者さんの心と体を癒やす音楽療法 身心の調子に合わせた選曲が大事
- 管理栄養士:細やかな心配りで、がん患者の「食べる」を応援 患者の約7割は、その人に応じた個別対応



