がん体質を調べる遺伝子検査・診断の最前線

埼玉県立がんセンター
腫瘍診断・予防科科長の
赤木究さん
がんになりやすい体質をその人が持っているのかどうか、それを調べる遺伝子診断。
これはどこまで進んでいるのだろうか。
先進的に取り組んでいる埼玉県立がんセンター遺伝子診断室の最前線をレポートする。
病気と遺伝子の関係について説明をしていた医師がふと口をつぐんだ。長い話に休止を挟んでいるようでもあったが、私が何か言うのを期待するようでもあった。医師の隣では女性の遺伝カウンセラー(※1)が穏やかな表情でこちらを見ている。
大腸がんを宣告されたときはショックだった。でもすぐに、「よし、治療を乗り切って、また元気になるぞ」と引き締まった気持ちになった。けれども、「がんになりやすい体質の可能性がある」と言われた場合は、どうなのだろう? 宣告された事実にどう立ち向かったらいいのか。そこがピンと来ない。
部屋に入ったときからずっと流れていたオルゴールの音色に耳を澄ませた。ここは、カーテンの向こうで看護師たちが忙しく働いている診察室とはまったく違う。完全な個室だ。窓から差し込む午後の日射しが室内をどこかのんびりとした雰囲気にしている。窓の下半分が磨りガラスなのはプライバシーを守るためなのだろう。
放心したように見えたのか、医師が優しく声を掛けてきた。
「遺伝子診断を受けるかどうか、急いで結論を出す必要はありませんよ。ご家族の方にもかかわる問題ですので、ご家族とよく話し合ってはいかがですか」
これは、埼玉県立がんセンターで行われている「がん遺伝カウンセリング外来」の1コマだ。
※1 遺伝カウンセラー=遺伝的、先天的な疾患に関する悩みを抱える人や、遺伝子診断や遺伝子治療を受ける人に必要な情報を提供し、心理カウンセリングを通して、問題の克服を援助する職業
(遺伝子検査装置類の写真提供:(株)ファルコバイオシステムズ)
遺伝子の変異の性質を調べ受診後のケアを行う外来
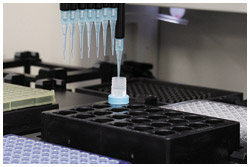
がんの原因は特定の遺伝子の変異が積み重なることにある。変異は生活習慣や環境に起因することが多いが、生まれつき遺伝子の変異を持っている場合もある。
遺伝子は両親からそれぞれ1セットずつ受け継ぐので、人は同じ役割の遺伝子を2つ持っている。だから、一方の遺伝子が生まれながらに変異していても、もう一方の遺伝子が偶発的に変異するまでは、がんの発症にはつながらないことが多い。
つまり、変異が遺伝しているからといって、必ずがんになるとは限らない。とはいえ、遺伝的な変異の場合は、体中の細胞に同じ遺伝子変異が存在しているため、一般の人に比べれば、がんになりやすいといえる。
そうした体質の持ち主であるかを調べるのが、がん体質の遺伝子診断であり、受けることで得られるメリットや気をつけてもらいたいことなど、十分な情報提供を行い、結果を知らせた後もケアをしてくれるのががん遺伝カウンセリング外来だ。
診断対象が多いのは遺伝性の大腸がんや乳がん


同センター腫瘍診断・予防科の赤木究さんはがんの遺伝子診断の意義をこう語る。
「遺伝性がんの多くは、普通のがんに埋もれてしまって、あまり気づかれていません。そこをなんとか掘り起こして、ハイリスクの人たちに定期的に検診を受けていただくようにする。それが現時点における最も効果的な予防法となります」
では、がん体質の遺伝子診断の実際とはどんなものだろうか。同科の外来は再診も含めて年間延べ70~80人。その約7割を占めるのが、リンチ症候群を疑われる患者さんだという。
リンチ症候群は、遺伝性非ポリポーシス大腸がんとも呼ばれ、遺伝性の大腸がんの一種として知られてきた。大腸がん患者の2~5パーセントはリンチ症候群といわれている。リンチ症候群と診断された場合、約8割の方が70歳までに大腸がんを発症する。また、子宮内膜や胃、卵巣などのがんの発症率も一般の人よりは相対的に高い。若くしてがんになる傾向があり、繰り返し発症する可能性も高い。リンチ症候群は(1)原因となる遺伝子がわかっている、(2)診断のメリットが得られやすい、(3)患者数が比較的多い、といった条件を満たしているため遺伝子診断の対象となる代表的な病気である。
同センターでは、大腸がん手術で摘出されたがん組織を用いて、臨床所見では見つけることが難しいリンチ症候群を絞り込むための予備検査(マイクロサテライト不安定性検査)を実施している。この検査で陽性になるのは大腸がんの6パーセント程度。陽性となった患者さんには、主治医から遺伝カウンセリング外来の受診を勧めている。受診された患者さんには、病気の特徴や遺伝子との関係、病気の可能性がどの程度疑われるのか、遺伝子診断の実施で注意すべき点など、患者さんの理解や気持ちに応じて話を進める。
遺伝子診断してもはっきりしない場合がある

遺伝子診断では、受診者本人のみならず、家族にもさまざまな影響を及ぼす可能性があることを認識しておく必要がある。
「自分ががんになりやすい遺伝子を持っていることがわかることで、子どもに申し訳ないような気持ちになるかもしれません。また、家族に正しく理解してもらえないかもしれません。就職や昇進、あるいはお子さんの結婚などによくない影響を与えてしまう可能性もあります」
同センターでは、遺伝カウンセリングを医師(臨床遺伝専門医)と遺伝カウンセラー(または看護師)の2人で行っている。
「説明はだいたい私が1人で行いますが、私が席を外したときなどに、カウンセラーの方に受診者の気持ちを聞いてもらい、フォローをお願いしています」
受診は配偶者同伴が望ましいことが多い。結果が陽性だった場合、配偶者なら客観的な立場で子どもに対応できる。また、万が一本人が亡くなっても、配偶者が知っていれば、子どもに伝えることができるからだ。
診断実施前に外来へは何回でも通えるが、多くの方が1~2回受診した後に遺伝子診断を行うかを決定するケースが多い。1回の話が2時間に及ぶこともある。これまでのところ、遺伝カウンセリングの結果、約6~7割の方が遺伝子診断を希望している。診断に同意すると、7~10ccの採血を行う。血液細胞のDNAを検査に用いるためだ。検査は検査会社に委託され、結果まで1~2カ月を要する。
遺伝子診断でわかることには限界がある。遺伝子検査で陰性であっても、遺伝性のがんである可能性は否定されない。
「検査では見つからない遺伝子の変化が存在していたり、検査した遺伝子のほかにも原因となる遺伝子が存在する可能性もあり、遺伝子検査で変異が見つからなくても、遺伝性のがんでないとは言い切れません」
逆に、変異が見つかっても、がんになりやすい体質と断定できない場合もある。
「調べた遺伝子に変異が発見されても、それががんの発症とは関係ない場合もあります。変異の種類とがん発症に関するデータベースを参照するなどして変異の評価を行うのですが、情報不足で判断できないこともあります。これまでの遺伝子検査の3分の1弱は、はっきりした診断がつきませんでした」
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場
- 正確な診断には遺伝子パネル検査が必須! 遺伝子情報による分類・診断で大きく変わった脳腫瘍
- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!
- がんゲノム医療をじょうずに受けるために 知っておきたいがん遺伝子パネル検査のこと
- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す
- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜
- 重要な認定遺伝カウンセラーの役割 がんゲノム医療がますます重要に
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 「遺伝子パネル検査」をいつ行うかも重要 NTRK融合遺伝子陽性の固形がんに2剤目ヴァイトラックビ
- 血液検査で「前がん状態」のチェックが可能に⁉ ――KK-LC-1ワクチン開発も視野に



