「乳癌診療ガイドライン」が3年ぶりに大幅改訂 「乳癌ガイドライン」を医師と患者のコミュニケーションツールとして使って欲しい

話す岩田広治さん
これまでは2年ごとに改訂されてきた「乳癌診療ガイドライン」だが、今回は3年を要して改訂された。今回の改訂は、これまでのガイドラインと大きく変わったという。どこがどのように変わったのか。ガイドライン作成委員長の愛知県がんセンター中央病院乳腺科部長の岩田広治さんに伺った。
世界のガイドライン作成の流れを取り込む
診療ガイドラインとは、ある病気に対する検査・診断から、進行度に応じた各治療法まで、現時点でのエビデンス(科学的根拠)に基づいてその推奨度を整理し、医師が診療にあたっての指針とするためのまさしく診療ガイドブックのことだ。
ここでは2018年5月に改訂版として日本乳癌学会が発刊した「乳癌診療ガイドライン2018年版」(図1)について紹介する。
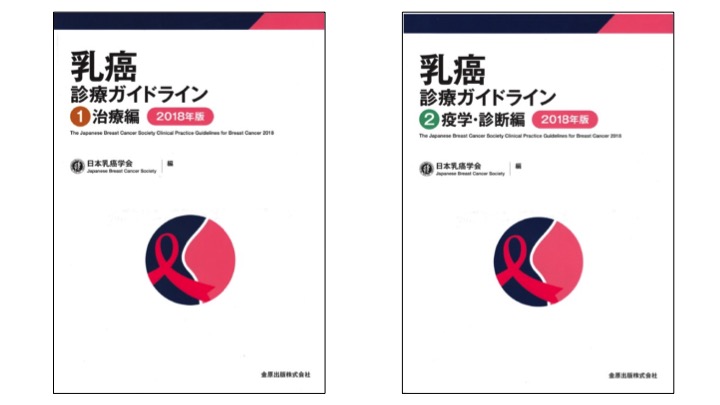
乳がんの領域においては、2002年に、日本乳癌学会による最初の「乳癌診療ガイドライン」が作成されて以来、改訂を重ね、2015年版まで、2年ごとに新たなものが作成されてきた。
「私は、2015年に新たな改訂版のガイドライン委員長を任されたとき、ガイドラインとはそもそも何のためのものだと改めて考えました。そして、ガイドラインとは患者さんのためのものなのだということを、世界のガイドラインの流れなども勉強しながら痛感しました。ですから今までのガイドラインの反省点を洗い出しながら、新たなガイドラインを作成しようという思いになりました」(図2)
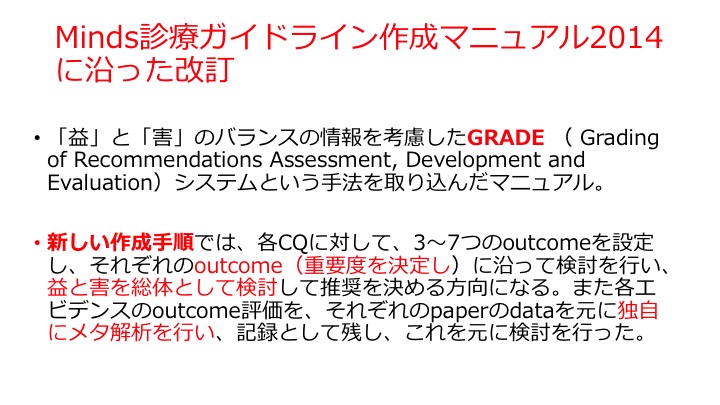
そう話すのは、2018年版のガイドライン委員長を務めた、愛知県立がんセンター中央病院副院長で乳腺科部長の岩田広治さんだ。
2018年版は、従来とは違い、3年の時間を要し改訂された。岩田さんは、その理由をこう説明する。
「2018年版は、2015年版までとは違ったプロセスでの作り込みを行ったことで作業量が大幅に増えました。そこで私の判断で2年ではなく、3年かけて完成するに至りました」
2015年版までは、CQ(クリニカル・クエスチョン)という臨床上の疑問が、「薬物療法」「外科的療法」「放射線療法」「疫学・予防」「検診・画像診断」「病理診断」と6分類されて立ち、それぞれに関する文献を選んできて読み込んで、エビデンスに基づく推奨度を専門家集団の委員会の中で議論して決めて、各委員が書いたものをピアレビュー(査読)して確定していくというプロセスを踏んでいた。
「ところがこの方法には弱点があって、エビデンスが一番あって推奨度が一番の治療を必ず行うというように、結論と治療の選択が限定的になっていたのです。しかし、私たち乳がんの専門医は日常の臨床において患者さんに行う実際の治療では、推奨度が一番のものでもオールマイティではなく、必ず良い面と悪い面の両方があるということを認識しています。例えば、生存期間が延びるという薬であっても、副作用が強かったり、治療費が高額だったりするなどの弊害は、患者さんの立場を考慮すると、必ずしも良い面ばかりでないことがあるからです。
そこで2018年版のガイドラインでは、実際の臨床での、良い面と悪い面の両方を考慮して治療法を決めていくというやり方に則(のっと)っての内容にしようと考えたわけです」
つまり従来のガイドラインは、医療者側のエビデンスを重視した一方的な発想が反映された、正(まさ)にエビデンス集だったと岩田さんは振り返る(図3)。

益と害のバランスを重視
そこで2018年版の作成にあたり、実際に行った作業は、CQを立てると、アウトカム(outcome: 結果・成果)を1つではなく 3~7つ設定して、益と害を総体として検討し、推奨度を決めたという。
「例えば手術の場合を例にとると、腋窩 (えきか)リンパ節郭清は、センチネルリンパ節転移が陽性でも、リンパ浮腫という副作用が起こることを考慮しながら、生存率との関連性などをアウトカムごとに設定して、それぞれのアウトカムごとに全文献を調べて、システマティックレビューという統計ソフトにデータをすべて入れて、メタ解析(複数の研究結果による分析)をするということを1つひとつに対して行いました。これはものすごい労力でした。担当した医師の皆さんには本当にご苦労をかけたと思います。
しかし、このやり方を実践したことで、治療の良い面、悪い面を整理でき、治療の選択肢に大きな意味を与えることができたと思います。おそらくこの膨大なデータを入れるという作業は、将来的にはAI(人工知能)に任せることができるようになるでしょう」
