チャイルド・ライフ・スペシャリストの重要性
緩和ケアを受ける家族の子どもにも目を向けて欲しい

父母が病気になると、子どもは親と離れることや、生活が変わっていくことに対して不安になることが多い。また、家族は親の病気について、どう子どもに伝えたらいいのか悩みがちだ。
チャイルド・ライフ・スペシャリストは、子どもの心を支える専門職。緩和ケアを受ける子どものいる患者家族をサポートする取り組みを紹介する。
家族は子どもの問題を打ち明けられずにいる
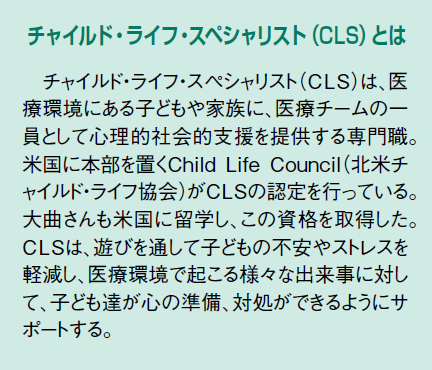

緩和ケアを受ける家族は配偶者や親といった大人が対象になりがちだが、子どもにも目を向けようという取り組みがある。
国立国際医療研究センターの小児科には、チャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS)の大曲睦恵さんが所属している。CLSは耳慣れない職名だが、入院中の子どもたちを励ましたり、両親、祖父母などの家族が緩和ケア治療を受けている場合に、心の準備ができるように手伝ったりするのが仕事だ。アメリカやカナダなどでは、すでに小児医療に不可欠な存在になっているが、日本ではまだまだ認知度が低い。
大切な家族の闘病は、子どもにとっても大きな出来事だ。孤独な状況に置かれることで、心理的に不安定になることもある。同センターで、大曲さんと患者家族との橋渡し役をしているのが、副看護師長であり、精神看護専門看護師である小川弘美さんだ。
「病状が進行していく患者さんにお子さんがいる場合は、常に気に掛けるようにしています。お子さんが見舞いに来る回数や、来たときの様子をスタッフに聞いて、子どもをフォローできていないようであれば、踏み込んで家族に話を聞きます。
面談してみると、お子さんの食欲がない、学校を休みがち、親のお見舞いに来たがらないなどで困っている。よくよく話を聞くと、お子さんにはまだ親の病気の話をしていない、どう伝えていいのかわからない、親が徐々に弱っていく姿を見せることに抵抗があるなど、様々な問題が出てくる。患者さんたちは、子どものことまで病院のスタッフに相談していいものかと躊躇し、我慢しているのです。そうしたご家族の悩みを解消してもらうために、大曲さんを紹介します」
小川さんからバトンを受けた大曲さんは、遊びを通して子どもの不安を和らげる。また、さりげなく気持ちを聞き出し、家族全員がお互いを理解し合えるように支援していく。「○○くん」「○○ちゃん」と名前で呼び、子どもは自然に大曲さんのことを「おーちゃん」と呼ぶ。だが、赤ちゃん言葉は一切使わない。「子どもを1人の人間として認め、適切な距離感を維持しながら接しています」と言う。優しさの中に毅然とした姿勢を感じるからこそ、子どもは信頼して心を開くのかもしれない。
事例① 妹の緊張感がほぐれて 姉と最期のときを過ごす
実際に、思春期のお子さんのいる家族をサポートした例を紹介しよう。
両親と姉妹の4人家族で、10代後半の姉が入院。病状が進行していた。お母さんは妹が不安にならないよう、姉の厳しい病状については知らせなかった。妹はなぜか姉のベットサイドに行きたがらず、病院に来るものの、ロビーにポツンと1人で、学校の宿題やゲームをする毎日。小川さんはスタッフから、ロビーで1人きりでいる子がいると聞いて気になっていたと言う。
やがて姉の病状がさらに進行し、このまま妹と会わないでいいのだろうかと、迷ったお母さんが小川さんに相談に来た。そこで小川さんは、大曲さんに介入を依頼する。
「私が妹さんに話を聞くと、彼女は両親の様子を見て、お姉さんの病状がよくないことに気づいていました。そして『今は怖いからお姉ちゃんの側に行けないけれど、いつかは行こうと思っている』と話してくれました。私は彼女に『ビーズでブレスレットのお守りを作って、お姉ちゃんにプレゼントしない?』と提案し、お母さんには『予後について話すのではなく、今日はお姉ちゃんの手をマッサージしたのよなど、お姉さんにしたことを話してあげると、妹さんが病室に行きやすくなりますよ』と伝えました」(大曲さん)
翌週、姉の病室は今までとは部屋の様子がまるで変わっていた。妹が作ったビーズの作品がたくさん飾ってあり、家族全員が1つの部屋で過ごせるようになった。「その後お姉さんは亡くなりましたが、最後まで病室は温かな雰囲気でした」(小川さん)
事例② 子どもは見守る役割を果たし、親の力になる
大曲さんは、「子どもだからといって蚊帳の外に置かず、家族はみんな輪の中に入れる」サポートを心掛けている。もう1つの例を紹介しよう。
園児と小学生の子どもがいる4人家族。40代のお母さんの看取りを在宅ですることになり、お父さんから「これからもっと症状が進んできたら母親が苦しむ姿を子どもに見せていいのか、最期のときが近いことを子どもに知らせていいのか迷っている」という相談があった。
「答えはないのですよ。でもお子さんにも、お母さんにしてあげられることをさせてあげてはどうでしょう。そのように、子どもを家族の輪にしっかり入れながら、最期については、お子さんが知りたいと言ったら、タイミングを見計らって話してあげたらいいのではないでしょうか」と大曲さんが話すと、お父さんは安堵した表情で帰宅したそうだ。
その後1カ月ほどでお母さんは亡くなり、ともに看取りをした訪問看護師から、「お母さんがつらそうにすると、お子さんが頭をなでたり、背中をさすったり、お母さんを励ましていた」という話を聞いたと言う。小川さんは言う。「子どもは大人を支える力になってくれます。子どもたちが側で見守る役割を果たしてくれたことで、お母さんは安心し、温かな看取りができたのではないでしょうか」
