進行別 がん標準治療 手術できるか否かが大きな分かれ目。手術できなければ放射線、抗がん剤治療
下部胆管がんの治療
手術しやすく、治りやすいがん
胆管がんの中でも、割合治る率が高いのが、ファーター乳頭部がんと下部胆管がんです。
「下部胆管は、膵臓の中を走っているので、いわば膵臓ががんの広がりを止める防波堤の役割をしています。そのために、手術の適応になる率が高く、手術しやすいのです」と木下さんは語っています。手術できれいにがんが切除できれば「報告にもよりますが、5年生存率は30~50パーセント」だそうです。
下部胆管はもちろん、乳頭部がんも、極めて早期の場合は別として、膵臓に近いので膵臓にもがんが関係していることがほとんどです。そのため、手術は胆管切除と同時に、膵頭十二指腸切除を行うことになります。つまり、膵臓の頭部とここに隣接する十二指腸を一緒に切除します。残った胆管と腸を直接繋ぐことになります。木下さんによると「膵臓にかなり浸潤していたり、リンパ節転移があると、治療成績は低下する」といいます。
逆に、手術できないのは、「がんが腹膜や肝臓に飛んでいたり、周囲のリンパ節に多数の転移がある場合」です。この場合は、最初から手術の適応にはならないそうです。
胆のうがんの治療
腹膜播腫になりやすく、手術しにくい
胆のうは、胆汁を貯蔵して濃縮し、胆管に放出する小さな臓器です。ここにできるがんは「早期発見がかなり進行したがんか、発見時の状態は二極化している」といいます。
胆のうがんは、胆石を合併している人が多いことが知られており、胆のうがんの人の6割が胆石を持つといわれています。胆石自体は、今では内視鏡で摘出されることが多くなっていますが、このとき運良く偶然に胆のうがんが発見されることがあります。こうして発見された胆のうがんや、胆のうポリープとして切除され診断された胆のうがんは、早期がんの場合も多くあります。早期がんでは、単純に胆のうだけを切除する単純胆のう摘出で治療はすみます。その後の生活も、以前とほとんど変わりません。
一方、黄疸も含めてそれ以外で発見される胆のうがんは、ほとんどがか��り進行していて、中間はほとんどないそうです。木下さんは「胆のうがんは、腹膜播種を一番起こしやすいがんで、神経に沿って浸潤し広範囲のリンパ節転移や肝臓への浸潤を起こすことが多いからです」と語っています。
したがって、手術適応になるのは胆のうがん全体の2割程度にすぎません。また、進行がんで手術可能な場合でも、大がかりな手術になることが多いのです。
肝臓に浸潤している場合は、胆のうと胆管、さらに周囲のリンパ節と一緒に肝臓の一部を系統的に切除する必要があります。 「肝臓への浸潤がかなり深い場合や右の肝動脈ががんに巻き込まれている場合は、肝臓の右葉を丸ごと切除する必要がある」そうです。また、膵臓の裏や十二指腸まで広がっていれば、これらに加えて膵頭十二指腸も切除する拡大手術が行われることになります。
しかし、ここまで手術を行ってもなお、下部胆管がんや乳頭部がんに比べると手術成績は、決して良くないといいます。「目に見えるがんを全て切除できた場合、つまり根治手術ができた場合でも、目に見えないミクロのがんが残存していることがあるのです。これが、再発や転移となってやがて現れるのです。だからこそ胆のうがんや肝門部胆管がん、中部胆管がんは難治がんと言われるのです」と木下さんは語っています。
胆道がんの早期発見
胆道がんは、自覚症状に乏しく、「黄疸がない状態で見つかることは、学会で報告されるほど珍しい」といいます。手術できる状態、つまりできるだけ早く発見することが、胆道がん克服の唯一の道であるといっても過言ではありません。
そこで、木下さんは「肝機能検査で、アルカリフォスファターゼやGTP、トランスアミラーゼなど胆道系の酵素の値が上昇していたら、放置しないでその原因をみつけることが大切です。胆管の狭窄でみつかるのが理想です」と語っています。
中部胆管がんの治療
周囲の血管に浸潤しやすいがん
中部胆管のすぐ裏には、右の肝動脈と門脈が走っています。そのため、中部胆管がんは門脈や肝動脈に浸潤している可能性が高いといいます。
「門脈にも浸潤しているけれど、肝動脈は右側に浸潤しているだけで門脈と合併切除が可能という場合には、肝臓の右葉を切除し、門脈と右の肝動脈を合併切除して胆管を切除することもあります。しかし、浸潤が強くなると、手術の適応はなくなります。実際には、中部胆管がんは、遠隔臓器への転移や腹膜播種のために手術の適応がなくなることより、動脈や門脈への浸潤が強くなって、手術適応からはずれてしまうことのほうが多いのです」と木下さんは語っています。
部位によっては膵頭十二指腸切除まで必要になることもあれば、高齢で手術のリスクが高かったり、全身状態によって大がかりな手術に耐えられないという場合には、胆管だけの切除で終わらせることもあるそうです。
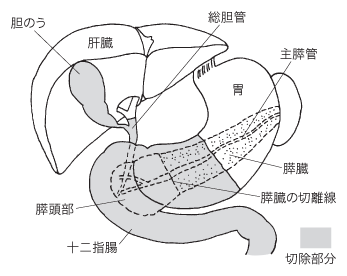
肝門部胆管がんの治療
手術できれば膵臓がんよりも治りやすい
胆管がんの中でも、一番治療が難しいのが肝門部胆管がんです。「ここは、扇の要のような場所です。胆管も門脈も肝動脈もみなここが要になり、ここから分岐しています。その分岐部にまたがってできるのが、肝門部胆管がんなのです」。
どこまでがんが広がっているかで手術で切除する範囲は変わりますが、木下さんによると「部位的に、左右の肝管や肝動脈など両方に浸潤していることが多く、手術の適応にならないケースが多い」といいます。そういう意味では厳しいがんです。
しかし、冒頭でお話したように、胆道がんは手術が完治への唯一の道です。木下さんによると「胆管がんは手術で取りきれれば、膵臓がんよりは治るチャンスがあるのです」と語っています。そのために、胆のうがんや中部胆管がんと同様、肝門部胆管がんでも拡大手術が行われています。
たとえば、肝門部胆管がんでは胆管のがんの広がりに応じた積極的な肝臓の部分的な切除が必要になります。この場合、以前はがんの広がりに応じた肝臓の系統的切除などを行っていました。しかし、現在は術式が単純化され「どちら側にがんが広がっているかで、肝臓の右葉をとるか左葉をとるかを決め、加えて尾状葉を切除するのが標準的」だそうです。ただ、尾状葉は肝臓の裏側にあるため、手術はかなり難しいそうです。さらに、胆管を門脈や肝動脈から剥離して肝臓に入るギリギリのところで切断します。場合によっては膵頭十二指腸切除も加えられます。
「その後、肝臓の切除によって露出した肝内胆管をひとつずつ繋いでいくわけですから、非常に難しい手術になります」
しかし、それだけリスクの高い手術をして、どれだけの人が命を救われるのか、その点も考えていかなければいけないと木下さんは語っています。これは施設や医師によって、考え方が異なっているそうです。
実際にはこうした肝膵同時切除手術で、20年前には手術死が20パーセント、あるいはそれを超える数字も報告されていたといいます。つまり、胆道がんでは手術が唯一の助かる道であり、そのために医師も拡大手術まで行って頑張っているけれども、逆に手術そのものによって命を落とすケースも少なくはないというのが、偽りのないところなのです。
そこで、手術の安全性を高めるために、それぞれの施設でさまざまな工夫が行われています。それによって「まだ高いところもありますが、全体では手術死は5~10パーセントというところで落ちついています」と木下さんは語っています。
胆道がんでは、術後抗がん剤などによる補助療法を行って、有効であるという報告はありません。そのため、国立がん研究センター東病院の場合基本的には手術のみで治療は終了となります。


