判断が分かれる難しい「がん」だから、治療の意義と選択肢をおさえたい ガイドラインを知って胆道がんの確実な治療を受けよう
まず、黄疸の処置が行われる
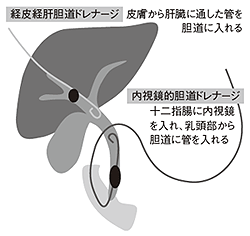
切除手術が可能な場合でも、すぐに手術とならないことがある。手術にもいろいろな方法があるが、胆道と一緒に肝臓を切除する場合には、黄疸が出ている患者さんに対しては、黄疸を改善する処置が必要になるからだ。
「胆汁の通り道がふさがれることで黄疸が起きるわけですが、このような状態が続くと、肝細胞が障害を受けてしまいます。そして、肝臓が弱った状態で肝臓を切除すると、再生がうまくいきません。また、胆汁の流れが滞ることで胆管炎が起きていると、菌が血中に入って敗血症という命にかかわる合併症を起こす危険があります」
そこで、胆汁の流れがせき止められている場合は、胆汁を流す処置が必要になる。行われるのは胆道ドレナージという処置である。代表的な方法として、経皮経肝胆道ドレナージ(PTBD)と内視鏡的胆道ドレナージ(ENBD)がある(図4)。
経皮経肝胆道ドレナージは、皮膚にあけた孔から管を入れ、それを肝臓内の胆管に挿入する方法。超音波画像を見ながら管を入れていく。この管を通して、たまった胆汁を流し出す。
内視鏡的胆道ドレナージは、十二指腸に内視鏡を入れ、乳頭部から胆道に管を入れる方法で、管は鼻から体外へ出す。この管からたまった胆汁を流し出す。
「このようにして胆汁を流すことで、黄疸がよくなりますし、胆管炎を予防することができます。また、胆汁内のがん細胞を調べたり、管を入れたルートを利用して検査を行い、がんがどこまで進展しているかを調べたりすることもあります」
留置した管を通して胆管内に造影剤を入れ、胆管の造影撮影が行われることがある。このような検査で、切除手術が可能かどうかがはっきりすることもある。
切除手術の方法は3種類に大別
切除手術は、がんが胆道のどこにでき、どこまで広がっているかによって、切除範囲が決まる。切除手術には、大きく分けて次の3つの方法がある(図5)。
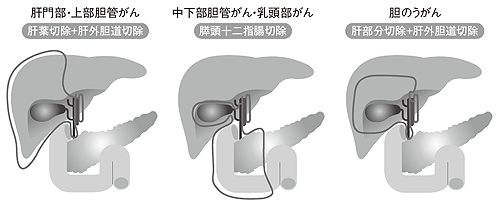
肝門部胆管がん、上部胆管がん の場合
肝臓外の胆管と胆のう、がんが肝内胆管に広がっていると考えられる右葉か左葉の片方を取る手術が行われる。右葉か左葉のどちらかに行く血管にがんが浸潤し���いる場合は、そちら側の肝臓を切除することになる。
中下部胆管がん、乳頭部がん の場合
膵臓の頭部(十二指腸に近い側)と十二指腸を含め、胆道をすべて切除する手術が行われる。
胆のうがん の場合
胆のうを肝臓の一部を含めて切除する手術が行われる。
いずれの手術でも、胆道を取り除いた後は、肝臓と小腸をつなぎ、胆汁が小腸に流れるようにする。
「胆道がんの手術は、胃や大腸の手術に比べると、患者さんの身体的負担が比較的大きいと言えます。とくに肝臓や膵臓を切除する手術は、負担の大きな手術です」
切除手術は開腹手術が基本である。胆石で胆のうを摘出する場合はほとんどが腹腔鏡手術だが、ガイドラインには次のように記載されている。
『胆のうがんを疑う症例に対して腹腔鏡下胆のう摘出術は勧められず、原則的に開腹胆のう摘出術を行うことが望ましい。(推奨度C1)』
「胆のうがんの手術では、肝臓の一部を切除する必要があります。また、胆汁がもれた場合、そこから再発する危険性があるため、それを防ぐためにも開腹手術が望ましいのです」
再発の可能性が高い場合術後化学療法を
| 1期 | 2期 | 3期 | 4a期 | 4b期 | |
| 胆のうがん | 87.5% | 68.7% | 41.8% | 22.3% | 6.3% |
| 肝門部・上部胆管がん | 69.5% | 43.3% | 30.5% | 22.3% | 7.2% |
| 中下部胆管がん | 59.5% | 39.3% | 32.6% | 29.6% | 9.7% |
| 乳頭部がん | 82.9% | 66.8% | 49.9% | 33.9% | 0.0% |
胆道がんの治療成績は、5年生存率を示した表を見ても明らかなように、基本的にあまりよくない(表6)。切除手術を行っても再発することが多いからだ。そこで、再発を防ぐために、術後化学療法が行われることがある。
「胆のうがんや乳頭部がんの1期なら、5年生存率が8~9割なので、これなら術後化学療法はいらないでしょう。しかし、それ以外のがんや、3期以降では、再発するケースが非常に多いのです。何とかして、こういう人たちを救いたいということで、術後化学療法が行われています」
ただし、術後化学療法が再発予防に有用であることを示したエビデンス(科学的根拠)は、現在のところない。ガイドラインには次のように記載されている。
『現状では推奨すべきレジメンがないので、臨床試験として行われることが望まれる。(推奨度C1)』
- ゲムシタビン(ジェムザール®)
- テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム(TS-1®)
- シスプラチン(ブリプラチン®/ランダ®)
- テガフール・ウラシル(UFT®)
- シタラビン(キロサイド®)
- ドキソルビシン(アドリアシン®)
現在、わが国で胆道がん治療に使用できるのは、表に示した抗がん剤である(表7)。ガイドラインが刊行された時点では、シスプラチンはまだ承認されていなかったが、その後承認された。術後化学療法で使われるのは、TS-1(*)かジェムザール(*)が多いという。
「TS-1は経口薬なので、点滴に時間をとられなくてすむなど、利便性の面から選択されることが多い抗がん剤です。ジェムザールは点滴ですが、外来治療が可能で、点滴時間も比較的短くてすみます」
中には術後化学療法が行えない人もいる。手術後に合併症が起きた人、肝機能が悪い人、高齢者、通院が困難な人などである。
*TS-1=一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム
*ジェムザール=一般名ゲムシタビン


