判断が分かれる難しい「がん」だから、治療の意義と選択肢をおさえたい ガイドラインを知って胆道がんの確実な治療を受けよう
手術ができない場合ステントを入れることも
- 化学療法
- 放射線療法
- 胆道ステント
- 光線力学的療法
手術ができない場合でも、黄疸などの症状がある場合には、ドレナージが行われる(表8)。基本的な方法は、さきほどの経皮経肝胆道ドレナージと内視鏡的胆道ドレナージで、手術前に行う場合と同じである。ただ、手術できない患者さんでは、ステントを入れることが多い。
ステントとは、胆汁の流れを確保するために、胆道に留置する管のことである。プラスチック製や金属製などがあり、柔軟性があるもの、長いもの、短いものなど、いろいろな種類がある。
「がんのできている部位や広がりなどに応じて、適当なステントが選ばれます。これで胆汁は流れるようになりますが、基本的にステントは詰まりやすく、交換が必要になることもあります」
その他に、黄疸を改善するため、手術で胆管を小腸につなぐ方法もある。ただし、現在ではステントによる治療が中心になっている。
化学療法に新たなエビデンスが登場
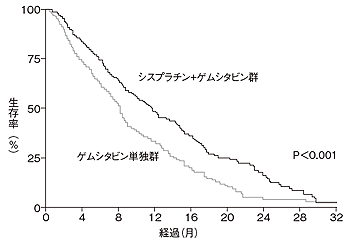
手術できない胆道がんの治療としては、化学療法、放射線療法などが行われる。
化学療法で使用できる抗がん剤は、術後化学療法で紹介したものと同じである。ガイドラインには、ジェムザールまたはTS-1について、『有用性が期待できる可能性がある。(推奨度C1)』と記載されている。
「その後、ジェムザールとシスプラチン(*)の併用療法で、切除できない胆道がん患者の生存期間が延長するという研究結果が、世界的な医学雑誌に掲載されて注目されました(図9)。今後、ガイドラインが改訂されるときには、この併用療法が第1選択の治療法となっている可能性もあります」
一般的には、ジェムザール、シスプラチン、TS-1がよく使われており、3剤のうち2剤を組み合わせることが多い。
化学療法は副作用もあるため、全身状態が良好であることが、実施するための条件となる。
切除手術ができない患者さんに対する放射線治療に関して、ガイドラインには、『放射線療法を行うことを考慮してもよい。(推奨度C1)』となっている。そして、放射線治療の目的は、がんを小さくすることで延命を図る、ステントが詰まるのを防ぐ、黄疸の軽減、痛みの緩和などがあげられている。
「手術ができず、抗がん剤も使えない場合に行われることが多いと思います。ただ、胆道は十二指腸や門脈などの重要臓器が近くにあるので、位置的に放射線を照射しにくい臓器だと言えます」
こうした事情で体の外から照射する外照射だけでは限界がある。そのため、腔内照射を併用することもあり、ガイドラインでも推奨されている(推奨度C1)。胆道ドレナージのために留置してある管などを利用し、放射線の線源を一時的に胆道内に入れ、内側から放射線を照射する治療法である。
化学療法、放射線療法以外に、光線力学的療法(*)という治療法もある。レーザーに反応する物質を注射し、がん細胞にそれを集積させてからレーザーを照射し、がん細胞を破壊する治療である。ガイドラインでは、『有用性を支持する報告が近年みられ、行うことを考慮してもよい。(推奨度C1)』となっている。
*シスプラチン=商品名ブリプラチン/ランダ
*光線力学的療法=フォトダイナミック・セラピー
胆道がんの治療はエビデンスが少ない
現在刊行されている『胆道癌診療ガイドライン』は、05年までに世界で報告された信頼できる論文を元に、推奨できる診断法や治療法を紹介している。だが、胆道がんの患者数が多くないこともあり、他のがんに比べ、信頼できる臨床試験が非常に少ない。そうした影響で、推奨度C1が圧倒的に多く、推奨度AやBはごくわずかという内容になっている。
しかし、05年以降も研究は進んでいるため、ガイドラインの内容は古くなりつつある。数年以内には改訂版が刊行されそうだという。
「化学療法の分野で、ジェムザールとシスプラチンの併用療法のエビデンスが出てきたように、新たな研究も進んでいます。診断に使われる新しいバイオマーカーの研究や、分子標的薬の研究も進んでいます」
数年後の改訂版には、そういった研究成果が盛り込まれているのかもしれない。


