分子標的薬や、多様な治療法の組み合わせの登場で着々と改訂が進行中 膀胱がんの「診療ガイドライン」の注目ポイント
ステージ2、3なら膀胱摘除とリンパ節郭清
ステージ2、3の標準治療は、根治的膀胱摘除術と骨盤リンパ節郭清術である。エビデンスはしっかりしていて、
〈現時点ではこれ以上の治療効果を保証する治療法はない。推奨グレードA〉
とまで書かれている。
新しい話題としては、術前補助化学療法の有効性が示唆されている。
〈生存率向上の効果が示されているのはシスプラチン(一般名)を含む多剤併用術前化学療法である。推奨グレードA〉
ただし、この治療は日常診療では標準的には行われていない。
手術で膀胱を取ると、尿路変向が必要になる。いろいろな方法があるが、ほぼ正常な排尿状態が得られるという点で、自然排尿型尿路再建が推奨されている。
「できることなら自然に排尿するのがいいというのは当然でしょう。どのような尿路変向を行っても、がんの治療成績に影響しないことは明らかになっています」
自然排尿型膀胱再建を行うためには、尿道を残せることが必要になるという。
効果が同等で副作用が軽いGC療法が選ばれている
膀胱がんの全身化学療法として、かつてはMVAC療法が広く行われていた。メソトレキセート(一般名メトトレキサート)、エクザール(一般名ビンブラスチン)、アドリアシン(一般名ドキソルビシン)、シスプラチンの併用療法である。効果は高いが、強い副作用が出ることで知られていた。白血球の減少、下痢などの消化器症状、口内炎、脱毛などが主な副作用だ。
これに対し、副作用が軽い治療法として、GC療法が行われるようになってきた。ジェムザール(一般名ゲムシタビン)とシスプラチンの併用療法である。08年にジェムザールが保険適応となり、日本でもGC療法が行えるようになった。
こうした状況で、MVAC療法とGC療法はどちらが有用かという問いに、ガイドラインはこう答えている。
〈(略)両者とも治療効果は同等であることが報告された。有害事象は、好中球減少症、口内炎、脱毛などであり、GC療法の方がより軽微である。推奨グレードA〉
MVAC療法とGC療法を比較した臨床試験では、生存期間に有意な差はない(図4)。ところが、有害事象の差は明らかだったのだ。
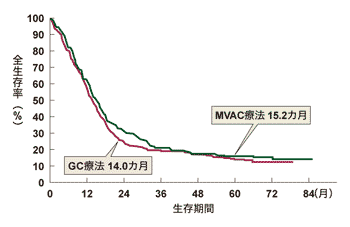
「効果が同じなら、副作用が軽いほうがいいというのは当然です。NCCNのガイドラインでも、EAU(欧州泌尿器科学会)のガイドラインでも、GC療法が第1選択となっています」
ガイドライン刊行後の新しい治療法
第1版のガイドラインが刊行されたのは09年だが、すでにいくつかの治療法が新たに登場してきている。それを列挙すると、次のようになる。
●筋層非浸潤性膀胱がんにおけるBCG維持注入療法の確立
「海外でも国内でも臨床試験の結果が報告され、この治療の有用性が明らかになっています」
●同ステージにおける膀胱温存
「TUR-Bt、放射線療法、化学療法を組み合わせる膀胱温存治療のデータが、いくつか報告されています」
●全身化学療法におけるアンフィット・ペイシェントの概念確立と、それに対する化学療法の標準化
「アンフィット・ペイシェントとは、合併症をたくさん持っていて、体が弱っている人のことです。副作用の軽いカルボプラチン(一般名)を用いた併用療法や、白金製剤を用いない併用療法が有効です」
改訂された第2版のガイドラインには、これらの内容が入ってくる可能性がある。改訂に向けての作業は始まっているそうだが、第2版の刊行時期はまだ決まっていないようだ。
同じカテゴリーの最新記事
- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!
- 免疫チェックポイント阻害薬や抗体薬物複合体の登場で急激に変わった進行膀胱がん(尿路上皮がん)の薬物治療
- 尿路上皮がん(膀胱・腎盂・尿管)に新薬の期待 進行した尿路上皮がん治療に選択肢が増える
- 筋層浸潤膀胱がんに4者併用膀胱温存療法を施行 ~生命予後や合併症抑止に大きく貢献~
- 筋層浸潤性膀胱がんの最新情報 きちんと理解して、治療選択を!
- 膀胱を残す治療という選択肢を より多くの人が選べるよう実績を積んでいます
- 自分に合った尿路ストーマ装具で日々の暮らしをより豊かに
- 膀胱がんの基礎・最新治療 高齢化に伴い罹患率が上昇 5年生存率は病期別に10~90%
- 低侵襲、しかしがんの芽はしっかり摘む! 膀胱をとらずに治す「大阪医大式膀胱温存療法」とは


