膀胱を温存する治療も、新膀胱を再建する技術もより積極的に ここまで進んだ! 進行膀胱がんの最新治療
化学放射線療法で膀胱を残す
浸潤がんで膀胱全摘術を行っても、予後は必ずしもよくない。5年生存率は全体で50~60パーセントといわれている。その上、膀胱を失うことによるQOL(生活の質)の低下も否定できない。
一方で、膀胱がんの化学療法に対する感受性は比較的高いことから、20年ほど前から行われるようになってきたのが、抗がん剤と放射線の併用によって膀胱を残したままがんをたたく方法、膀胱温存療法だ。
以前から、膀胱全摘術の前に術前補助療法として化学放射線療法が行われてきた。その後に、いざ手術して膀胱を取ってみると、がんが消えてしまった人がいたことから、「ケースを選べば膀胱をとらなくても済むのではないか?」との考えで始まった。
アメリカではボストンにあるマサチューセッツ・ゼネラル・ホスピタルで行われるようになり、日本でもほぼ同時期に筑波大学をはじめとしていくつかの病院で始められた。
どんなケースが適応かというと、小さくて腫瘍の数が1つしかない場合が最も適している。筑波大学では、原則的に大きさが3センチ以下の浸潤がんで、腫瘍の数が1つしかない場合を適応としている。これまでの成績では、80パーセントの患者さんでがんの残存もなく、膀胱を残すことができている。全生存率は66パーセントで、膀胱全摘術と比べても同等以上であり、がん特異的生存率(膀胱がんによって死亡していない人の割合)は81パーセントという。
動注療法でがんを狙い撃ち
膀胱温存療法のやり方は施設によって違い、宮永さんが行っているのは「筑波大学方式」と呼ばれるもの。
まず内視鏡で腫瘍を可能な限り切除し、動注化学療法と放射線療法を併用して行う。動注療法は直接、腫瘍に高濃度の抗がん剤を投与するのでがんを殺す力が強く、副作用は点滴で全身に投与する場合より少なくて済むのが利点。
血管造影を行って細い管(カテーテル)を左右の足の付け根の大腿動脈から刺し入れ、先端を膀胱の近くの動脈内に留置して、抗がん剤のメソトレキセート(一般名メトトレキサート)とシスプラチン(商品名ブリプラチンまたはランダ)を注入。これを3週間ごとに3回行う。
動注療法を行っている間に、膀胱全体と周辺のリ��パ節に放射線(X線)を照射する。
これらの治療が終わった段階で、もう1度内視鏡でがんが存在したところの組織を採り、顕微鏡でがん細胞の有無を確かめる。がん細胞がないことが確認されれば、がんがあった場所だけをねらって放射線を追加照射するが、がん細胞が確認されたときは、手術に切り換えて膀胱全摘をする。
「膀胱の放射線の耐用線量(耐えられる線量)は60~65グレイです。それ以上かけると膀胱が萎縮してしまいます。そこで私たちは、最初にかける放射線量は40グレイにとどめ、追加の放射線は20グレイとし、合計で60グレイにおさまるようにしています」
追加の放射線照射を陽子線で行う例も報告されているが、成績には差がないという。
膀胱温存療法でがんが消えても、半数ぐらいの人では膀胱に新たな腫瘍が再発する。ただし、再発した腫瘍のほとんどが浸潤がんではなく表在がん。内視鏡による切除で治すことができるという。
副作用としては、放射線による頻尿や、抗がん剤による吐き気、脱毛、骨髄抑制、腎機能低下などがあげられる。
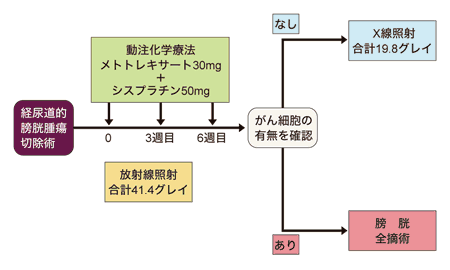
転移している場合は化学療法
がんが周辺臓器に広がったり、遠隔臓器に転移している場合は、手術の適応にはならず、全身化学療法が行われる。
従来、標準的治療としてM-VAC療法と呼ばれる抗がん剤治療が行われてきた。メソトレキセート、エクザール(一般名ビンブラスチン)、アドリアシン(一般名ドキソルビシン)、シスプラチンの4剤併用療法だ。
M-VAC療法の奏効率は6割ぐらいだが、効果が持続せず、がんが小さくなったり、ときには消えてしまっても、やがて再発してくる。また、生存期間は14カ月ぐらいで、治療しない人とそれほど大きな差がつかない問題点もあった。
その一方で抗がん剤による副作用は強く、とくに目立つのは骨髄抑制。口内炎も高い頻度であらわれ、食事が満足にとれないことで疲弊感を訴えるケースが少なくないという。ほかに吐気・嘔吐、消化器症状、腎機能障害などもあらわれる。
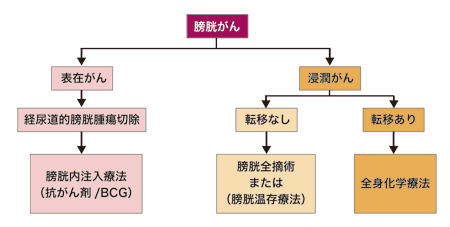
より副作用の少ないGC療法
近年、M-VAC療法に代わる全身化学療法として注目されているのがGC療法だ。ジェムザール(一般名ゲムシタビン)とシスプラチンの併用療法で、ヨーロッパでの大規模な臨床試験の結果では、効果はM-VAC療法と同等で、副作用が少ないことが報告された。
M-VAC療法に比べ、口内炎が圧倒的に少なく、白血球数の減少や腎障害なども少ないことがわかった。現在、欧米ではM-VAC療法に代わるものとして推奨され“ 世界標準” の治療法となっている。
日本でも、最近になってようやく膀胱がんの治療薬としてジェムザールが承認され、全身化学療法の第1選択としてGC療法が行われることが多くなってきている。
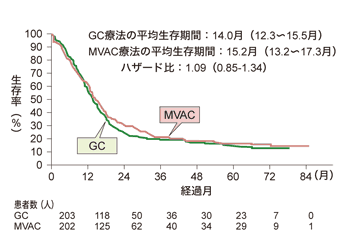
では今後、膀胱がんに有望な薬剤は出てくるのだろうか。宮永さんによると、現在、分子標的治療薬を抗がん剤と併用した臨床試験など、いくつかの試験が進行中だという。
「現在、腎がんで使われているスーテント(一般名スニチニブ)とシスプラチンを併用した臨床試験などが行われています」 ただし、効果についてはまだ未知数とのこと。今後、より有効な薬剤の開発が待たれる。
同じカテゴリーの最新記事
- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!
- 免疫チェックポイント阻害薬や抗体薬物複合体の登場で急激に変わった進行膀胱がん(尿路上皮がん)の薬物治療
- 尿路上皮がん(膀胱・腎盂・尿管)に新薬の期待 進行した尿路上皮がん治療に選択肢が増える
- 筋層浸潤膀胱がんに4者併用膀胱温存療法を施行 ~生命予後や合併症抑止に大きく貢献~
- 筋層浸潤性膀胱がんの最新情報 きちんと理解して、治療選択を!
- 膀胱を残す治療という選択肢を より多くの人が選べるよう実績を積んでいます
- 自分に合った尿路ストーマ装具で日々の暮らしをより豊かに
- 膀胱がんの基礎・最新治療 高齢化に伴い罹患率が上昇 5年生存率は病期別に10~90%
- 低侵襲、しかしがんの芽はしっかり摘む! 膀胱をとらずに治す「大阪医大式膀胱温存療法」とは


