抗がん剤と放射線を併用することによって、QOLの高い生活ができる 進行がんでも、膀胱全摘に引けを取らない膀胱温存療法
治療成績も全摘術に負けていない
四国がんセンターでは、膀胱温存療法の対象を、本来膀胱全摘術の適応となるT2(TNM分類のT=腫瘍の大きさ)からT3、さらに普通は手術の適応にならないT4の患者さんまで含めている。そして2007年11月までに、約80件の膀胱温存療法を実践してきた。もちろん膀胱全摘術も行っているが、現在は3対7か4対6の割合で温存療法を選択する患者さんが多いという。
「患者さんはがんが膀胱じゅうに広がっているとか、膀胱の外側にしっかり及んでいるなど、とんでもなく進行している症例が多く、簡単に治るような人はいません。『どうしても手術がいやなのですね?』と十分確認してから、徹底的にやってみるということになるのです」
住吉さんはこれまでにこうした厳しい症例を含めて約80例に膀胱温存療法を施してきたが、患者さんの5年生存率は75パーセントを超える。ちなみに膀胱がんで膀胱全摘の治療を行った場合の5年生存率はアメリカなどのデータでは50~70パーセントといわれている。温存療法は治療成績の面でも全摘術に負けていないようだ。
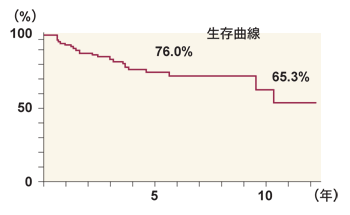
「似たような症例を無作為に振り分けて比較する科学的なレベルの高い臨床試験を行ったわけではないので確かな根拠があるとはいえませんが、少なくとも膀胱温存術の治療成績が全摘術に劣るとは思えません」
日本で膀胱温存療法を実践している施設は、他に、筑波大学病院や九州大学病院があり、それ以外にいくつかの小さな施設でも行われているが、それらの施設で適応としているのはT3までである。なかには、抗がん剤と放射線の使い方についてきちんとしたフォーマットができていない施設もあるそうだ。
また、欧米でも膀胱温存術は日本と同じように実験的治療として進められている。治療方法はだいたい同じだが、日本では抗がん剤の使い方が動脈内注入法が��いのに対して、欧米では静脈内への点滴で行うことが多い。日本のほうがかなり治療成績がよく、以前、ある国際学会で「オリエンタルマジック」とコメントされている。
骨髄抑制としびれが問題
抗がん剤を用いる膀胱温存療法では、当然副作用も伴う。まず、骨髄抑制という障害は必発だ。血液の成分は骨の中にある骨髄で作られているが、ここにダメージが与えられるためそれが作られなくなってしまう。とくに細菌を殺す役割を持った白血球が少なくなるため、感染症にかかりやすくなり、命に関わる事象も起こる危険がある。
もう1つ起こりがちな副作用は末梢神経障害で、とくに動脈内注入を行っているときに足の裏にしびれが生じる。スリッパを履いたときは足の裏の違和感のため階段が昇りにくいといった訴えが多くなる。ただ歩けなくなるほど強いものではなく、人によってはこの副作用はまったく出ないこともある。
「これらの副作用はいくらでもコントロールできます。白血球の低下に対してはG-CSFという薬で対策を立てることができます。これまで膀胱温存療法の治療で命を落とした人はいません。しびれもそれ自体を抑えることはできませんが、マッサージをしたり、温めたりすれば和らげることができます」
一方、放射線照射により出血性膀胱炎という障害が起こることがある。そのためこれまでに2例で輸血が必要となり、その内の1例は膀胱切除に至った。
「ただし、これは放射線量を60グレイにしていたとき起こった事象です。そのために現在は42グレイに線量を減らしています。減らしてからは膀胱炎の副作用はまったく出ていません」
リンパ節転移で5年生存をクリア
膀胱温存療法を求めて四国がんセンターへ来る患者さんは関東以南を中心とする全国から集まってくる。その中には、医師や大学医学部教授など医療関係者も含まれているそうだ。
数年前、金沢の大学病院に勤務する40代半ばの医師が妻を伴って来院した。自分の勤める病院の泌尿器科でT3の膀胱がんと診断され、膀胱全摘術を受けるよう勧められたが、拒絶し、住吉さんに「子どもが欲しいので、膀胱を取るのは絶対いやだ」と訴えた。
「膀胱を取っても子どもはできるのですが、本音は『どうしても手術を受けたくない』ということです。結局温存療法の治療を始めたのですが、医師なので抗がん剤の副作用などは全部わかっており、治療の10日間のみ入院し、あとは金沢に帰られました。以後は自分で血液検査を行い、メールでデータを送って来られ、それをみて指示するようにしました」
現在までこの患者さんに再発はなく、医療現場で忙しく立ち働いているそうだ。
6、7年前に東京のがん専門病院から紹介されて来院したのは某大学医学部教授だった。「飛行機を操縦したいので、尿路変向は困る」と膀胱温存療法を希望した。骨盤内のリンパ節に転移があり、全身治療をしたほうがよいと判断し、シスプラチン、メソトレキセート、ビンブラスチン、アドリアシンの4種類の薬剤を組み合わせたM-VACという抗がん剤治療を点滴で行った。もちろん膀胱への放射線照射も併用した。
「この先生も、今もとてもお元気です。私たちのところへ来院される患者さんは、しっかり説明を受けているので、『死んでもいいから膀胱を取るのはいや』という人が“最後の砦”のように覚悟されて来ることが多いのです。私たちのところでも、この治療法の利点と不利な点を再度説明しますが、多くのケースで膀胱温存を希望します。その希望をかなえて差し上げるように全力でこの治療を行っています」
(構成/林義人)
同じカテゴリーの最新記事
- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!
- 免疫チェックポイント阻害薬や抗体薬物複合体の登場で急激に変わった進行膀胱がん(尿路上皮がん)の薬物治療
- 尿路上皮がん(膀胱・腎盂・尿管)に新薬の期待 進行した尿路上皮がん治療に選択肢が増える
- 筋層浸潤膀胱がんに4者併用膀胱温存療法を施行 ~生命予後や合併症抑止に大きく貢献~
- 筋層浸潤性膀胱がんの最新情報 きちんと理解して、治療選択を!
- 膀胱を残す治療という選択肢を より多くの人が選べるよう実績を積んでいます
- 自分に合った尿路ストーマ装具で日々の暮らしをより豊かに
- 膀胱がんの基礎・最新治療 高齢化に伴い罹患率が上昇 5年生存率は病期別に10~90%
- 低侵襲、しかしがんの芽はしっかり摘む! 膀胱をとらずに治す「大阪医大式膀胱温存療法」とは


