理論的には理想的ながんペプチドワクチンの本当の効果は? 実用化に1歩近づいた膀胱がんのワクチン療法
いよいよ患者での臨床試験を開始
このような基礎的な研究によって、MPHが膀胱がんの特異的抗原で細胞増殖に必須の遺伝子であること、MPH由来のペプチドが免疫に認識されて、CTLを作らせることが判明した。つまり、ワクチンとしての基本的条件を満たすことがわかったのである。
患者さんの検体の採取は岩手医科大学が中心となって行い、さらに遺伝子の抽出およびワクチン候補遺伝子の機能解析は、岩手医科大学から東京大学医科学研究所への留学医師らを中心に行い、さらにペプチドワクチンの開発は東京大学医科学研究所で行われた。いよいよ、あとは患者さんでの臨床試験である。日本では、薬の臨床試験は薬事法によって製薬会社が行うことが多いが、これには時間もかかる。藤岡さんは「一刻も早く患者さんに届けたいというのが私たちの思いです。そのためには、まず少人数でも医師主導の臨床研究で結果を出したいと考えたのです」と語る。医師法に基づく医師主導の臨床試験ならば、数年で結果が出せる。それを引き金に本格的なワクチン開発に結び付けようと考えたのである。
他の治療法で効果がなかった患者に抗腫瘍効果
こうして2007年2月、安全性を確認する第1相臨床試験が開始された。参加した患者さんは49歳から79歳までの男女6人。いずれも膀胱がんが進行し、治療手段が無くなった患者さんだ。「HLAの型がA2402であること、がん細胞にMPHかもう1つの候補遺伝子が発現していること」が臨床試験に参加できる条件。誰にでも効果が期待できるわけではないのである。
ちなみにもう1つの遺伝子も基礎研究で同じような結果が得られたそうだ。実際には、人工的に作られたペプチドの粉末を免疫賦活剤と混ぜて週に1回、脇の下か足のつけ根に皮下注射で投与する。つまり、リンパ節が多い部分を狙って投与する。4回を1コースとして、5週目に評価が行われた。
MPHかDEPの遺伝子発現があれば、そのペプチド���1mg、脇の下か足のつけ根に注射して投与。原則として週1回ずつ4回を1コースとする
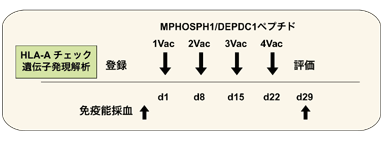
「基礎研究の結果からみても、安全性は問題ないだろうと思っていたのですが、副作用はありませんでした」と講師の小原航さん。1人だけ腕に湿疹が出た人がいたが、この人は抗がん剤でも同じ症状が出ていて、1週間休んでペプチドワクチンを再開。以後は何の問題もなかった。アレルギーなのか、湿疹の原因はわかっていない。しかし、藤岡さんたちを驚かせたのは副次的に観察したがんに対する効果だった。
「予想以上に抗腫瘍効果が高かったのです」
たとえば、ある男性は抗がん剤も放射線も効果がなく、2007年6月からペプチドワクチンの臨床試験に参加した。この人の場合、MPHともう1つの遺伝子も発現していたので、毎週2種類のペプチドワクチンを投与した。その結果、治療中から見る間にがんが縮小し、9月の検査では、画像上ではほとんどがんが消えてしまったのである。これには、藤岡さんもびっくりしたという。結局、安全性には問題ないことが確認され、さらに6人のうち4人でCTLが誘導され、がんが縮小した。
「これだけがんが進行して、他の治療では全然効果が無かった人たちなので、この効果は予想以上です」と藤岡さん。残念ながら、1年以上生存した患者さんはいなかったが、ふつうこの状態になると余命は3カ月から半年という。中には、転移した肺の病巣が縮小、空洞化した人もいたそうだ。
| 性別 | ワクチン投与 | 全身 副作用 | 遅延型 過敏反応 | 評価病変 | 評価 | MPHOSHP1 | DEPDC1 | 腫瘍増殖 停止期間 (日) | 全生存 期間 (日) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 期間(月) | 発現 | CTL | 発現 | CTL | ||||||||
| 1 | 男 | 4 | 1 | なし | なし | リンパ節 転移巣 脳転移 | 増悪 | ○ | × | ○ | × | 29 | 56 |
| 2 | 女 | 13 | 6 | なし | なし | 膀胱 (局所再発) | 症状安定 (3.3mo) | ○ | × | ○ | ○ | 176 | 296 |
| 3 | 男 | 24 | 8 | 発疹 | なし | 肺転移巣 | 画像所見に 反応有 | × | × | ○ | ○ | 239 | 269 |
| 4 | 男 | 10 | 3 | なし | なし | 膀胱 (局所再発) | 画像所見に 反応有 | ○ | × | ○ | ○ | 83 | 83 |
| 5 | 男 | 29 | 10 | なし | なし | 膀胱 (局所再発) | 画像所見に 反応有 | ○ | ○ | ○ | ○ | 322 | 339 |
| 6 | 女 | 12 | 3 | なし | なし | リンパ節 転移巣 | 増悪 | × | 未判定 | ○ | 未判定 | 25 | 111 |
ペプチドの安全性は問題なく、6例中4例においてCTLが増加、抗腫瘍効果がみられた
表在性膀胱がんの再発予防にも期待を寄せる
藤岡さんによると、「第1相試験の結果が発表されてから、進行した膀胱がんの患者さんや再発を繰り返している患者さんから、連日問い合わせが来ています。東京や大阪から岩手まで治療を希望して来られる患者さんも多い」と言う。最後の望みをワクチンに託す患者さんも多いのである。今後は、こうした人も含めて継続的にペプチドワクチン治療を行うと同時に、藤岡さんたちは再発予防にもワクチンを利用することを考えている。
「表在性の膀胱がんを内視鏡でとっても、術後1年で半数以上は再発するのです」
今は、BCG(結核ワクチン)の膀胱内注入が再発予防のスタンダードになっているが、それでも30パーセントが再発する。これをできるだけ0に近づけたいというのが藤岡さんたちの願いだ。これに、ペプチドワクチンを利用しようというのである。
「早い段階でワクチンを投与しておけば、少しでもがん細胞が出てきたときにCTLでつぶすことができるのではないか」と考えているからだ。ワクチンであらかじめCTLを誘導しておけば、即座に反応してがんの芽を叩きつぶすのではないかというのである。ゲノム医科学の第一人者として世界的に知られる東大医科学研究所の中村さんも「膀胱がんに限らず、ワクチンは再発予防に向くのではないか」と発言している。
そこで、すでに表在性膀胱がんの再発予防を目的に、今年3月から第2相試験が開始されている。BCGとの比較試験はまだ無理なので、今回は内視鏡によるがん切除後にBCGの膀胱内注入とワクチン療法を併用し、これまでのBCGの膀胱内注入と、再発率を比較する。2年間で120人ほどの患者さんに参加してもらうのが目標だ。
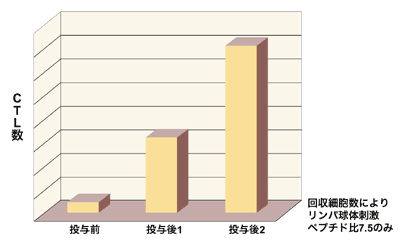
さらに腎がんでもワクチンを開発
さらに、腎がんでもワクチンを開発している。
「進行して転移した腎がんには、サイトカイン療法(免疫機能全体を強化する治療法)が行われますが、効果がある人は2割足らずです。今は分子標的治療薬が注目されていますが、あまりに副作用が強い。やはり新しい治療法が必要なのです」と藤岡さんは語る。
方法は膀胱がんの場合と同じで、患者さん由来の腎がんの細胞からがん抗原を見つけ、ペプチドを捜し出してきた。だが、腎がんの場合は、A02というタイプのお皿に乗るペプチドしか見つからなかったそうだ。
「これを持つ人は30パーセントですが、それでもかなりの人が適応となるのです」と藤岡さんは期待を寄せる。
実際には、同じ手法を使っても、すべてのがんでペプチドワクチンができるわけではないという。
そのがんに特異的で他の重要な臓器に発現していない、がんの増殖に働く遺伝子で、CTLを誘導できる、という条件をクリアするものが必ず見つかるわけではないのだ。遺伝子から探索していくので、他国で開発されたワクチンが日本人に合うとも限らない。藤岡さんによると、今この手法で期待されているのは、「泌尿器科領域では、膀胱と腎」なのだそうだ。
医師主導による臨床試験が順調に進んでも、薬にするためにはあらためて薬事法にもとづく臨床試験が必要になる。しかし、がんペプチドワクチン治療が実現に近づいていることは確かと言えそうだ。ペプチドワクチンが、がん治療の柱の1つになる日ははたしていつになるのだろうか。
同じカテゴリーの最新記事
- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!
- 免疫チェックポイント阻害薬や抗体薬物複合体の登場で急激に変わった進行膀胱がん(尿路上皮がん)の薬物治療
- 尿路上皮がん(膀胱・腎盂・尿管)に新薬の期待 進行した尿路上皮がん治療に選択肢が増える
- 筋層浸潤膀胱がんに4者併用膀胱温存療法を施行 ~生命予後や合併症抑止に大きく貢献~
- 筋層浸潤性膀胱がんの最新情報 きちんと理解して、治療選択を!
- 膀胱を残す治療という選択肢を より多くの人が選べるよう実績を積んでいます
- 自分に合った尿路ストーマ装具で日々の暮らしをより豊かに
- 膀胱がんの基礎・最新治療 高齢化に伴い罹患率が上昇 5年生存率は病期別に10~90%
- 低侵襲、しかしがんの芽はしっかり摘む! 膀胱をとらずに治す「大阪医大式膀胱温存療法」とは


