化学療法と放射線療法の併用で膀胱温存、副作用の少ない世界標準薬の登場も 明るい兆しが出てきた膀胱がんの最新治療
動注化学・放射線療法で膀胱を温存
筋層浸潤がんで膀胱全摘すれば尿路変更が必須で様々な合併症やQOL(生活の質)の低下を伴いがちだが、これを避けるために膀胱を温存する「動注化学・放射線療法」という治療が開発されている。放射線治療にも抗がん剤治療にもがん細胞を殺す効果があり、これを併用することで再発予防効果を高めて膀胱を温存しようとするものだ。赤座さんはこの治療のパイオニアであり、「筑波方式」と名付けている。
「すべての膀胱全摘除術に代わる治療法とは言えませんが、膀胱を温存する試みとしてはうまくいっています。昨年の学会で、『大きさが3センチ程度以下の筋層浸潤がんであれば、筑波方式で90パーセント以上膀胱を残すことができる』と発表しました。最近の大きな成果です」
ただし、筋層浸潤がんのすべてがこの治療の対象となるわけではなく、膀胱を温存しても再発の恐れが少ない症例だけに適用される。がんの大きさはせいぜい3~4センチくらいまでで、腫瘍の数も基本的には1個だけのものに限られる。もちろんリンパ節転移や遠隔転移が認められるものも対象にならない。
「たとえば5~6センチ以上の腫瘍に放射線照射をすれば、放射線障害による委縮のために膀胱が使えなくなってしまうことも危惧されますし、腫瘍を完全に消失させることは困難です。ですから、そういうケースでは膀胱全摘が必要となります。がんの大きさによって膀胱を切除するか、残せるかが次第にわかるようになってきました。他の病院で膀胱全摘を告げられた筋層浸潤がんの患者さんが、動注化学・放射線療法によって膀胱を温存できた例もたくさんあります」
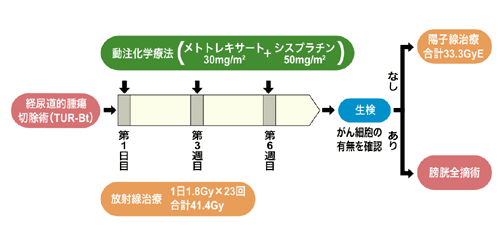
がんを殺��力が強く、副作用は軽い
筑波方式は、TUR-Bt→動注化学療法+放射線治療→陽子線治療という3ステップで進められる。最初のTUR-Btでは切除した患部の組織からがんの悪性度などを調べて、本当にこの治療が適応かどうかを見極める。
メインとなる動注化学療法では、太股の大腿動脈からカテーテルを挿入し内腸骨動脈まで進入させ、抗がん剤のメソトレキセート(一般名メトトレキサート)とシスプラチン(商品名ブリプラチン、ランダ等)を投与する。
直接、腫瘍に高濃度の抗がん剤が投与されるのでがんを殺す力が強いが、点滴で全身に投与する通常の方法に比べて副作用は軽くすむのが特徴。3週間ごとに3回行う。
また、放射線治療は、第1回目の動注化学療法の翌日から1回=1.8グレイを、膀胱のある骨盤の奥に照射する。通常の体外照射で週5回、計23回=41.4グレイを当てる。
この動注化学・放射線療法が終わった段階で、がんがあった部分から組織を採取し、顕微鏡でがん細胞が消えているかどうかを確かめる。がん細胞がなくなっていれば最終ステップの陽子線治療に進むが、がん細胞が残っていると手術による膀胱全摘に切り替えることになる。
最終段階の陽子線治療は、いわば「仕上げ」のようなもの。通常の放射線照射よりもピンポイントで、まだ残っているかもしれない微小ながん細胞を叩き、膀胱がんの再発防止をより確実にしようというのが目的だ。
「筑波方式を導入したいという施設もいくつか出てきましたが、問題はこのメニューで陽子線を使っていること。陽子線治療の装置がある施設が限られているからです。最近は何も陽子線でなくても、普通の放射線でもいいのではないか、という感触を得ています」
副作用の少ないジェムザール*の承認間近
膀胱がんも前立腺など、膀胱の周囲に浸潤したり、肝臓や肺、骨など遠隔臓器に転移している場合は、手術や動注化学・放射線療法などの根治を目指した治療は効かない。全身に効果的な化学療法が行われるのが普通だ。
現在膀胱がんの化学療法にはM-VAC療法という治療法が標準治療として用いられている。メソトレキセート、エクザール(一般名ビンブラスチン)、アドリアシン(一般名ドキソルビシン)、シスプラチンの4剤を組み合わせた治療だ。海外では術前にM-VAC療法を用いると生存期間を延長するという報告が散見されるが、その有用性はまだ確立されていない。
一方、膀胱の切除手術ができない例や遠隔転移を来した膀胱がんの症例に対しては、M-VAC療法の有効性が証明されているが、その効果は十分とは言えない。
ただし、M-VAC療法は、治療中に吐き気や食欲不振、白血球減少、血小板減少、貧血、口内炎など強い副作用が起きることが多い。そのために治療を中断しなければならないケースもしばしばあった。
「M-VAC療法は最初使えていても、15日目と22日目にエクザールとメソトレキセートが入ると、副作用に耐えられなくて完全に投与されないというケースが半分くらいありました。欧米では副作用の少ないジェムザール(一般名ゲムシタビン)にシスプラチンを組み合わせたGC療法が数年前から第1選択とされ、教科書にも記載されているほどの世界の標準治療です」
日本でもジェムザールは今年末か来年初めに、筋層浸潤がんの治療薬として承認される見通しとなっている。
「GC療法はM-VAC療法に比べて生存期間が凌駕するというわけではなく、効果は同等ですが、全体的に副作用が少ないのが魅力です。M-VACの副作用に耐えられないような人、あるいはM-VACで効果がなくなってきたような人に有用と考えられます」
副作用の少ないジェムザールが承認されれば、膀胱がん患者さんにとっては何よりの朗報だ。これでようやく欧米と同水準の治療が受けられることになる。この世界標準薬の承認や動注化学放射線療法の登場によって、今、筋層浸潤がんの治療法が大きく変わろうとしている。
*ジェムザールは、2008年11月25日に「尿路上皮癌」の効能で承認を受けました。
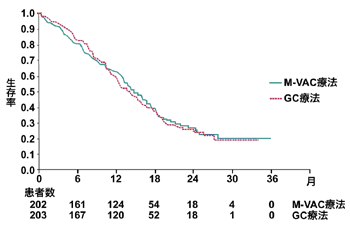
[新旧治療法での主な副作用の比較]
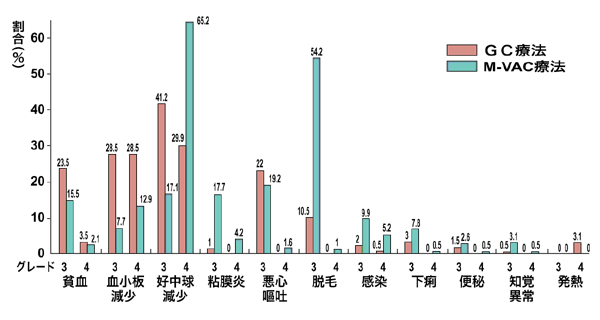
喫煙は危険!発症が早く、悪性度も高い
膀胱がんは喫煙者の発生率が高く、タバコを吸う人が膀胱がんになる危険性は非喫煙者の数倍高いとされている。タバコの発がん物質が体を巡り、最終的に尿として排泄されるとき、膀胱上皮を刺激し続けるためと考えられている。赤座さんたちが膀胱がんの患者さんたちを詳しく分析してみると、喫煙者や喫煙歴のある人たちは、そうでない人たちに比べてがんの発症が平均5~6年早いこと、しかもがんのたちが悪いこともわかった。
「膀胱がんになって同じ経過をたどるとしたら、発症が5~6年早いということになれば寿命が5~6年短いという計算になります。加えて喫煙者のがんは悪性度が高いのですから、もっと差がでるかもしれません。これはすごい話でしょう」
膀胱がんは男性のほうが女性より3倍ほど発生率が高いが、これは男性の喫煙率が高いことが1つの要因と考えられている。ただし、最近日本では全体に喫煙率が下がっているのに、若い女性たちはタバコから離れようとしない。そのうち日本では膀胱がんの男女比は変わってくるかもしれない。
同じカテゴリーの最新記事
- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!
- 免疫チェックポイント阻害薬や抗体薬物複合体の登場で急激に変わった進行膀胱がん(尿路上皮がん)の薬物治療
- 尿路上皮がん(膀胱・腎盂・尿管)に新薬の期待 進行した尿路上皮がん治療に選択肢が増える
- 筋層浸潤膀胱がんに4者併用膀胱温存療法を施行 ~生命予後や合併症抑止に大きく貢献~
- 筋層浸潤性膀胱がんの最新情報 きちんと理解して、治療選択を!
- 膀胱を残す治療という選択肢を より多くの人が選べるよう実績を積んでいます
- 自分に合った尿路ストーマ装具で日々の暮らしをより豊かに
- 膀胱がんの基礎・最新治療 高齢化に伴い罹患率が上昇 5年生存率は病期別に10~90%
- 低侵襲、しかしがんの芽はしっかり摘む! 膀胱をとらずに治す「大阪医大式膀胱温存療法」とは


