進行別 がん標準治療 再発予防にはBCG注入療法が有効。膀胱温存の道も広がってきた
上皮内がん
がんが、移行上皮内にとどまる扁平な上皮内がんの場合は、BCGの注入療法が第一選択です。この場合、がんがどこまで広がっているかわからないので、削ってとることは難しいのです。 この場合、BCGの膀胱内注入療法のみで治療が行われますが、60~80パーセントの人でがんが消失します。これから見ても、表在性のがんの場合70パーセント前後の人に効果があると推測されます。
それでも再発が起きた場合には、2回目のBCG注入療法を行うのが標準的です。鳶巣さんによると、残念ながら最初のときほどの効果はないそうです。
「CR(完全寛解。がんが消失する率)は、3割ぐらいです。完全にがんが消えなければ意味がありませんからね。ただ、いったん消えても長続きしない傾向があります。したがって、再発が起きた場合は、いずれ膀胱の摘出をしなければならないと考えるのが一般的です」
ただし、上皮内がんでも特殊な場合、全体としては上皮がんであるが、一部で粘膜下層まで浸潤していて「スキルスと同じ、つまりかなり壁内への浸潤傾向が強いタイプであると判断されたら、膀胱の摘出を行う場合もある」そうです。鳶巣さん自身も、こうした場合は膀胱摘出に踏み切ることが多いといいます。
「10年ぐらい前、国立がん研究センター時代にデータをとったことがあるのですが、こういうタチの悪い表在性のがんの場合、半数に筋層浸潤があった」というのがその根拠です。臨床的には、上皮内がんは表在性のがんですが、こういう悪性度の高い上皮内がんは、その危険性を考えて治療を行うことが必要なのです。
浸潤性がんの治療
膀胱全摘術+尿路変向術が標準
筋層までがんが食い込んでいますが、まだ膀胱の外に転移していない場合、つまりT2からT3までは、周辺のリンパ節郭清を含めて膀胱全摘術を行い、尿路変向術を行うのが標準的です。男性の場合前立腺と精のう、女性の場合は通常は子宮も一緒に摘出します。
尿路変向とも関連して、ここで問題になるのは前部尿道を残すかどうかです。前部尿道を残したままで放置すると10~20パーセントにがんが再発することが、以前から指摘されているそうです。しかし、現在では膀胱の出口や前立腺に囲まれた部分の尿道にがんがなければ、再発率は低いことがわかり、この場合は前立腺を出た部分で膀胱と一緒に尿道を切断し、前部尿道を残すことができます。
一方、前立腺に囲まれた尿道部分までがんがあれば、尿道も摘出することになります。「中には、どうしても前部尿道を残して、ここから排尿��たいという患者さんもいるので、そういう場合は厳重警戒のもと、再発したら取りますよとお話した上で残すこともある」そうです。
ここで、重要なことは「全摘手術は、少なくとも画像上がんがなくなる、つまり根治を目指して行うべきもので、摘出していい状況をしぼりこまなくてはいけません」と鳶巣さんは指摘しています。たとえば、頭が崩れて扁平になった浸潤がんの場合、まずCTで転移がないか周辺を調べてから手術が行われます。
鳶巣さんによると「膀胱全摘術の5年生存率は、ここ20年ほど40~60パーセントで、変わっていません。筋層の表面にとどまる場合は、60パーセントというところも70パーセントというところもあります。これが筋層を貫通するようになると40パーセント程度」だそうです。施設によって成績に幅があるのは、どういうタイプの膀胱がんを治療したかで、成績がかなり違うからだそうです。
つまり、筋層に浸潤したがんでも、有茎性で内腔にポッコリと飛び出したものならば、5年生存率はほぼ100パーセント近いといいます。膀胱がんの場合、5年間再発がなければ、再発はまずありません。つまり、完全に治ったと言っていいのです。これが、同じ筋層に浸潤したがんでも、表面が崩れてくると成績は低下し、扁平になったものはかなり成績が落ちるといいます。
「実は、この扁平になったものが特殊な上皮内がんで、表在性でも膀胱全摘術が必要とお話したタイプなのです。これは、表在性の間にとってしまうことが重要。表在性でなくなった時点で、たいてい膀胱の外に出ているのです」
実際には、日常臨床で遭遇する浸潤がんのほとんどが、すでに表面の一部が崩れているタイプだといいます。こうなると、5年生存率は4割から6割になります。
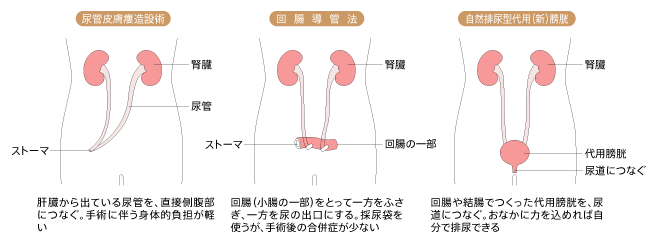
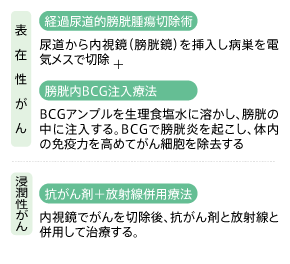
同じカテゴリーの最新記事
- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!
- 免疫チェックポイント阻害薬や抗体薬物複合体の登場で急激に変わった進行膀胱がん(尿路上皮がん)の薬物治療
- 尿路上皮がん(膀胱・腎盂・尿管)に新薬の期待 進行した尿路上皮がん治療に選択肢が増える
- 筋層浸潤膀胱がんに4者併用膀胱温存療法を施行 ~生命予後や合併症抑止に大きく貢献~
- 筋層浸潤性膀胱がんの最新情報 きちんと理解して、治療選択を!
- 膀胱を残す治療という選択肢を より多くの人が選べるよう実績を積んでいます
- 自分に合った尿路ストーマ装具で日々の暮らしをより豊かに
- 膀胱がんの基礎・最新治療 高齢化に伴い罹患率が上昇 5年生存率は病期別に10~90%
- 低侵襲、しかしがんの芽はしっかり摘む! 膀胱をとらずに治す「大阪医大式膀胱温存療法」とは


