進行別 がん標準治療 再発予防にはBCG注入療法が有効。膀胱温存の道も広がってきた
術前M-VAC療法の可能性
では、ここ20年間、膀胱がん治療では、どういう工夫が行われてきたのでしょうか。鳶巣さんによると、「まず、放射線治療をしてから、手術をすることが考えられたのですが、これはうまくいかなかった」と言います。これに対して、抗がん剤には大きな進展がありました。膀胱がんは、中等度に抗がん剤が反応するがんです。シスプラチン(商品名ブリプラチン、ランダ等)が登場して、1985年にM-VAC療法(メトトレキサート、ビンブラスチン、アドリアマイシン、シスプラチン)という4剤併用療法が誕生したのです。これは、「奏効率(腫瘍縮小率)が6割ぐらいでかなり高いのですが、残念ながら膀胱がんは治らないのです。がんが縮小するだけで、半年から1年もたつと、元に戻ってしまうのです」。短いと効果は3カ月。治療に3カ月、効果も3カ月という治療法でした。しかし、残念ながら今もこれを凌駕する化学療法は生まれていないのです。

ジェムザールとシスプラチンの併用療法の効果は
M-VAC療法と遜色ないことが明らかになってきている
そこで、このM-VAC療法の利用法が工夫されています。術前治療として利用すれば手術成績の向上につながるのではないかと考えられました。80年代後半には、鳶巣さんらもかなりM-VACの術前治療を行いましたが、当時は意味がないという結論でした。ところが、2000年頃に「術前に行うM-VAC療法は、5年生存率を15パーセントくらい向上させる」という報告があり、現在見直しが行われているところだそうです。術後補助療法として使った場合は、再発を遅らせるだけで生存期間の延長にはつながらないと結論されています。つまり、「浸潤がんの5年生存率は4~6割で、術前にM-VAC療法を行うと手術成績の底上げにつながるらしいというのが、現在の見方です」と鳶巣さんは語っています。そこで、現在日本でも術前のM-VAC療法の効果を検証するために多施設共同で臨床試験が進んでいるところです。
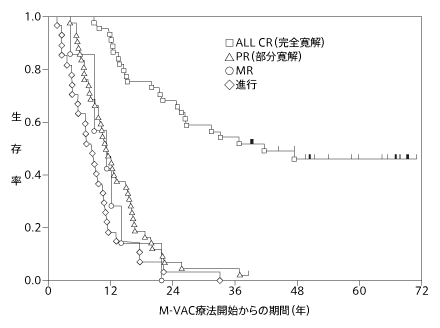
尿路変向術
膀胱を全摘した場合には、尿路変向をして尿の排出ルートを再建する必要があります。鳶巣さんによると、現在日本では「4分の3の人は回腸導管法か尿管皮膚瘻を行っており、復壁に袋を付けて尿を溜めています。4分の1ぐらいの人が代用(新)膀胱を作って尿道から排尿しています」
尿管皮膚瘻
一番単純な方法で、腹部に尿の出口(ストーマ)を作り、腎臓から出た尿管をつなぎます。ストーマに張りつけた袋に尿を溜めて、自分で捨てます。最近では、あまり行われなくなりつつあります。
回腸導管法
小腸の一部をとって尿管につなぎ、一方の端は閉じて、もう一方の端を腹部に作ったストーマにつなげます。ストーマに袋を張りつけて尿を溜める方法です。
代用(新)膀胱(自然排尿型)
以上の2つの方法が、ストーマを使って袋に尿を溜めるのに対し、尿道から排泄できるのがこの方法です。尿道を残すことができた人に行える方法です。腸の一部で代用(新)膀胱を作り、ここに尿管と尿道をつなげます。自然の尿意はありませんが、腹部に力をこめることで尿道から排尿できます。ただし、尿意はないので定期的に排尿する必要があります。
「自己導尿型」といって、代用膀胱をストーマとつなぎ、ここに自分で管をさして尿を排泄するタイプもありますが、これは手術として技術的に難しいこと、また代用膀胱に結石ができやすいなどの問題があり、最近はあまり行われなくなっているそうです。
膀胱温存の可能性を探る
膀胱がんでも、現在は患者さんのその後の生活を考えて、できるだけ膀胱を残して治療する方向で、研究が進んでいます。
鳶巣さんによると、「抗がん剤が非常に効くということから、抗がん剤と放射線の併用で膀胱を残せないかという研究が、1990年頃から行われている」と言います。アメリカでも行われていますが、日本ではとくに盛んであちこちの病院で研究的に治療が行われているそうです。ただし、多施設で協調してきちんとした治療計画にのっとって行われていないため、治療法として確立させるようなエビデンス(科学的根拠)にならないのが現状です。
しかし、アメリカでの400~500例を集めたデータでは抗がん剤と放射線の併用で、手術に近い成績が得られているといいます。「残念ながら、抗がん剤の種類や使い方、放射線の照射量などもバラバラなのですが、もう少しきちんと整理していけば、これは手術に対抗する立派な治療手段になると思います」と鳶巣さんは語っています。近い将来、浸潤がんでも膀胱を残して治療できる可能性がかなり期待できるのです。
ただし、まだ問題点もあります。1つは、治療法が確立されていないこと。そしてもう1つは、うまく行かなかった場合の救済法としての手術が難しくなるという点です。「おそらく、手術成績のいい人、つまり有茎性で突出したタイプのがんの人には、抗がん剤と放射線も効くと思われますが、どういう人にメリットがあるのか、ぜひ明らかにして欲しいと思っています」
他臓器に転移したがん
がんが、周辺や遠隔の臓器に転移を起こした状態になると、残念ながら手術の適応にはなりません。この場合は、M-VACという抗がん剤の併用療法を3~4コース行うのが標準的です。「6割ぐらいの人は反応があって、がんが縮小しますが、半年から1年で元に戻ってしまう」というのが、現状です。
最近、膵臓がん治療に使われるジェムザール(一般名ゲムシタビン)が、ヨーロッパでは膀胱がん治療に認可され、シスプラチンとの併用が始まっています。この方法は、M-VAC療法より副作用が少なく、同等の効果を得られると報告されています。
日本では現在、ジェムザールの臨床試験が行われているところですが、「まもなく、この併用療法が第一選択になるのでは」と鳶巣さんは語っています。
BCG注入療法の副作用
BCG注入療法では、BCGの乾燥粉末を生理食塩水に溶かして、膀胱内に注入します。このあと2時間そのまま我慢して、排尿します。通常、これを週に1回、6~8回ほど外来で繰り返します。鳶巣さんによると、「当日は発熱することもありますが、1回目の治療はケロッとしている人が多い」といいます。これが、3回、4回と繰り返されると膀胱刺激症状が強くなり、排尿後半日ぐらいはトイレが近い、排尿時にしみるなどの症状が現れます。5回目ぐらいになるとさらにトイレが近くなり、これが一晩中続く、さらに回数を重ねるとトイレがもっと近くなり、それが長く続くようになる人が多いそうです。治療が終われば治りますが、気をつけたいのは、時に膀胱が固く萎縮することがあることです。「治療から1週間たっても、1回の排尿量が100CC足らずという場合は、ただちに中止する必要があります」と鳶巣さん。反応には個人差が大きいので、様子を見ながら治療を続けていくことが重要だそうです。
ただし、膀胱炎症状が出る人は、効果も得られやすいというのが、「エビデンスはありませんが、経験的な医師の印象」だそうです。また、治療の当日は多くの人が発熱しますが、翌日、あるいは翌々日に発熱した場合は要注意です。BCGは、牛の結核菌が少し生きているので、これが感染して結核になることがあるのです。しかし、「薬剤に対する感受性がはっきりした菌なので、よほど免疫能力に問題がない限り治療ですぐに治る」そうです。
同じカテゴリーの最新記事
- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!
- 免疫チェックポイント阻害薬や抗体薬物複合体の登場で急激に変わった進行膀胱がん(尿路上皮がん)の薬物治療
- 尿路上皮がん(膀胱・腎盂・尿管)に新薬の期待 進行した尿路上皮がん治療に選択肢が増える
- 筋層浸潤膀胱がんに4者併用膀胱温存療法を施行 ~生命予後や合併症抑止に大きく貢献~
- 筋層浸潤性膀胱がんの最新情報 きちんと理解して、治療選択を!
- 膀胱を残す治療という選択肢を より多くの人が選べるよう実績を積んでいます
- 自分に合った尿路ストーマ装具で日々の暮らしをより豊かに
- 膀胱がんの基礎・最新治療 高齢化に伴い罹患率が上昇 5年生存率は病期別に10~90%
- 低侵襲、しかしがんの芽はしっかり摘む! 膀胱をとらずに治す「大阪医大式膀胱温存療法」とは


