急性リンパ性白血病(ALL)の最新治療 治療の新たな可能性――分子標的薬の登場、移植医療の進展
グリベック登場で治癒率が飛躍的に向上

もっとも、問題はフィラデルフィア染色体が陽性の場合で、数年前までは前にあげた多剤併用療法でも、ほとんど治癒は見込めなかった。しかし最近ではフィラデルフィア染色体の遺伝子産物の構造解明とともに、従来は慢性骨髄性白血病の治療に用いていた分子標的薬のグリベック(一般名イマチニブ)が効果をもたらすことがわかってきた。安藤さんによると、臨床試験段階ながら、グリベックを用いることで、このタイプの寛解率は60パーセント近くにまで達しているという。
「試験を始めてまだ日も浅く、断定的なことはいえません。これからこの薬剤に耐性を持つ白血病細胞が出てくることも考えられますからね。しかし、現在ではグリベックに続き、グリベックが効かなかった場合に用いるスプリセル(一般名ダサチニブ)という新たな分子標的薬もすでに一部では用いられています。
こうした分子標的薬の活用で、これまではほとんど治療の術がなかったフィラデルフィア染色体陽性の場合にも治癒の可能性が出てきたことは間違いありません」
と、安藤さんは語る。
もっとも、こうした抗がん剤治療は患者にも一定以上の体力が求められることになる。そこで高齢の患者の場合には、対称的にずっと穏やかな化学療法による治療が行われることも少なくない。
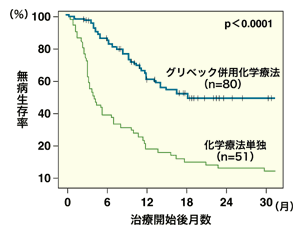
[グリベック併用化学療法の治療組み立て]
| 薬剤 | 投与量・投与経路 | 投与日 |
|---|---|---|
| 寛解導入療法 | ||
| ・エンドキサン | 1200mg/㎡経静脈投与(3時間) | 1 |
| ・ダウノマイシン | 60mg/㎡ 経静脈投与(1時間) | 1~3 |
| ・オンコビン | 1.3mg/㎡���max2mg)経静脈投与 | 1,8,15,22 |
| ・プレドニン | 60mg/㎡ 経口投与 | 1~21 |
| ・グリベック | 600mg 経口投与 | 8~63 |
| ・メソトレキセート キロサイド デカドロン* | 15,40,4mg 髄腔内投与 | 29 |
| 地固め療法(コース1) | ||
| ・メソトレキセート | 1g/㎡ 経静脈投与(24時間) | 1 |
| ・キロサイド | 2g/㎡ 経静脈投与(3時間)×2 | 2,3 |
| ・メドロール* | 50mg 経静脈投与×2 | 1~3 |
| ・メソトレキセート キロサイド デカドロン | 15,40,4mg 髄腔内投与 | 1 |
| 地固め療法(コース2) | ||
| ・グリベック | 600mg 経口投与 | 1~28 |
| ・メソトレキセート キロサイド デカドロン | 15,40,4mg 髄腔内投与 | 1 |
| 維持療法 | ||
| ・オンコビン | 1.3mg/㎡(max2mg)経静脈投与 | 1 |
| ・プレドニン | 60mg/㎡ 経口投与 | 1~5 |
| ・グリベック | 600mg 経口投与 | 1~28 |
維持療法 : 寛解到達日から満2年まで続ける
*デカドロン=一般名デキサメタゾン
*メドロール=一般名メチルプレドニゾロン
再発リスクを考慮し、造血幹細胞移植を

このように急性リンパ性白血病の場合は、強力な化学療法によって、白血病細胞をほとんど検出不能の状態にまで減少させ、症状を安定させることができる。しかし、それでもその後で病気が再発するケースが後を絶たないのも事実だ。そこで東海大学医学部付属病院では積極的な造血幹細胞移植も推進している。
「再発リスクの高い患者さんには、地固め療法を行う前から移植治療のメリットを説明しています。了解が得られた場合には、地固め療法を進めながら、その人にもっともふさわしいドナー(提供者)を探すことになります。言葉を換えれば、リスクがある場合には移植を前提に地固め医療を行っているといってもいいでしょう」(安藤さん)
再発リスクとは(1)年齢が30歳以上であること、(2)血液1マイクロリットル中の白血球数が3万個以上であること、(3)フィラデルフィア染色体が陽性であること、(4)寛解導入に6カ月以上を要している――の各点だ。前述したように(3)に関しては今後、治療方針が変更される可能性もある。しかし現段階では、これらの1点にでも該当する患者には迷うことなく、移植を勧めていると安藤さんはいう。
その移植方法だが大きくは3種類に分かれている。第1の選択肢となるのは当然ながら兄弟など血縁者をドナーとする移植で、骨髄バンクを介して非血縁者のドナーを探す移植がそれに続く。
期待が持たれる複数臍帯血移植
そして最近になって注目を集めているのが、新生児の血液を利用する臍帯血移植だ。ちなみに東海大学医学部付属病院は日本では初めて、小児白血病で臍帯血移植を成功させた病院で、院内には臍帯血バンクもある。
「移植の基本条件は6種類のHLA(ヒト主要組織適合抗原)のうち少なくとも5種類は合致していることですが、それに加えて遺伝子タイプの一致も重要です。それだけに遺伝子タイプが基本的に異なっている非血縁者の移植では、HLAが完全に合致していることが望ましい。そうでなければ、やっかいなGVHD(移植片対宿主病、移植したリンパ球が異物として患者の体を攻撃する合併症)発症の危険が高まりますからね。私たちの治療では地固め療法の段階からドナーを探すので、ほとんどの場合はその人にもっとも好ましいドナーを見つけることができる。しかし、ときには見つからないこともある。その場合には臍帯血移植が選択肢に入ってくるわけです。臍帯血の場合はT細胞がまだ未分化の状態なので、HLAが4種類合致すれば移植可能です」
と、安藤さんはそのメリットを指摘する。
ひとつ付け加えると、臍帯血移植では新生児がドナーとなるため、血液採取量が100ccに限られており、成人白血病患者の場合には量的な不足がネックになっていた。しかし最近では、異なる胎児から採取した臍帯血を1人の患者に用いる複数臍帯血移植が治験段階ながら行われており、良好な結果が出ているという。もちろん、この治療は東海大学医学部付属病院でも受けられる。
ただ移植治療を受ける場合も、やはり相応の体力が必要で、そのために現段階ではこの治療の適用は50歳以下に限られているのが実情だ。そこで他の白血病治療で行われている、抗がん剤による前処置を少なくし、患者への負担を抑えたミニ移植も行われつつある。


