新たな造血幹細胞移植法も出てきた! 化学療法と移植で根治を目指す急性骨髄性白血病の最新治療
HLAの一致が条件
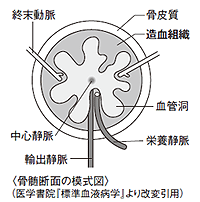
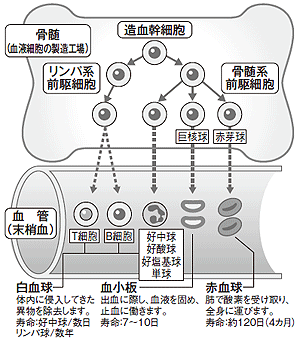
造血幹細胞は通常は骨髄にあります。一方、G-CSF(*)という白血球を増やす薬を注射すると末梢血(体のなかを流れている血液)の中にも増加することがわかってきました。また臍帯血(へその緒)にも豊富に含まれています。そこで造血幹細胞移植には、骨髄を採取して移植する骨髄移植と、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植の3種類があります。
どんな移植を選択するかというとき、まず判断するのは誰からもらうか、ということ。自分以外の他人から造血幹細胞をもらう同種造血幹細胞移植と、自分の造血幹細胞をあらかじめ採取しておいて体に戻す自家造血幹細胞移植の2つの方法があり、どちらかを選択します。
自家移植は、自分の血液細胞を戻すので白血病細胞が紛れ込んでしまい、再発する可能性が高くなります。このため急性骨髄性白血病では同種移植が多く行われます。
同種移植は、骨髄にするか末梢血にするかで、治療成績にほとんど差はないといいます。
「臍帯血も有効ですが、赤ちゃんが生まれたときの胎盤から血液をとっているので、とれる造血幹細胞数に限界があり、移植するとき細胞数が少ないという難点があります。しかし、ドナーに全く負担がかからないという点は大きな魅力です」と神田さん。
ドナーを選ぶとき、1番大事なのはHLA型という白血球の型が一致しているかどうか。不一致だと移植片対宿主病(GVHD)という副作用があらわれ、ドナーの細胞が患者さんの細胞を攻撃してしまい、悪くすると命にかかわることもあります。
このため、移植はHLA型の完全一致が基本。HLA型の不一致が1個だけなら通常の免疫抑制剤を使っての移植も可能ですが、不一致が2個以上だと成績が大幅に下がるため、以前はほとんど実施されていませんでした。
| 1位 | HLA型の適合する血縁者 |
|---|---|
| 2位 | HLA型の適合する非血縁者 (骨髄バンクのドナー、DRB1の遺伝子型が1つだけちがうドナーを含む) HLA型が1つだけちがう血縁者 |
| 3位 | 非血縁者の臍帯血 HLA型が2つか3つちがう血縁者 HLAのAあるいはBの遺伝子型が1つだけちがう非血縁者 HLA型がDRの血清型が1つだけちがう非血縁者 |
*G-CSF=顆粒球コロニー刺激因子製剤
ミスマッチ移植とミニ移植
ところが最近では、不一致が2個あるいは3個あっても移植することが可能になってきました。
移植片対宿主病はドナーの細胞が患者さんの細胞を攻撃するのですが、中でも問題なのはT細胞というリンパ球です。このT細胞を壊す抗体を移植のときに用いることによって、T細胞を抑え、移植片対宿主病を軽くします。
このような移植はHLAミスマッチ移植と呼ばれますが、この治療を行うには移植する側の慣れが必要なので、行える施設は限られています。
「臍帯血移植はHLAが1、2個ちがっていてもGVHDはほとんど問題になりませんので、HLAの一致したドナーが見つからない方には臍帯血移植も候補になります」
また、造血幹細胞移植の前に行う過酷な治療は、高齢者や体力の弱っている人には難しく、このような患者さんのために、移植前の抗がん剤と放射線を軽くしたミニ移植と呼ばれる方法も行われます。
「抗がん剤や放射線の量が減るため、移植しても白血病が再発してしまう危険が高くなる可能性はありますが、ドナーの免疫力(GVL効果)にも期待した治療法です」と神田さん。
移植の成績は、寛解期の患者さんの移植では10年生存率が60~70%というデータがあります。しかし、寛解に入らない状態で移植すると、移植を行っても再発してしまうことが多く、根治する可能性は低くなっています。
移植には注意も必要
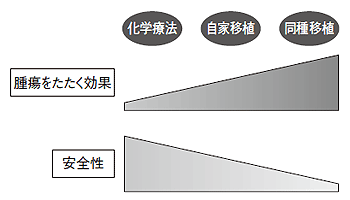
[化学療法と造血幹細胞移植を行った際の生存曲線イメージ]
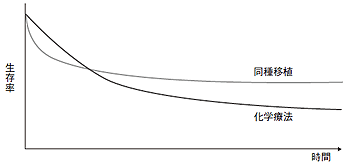
このように急性骨髄性白血病はより強力な抗がん剤治療を行うためにさまざまな方法の移植法が開発されています。しかし、神田さんはそんな移植に対し注意点も指摘しています。
「確かに造血幹細胞移植は通常の治療で根治することが難しい人に対して、行う有効な治療法です。もう1つ大切なこととして、副作用がとても強い治療だということをしっかり把握してください。最悪の場合には治療の副作用で命を失う可能性もあります。そのようなマイナス面よりも、病気を根治する確率が高くなるというプラス面のほうが上回る患者さんに対してのみ行われる治療です」
判断の基準として、年齢や初発時の白血球数などを考慮すると同時に、白血病細胞の染色体検査での病気の進行予測も大切になりそうです。
同じカテゴリーの最新記事
- これから登場する分子標的薬に期待! 急性骨髄性白血病(AML)の治療はそれでも進化している
- 医学会レポート 米国血液がん学会(ASH2015)から
- 貴重な患者さんの声が明らかに!急性白血病治療後の患者QOL調査
- 経過観察から移植まで幅広い治療の選択肢がある 高齢者に多い急性骨髄性白血病 生活の質を重視した治療が大切!
- 予後予測に基づいて寛解後療法を選択。分子標的薬の開発や免疫療法もスタート リスク別薬物療法で急性骨髄性白血病の生存率アップを目指す
- リスクの大きな造血幹細胞移植をやるべきか、いつやるべきかを判断する 再発リスクを測り、それに応じた治療戦略を立てる ~急性骨髄性白血病の場合~
- 治療の主体は抗がん剤を用いた化学療法と造血幹細胞移植 新薬など進歩著しい急性骨髄性白血病の最新治療
- 急性骨髄性白血病の最新治療 分化誘導や分子標的などの新療法の出現で飛躍的効果の足がかり


