予後予測に基づいて寛解後療法を選択。分子標的薬の開発や免疫療法もスタート リスク別薬物療法で急性骨髄性白血病の生存率アップを目指す
地固め療法ではリスク別の治療を重視
急性骨髄性白血病の完全寛解率は現在、約80パーセントに達している。ところが、5年生存率は依然3~4割という厳しい状況にある。この状況を打開するには、再発を防ぐための寛解後療法を的確に実施することにかかっていると宮脇さんはいう。
「そこで、地固め療法では層別化治療が重視されるようになっています。層別化とは患者さんを再発のリスク別に分け、より適切な治療を行うことです。リスク別に分けられるようになった背景には、多数例による臨床研究の結果の蓄積、染色体分析や遺伝子変異の検査によって、予後予測が可能になってきたことが挙げられます」
急性骨髄性白血病の病型分類は1976年に発表されたFAB分類が長らく使われてきたが、最近では2008年に改訂されたWHO分類が取り入れられるようになってきた。FAB分類は白血病細胞の形態による分類が中心だったが、WHO分類の特徴は分子生物学の発展の成果を取り入れ、染色体異常や遺伝子変異を有する病型を独立させている点が相違点だ(表2)。
「白血病の分子病態の研究は日進月歩で、急性骨髄性白血病に関しては次々と新しい遺伝子異常が発見されています。これまで見つかった異常な遺伝子は100種類を超えます。最近では遺伝子の欠失(一部が欠けていること)などの異常もわかるようになりました。これからも遺伝子異常がわかるにつれ、層別化の精度はどんどん上がっていくでしょう」
| ①特定の遺伝子異常を有する 急性骨髄性白血病 | (1)均衡型染色体転座/ 逆位を有する急性骨髄性 白血病 | a. t(8;21) b. inv(16)or t(16;16) c. t (15;17) d. t(9;11) e. t(6;9) f . inv(3) or t(3;3) g. t(1;22) |
| (2)遺伝子変異を有する 急性骨髄性白血病 | a. NPM1 遺伝子変異 b. CEBPA 遺伝��変異 | |
| ②骨髄異形成関連の変化を有する急性骨髄性白血病 | ||
| ③治療関連骨髄性腫瘍 | ||
| ④上記以外の急性骨髄性白血病 | a. 急性骨髄性白血病最未分化型 f. 急性赤白血病 b. 急性骨髄性白血病未分化型 g. 急性巨核球性白血病 c. 急性骨髄性白血病分化型 h. 急性好塩基性白血病 d. 急性骨髄単球性白血病 i. 骨髄線維を伴う急性汎骨髄症 e. 急性単球性白血病 | |
| ⑤骨髄肉腫 | ||
| ⑥ダウン症候群関連骨髄増殖症 | ||
| ⑦芽球形質細胞様樹状細胞腫瘍 | ||
リスクに応じた薬物療法の選択
| 項目 | 基準 | 点数 |
| MPO 陽性の白血病細胞の比率 | >50% | +2 |
| 年齢 | ≦50 歳 | +2 |
| 白血球数(初診時) | ≦20,000/μl(血中マイクロリットル) | +2 |
| FAB 分類病型 | M0,M6,M7以外 | +1 |
| 全身状態 | 0,1,2 | +1 |
| 寛解導入必要回数 | 1 | +1 |
| t(8;21)or inv(16)染色体異常 | どちらか1 つ | +1 |
| 合計 | ||
| 予後良好群 | 8~10 | |
| 中間群 | 5~7 | |
| 予後不良群 | 0~4 | |
[図4 リスク別の生存率(JALSGの調査)]
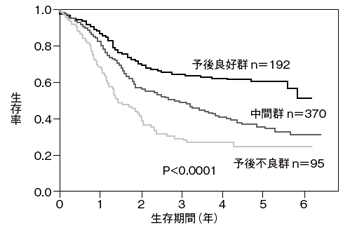
[図5 予後良好群の薬物療法別の無再発生存率]
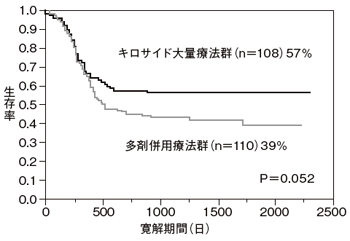
[図6 予後良好群の薬物療法別の全生存率]
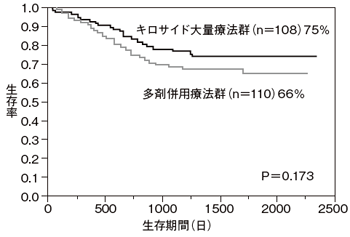
実際に、染色体によるリスク分類に応じた急性骨髄性白血病の治療が行われるようになってきている。リスク分類として、米国のSWOG分類や英国のMRC分類が広く使われているが、日本では、日本成人白血病治療共同研究グループがまとめたJALSGスコアリングシステムと呼ばれる分類が普及している。いずれの分類も予後良好群、中間群、予後不良群に大別する。分類の基準はSWOGとMRCは染色体によるものであるが、JALSGスコアリングシステムは染色体に加え、年齢、初診時白血球数なども加味するきめ細かさが特徴だ(表3・図4)。すでに、JALSGスコアリングシステムに基づいた研究で、リスク別にどのような治療法を行えばいいのかということもわかってきた。
「私たちの研究グループは、AML97研究で、骨髄移植と化学療法の比較を実施し、中間群と予後不良群では骨髄移植が勝ることを確かめました。また、1057人の急性骨髄性白血病患者さんを対象にしたAML201研究では、地固め療法でキロサイド大量療法と多剤併用療法を比較し、予後良好群ではキロサイド大量療法の治療成績がよく、中間群、予後不良群では成績に有意差がないことを明らかにしました」(図5・6)
この結果を受けて、地固め療法として、予後良好群ではキロサイド大量療法が用いられ、中間群では骨髄抑制が強いキロサイドは避け、多剤併用療法が選ばれるようになった。予後不良群では、移植のドナー(臓器提供者)が見つからない場合はキロサイド大量療法の治療成績が多剤併用療法を若干上回っていたので、キロサイドもよく使われるという。
分子標的薬や免疫療法の研究も始まっている
急性骨髄性白血病においても遺伝子変異部位を狙い撃つ分子標的薬への期待も高まるが、宮脇さんは実現への道のりは遠いと説明する。
「慢性骨髄性白血病では、遺伝子異常は増殖にかかわるものしかないので、そこを標的とする分子標的薬のグリベック(*)はきわめて有効です。急性骨髄性白血病の場合、増殖だけでなく、分化停止にかかわる遺伝子にも異常があるので標的部位は複数です。急性骨髄性白血病の約4分の1に認められるFLT3/ITDという遺伝子異常も見つかり、それを標的にした新薬が開発されていますが、臨床現場で使えるようになるまでにはもう少し時間がかかるでしょう」
宮脇さんによれば、ほかの血液がんの治療薬であるクロファラビンやアザシチジン(いずれも一般名)は、急性骨髄性白血病にも有効との報告もあり、期待できる薬剤だという。
「急性骨髄性白血病に対する免疫療法の研究も始まっています。白血病細胞のもとである白血病幹細胞は通常の薬物療法では退治しきれないため、がんワクチンであるWT1ペプチドを使って免疫を活性化し、白血病細胞のみならず、生き残った白血病幹細胞も掃討する作戦です」
再発のリスクに基づいた層別化治療が実施され、これに分子標的薬や免疫療法などが加われば、急性骨髄性白血病の生存率はもっと上昇するはずだと宮脇さんは力強く語ってくれた。
*グリベック=一般名イマチニブ
同じカテゴリーの最新記事
- これから登場する分子標的薬に期待! 急性骨髄性白血病(AML)の治療はそれでも進化している
- 医学会レポート 米国血液がん学会(ASH2015)から
- 貴重な患者さんの声が明らかに!急性白血病治療後の患者QOL調査
- 経過観察から移植まで幅広い治療の選択肢がある 高齢者に多い急性骨髄性白血病 生活の質を重視した治療が大切!
- 新たな造血幹細胞移植法も出てきた! 化学療法と移植で根治を目指す急性骨髄性白血病の最新治療
- リスクの大きな造血幹細胞移植をやるべきか、いつやるべきかを判断する 再発リスクを測り、それに応じた治療戦略を立てる ~急性骨髄性白血病の場合~
- 治療の主体は抗がん剤を用いた化学療法と造血幹細胞移植 新薬など進歩著しい急性骨髄性白血病の最新治療
- 急性骨髄性白血病の最新治療 分化誘導や分子標的などの新療法の出現で飛躍的効果の足がかり


