治療の主体は抗がん剤を用いた化学療法と造血幹細胞移植 新薬など進歩著しい急性骨髄性白血病の最新治療
移植はどんな人に必要か
60歳以下の急性骨髄性白血病患者を対象とした「寛解導入療法」後に行われる「地固め療法」には、数種類の抗がん剤を併用した化学療法とキロサイド大量療法とがある。
急性骨髄性白血病は染色体や遺伝子の異常などから「予後良好群」「予後中間群」「予後不良群」に分けられるが、この予後群別の臨床試験結果からみると、どちらを選んでも統計学的な有意差はないという。
「ただし、予後良好群のうち、CBF白血病と呼ばれる染色体異常を有するタイプはキロサイドに対する感受性が高く、キロサイド大量療法が標準的治療といえます」
「地固め療法」のあとに従来行われてきた「維持・強化療法」はその必要性を確かめる臨床試験がJALSGで行われ、現時点では「寛解導入療法」「地固め療法」でしっかりとした化学療法を行っていれば「維持・強化療法」は必要ないという結論になっている。
「寛解後療法」には、「地固め療法」のほかに、「造血幹細胞移植」という道がある。「造血幹細胞移植」には患者自身の造血幹細胞を使う「自家造血幹細胞移植」と、骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植、といったHLA(白血球の型)が一致した同胞やドナー(臓器提供者)から造血幹細胞の提供を受ける「同種造血幹細胞移植」がある。いずれも重い合併症や副作用が現れる非常に厳しい治療で、誰もが受けられるわけではない。
どんな人に移植が必要なのかを明らかにしようと国内外でさまざまな臨床試験が行われているが、急性骨髄性白血病全症例でみると、移植が従来の化学療法にまさるという明確な結果が得られた試験はない。
「予後良好群、中間群、不良群でそれぞれ移植が有利かどうかを解析すると、予後不良群と中間群ではドナーがいたら移植を行うほうがいいし、予後良好群は行わないほうがいいということになっています。HLA一致の血縁ドナーがいればいいですが、日本の場合はドナーが血縁でも非血縁でも治療成績はあまり変わらないので骨髄バンクからのドナーでも構いません。ドナーがいれば移植、いなければ従来の化学療法になります」
急性骨髄性白血病97試験における強化維���療法
実施群と非実施群の無病生存率(A)と全生存率(B)]
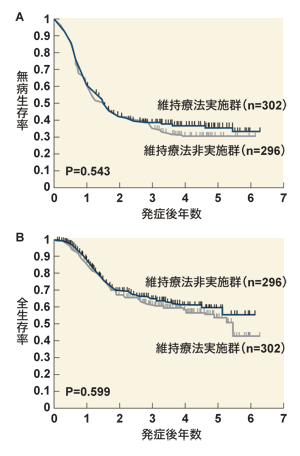
[寛解後療法としてのキロサイド大量療法
CALGB(米国立がん研究所共同臨床試験・白血病グループ)研究]
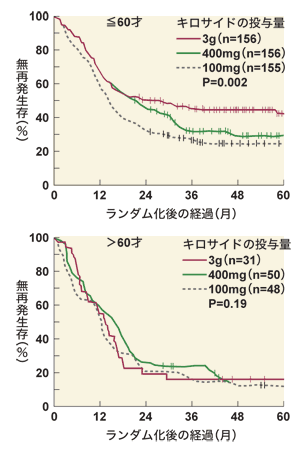
| 病期 | リスク | 同種移植 | 自家移植 | |
|---|---|---|---|---|
| HLA (白血球の型) 同胞ドナー | 非血縁 | |||
| 第1寛解期 | t(15;17)転座 | CRP | NR | R/CRP |
| 低リスク | CRP | CRP | R/CRP | |
| 標準リスク | D | R | R | |
| 高リスク | D | R | CRP | |
| 第2寛解期 | D | R | CRP | |
| 第3寛解期以降 | R | R | CRP | |
| 第1再発早期 | R | R/CRP | NR | |
| 再発進行期/寛解導入不応期 | R/CRP | R/CRP | NR | |
| D:積極的に移植を勧める場合 R:移植を考慮するのが一般的な場合 CRP:標準的治療法とは言えず、臨床試験として実施すべき場合 NR:一般的に認められない場合 | ||||
同じカテゴリーの最新記事
- これから登場する分子標的薬に期待! 急性骨髄性白血病(AML)の治療はそれでも進化している
- 医学会レポート 米国血液がん学会(ASH2015)から
- 貴重な患者さんの声が明らかに!急性白血病治療後の患者QOL調査
- 経過観察から移植まで幅広い治療の選択肢がある 高齢者に多い急性骨髄性白血病 生活の質を重視した治療が大切!
- 新たな造血幹細胞移植法も出てきた! 化学療法と移植で根治を目指す急性骨髄性白血病の最新治療
- 予後予測に基づいて寛解後療法を選択。分子標的薬の開発や免疫療法もスタート リスク別薬物療法で急性骨髄性白血病の生存率アップを目指す
- リスクの大きな造血幹細胞移植をやるべきか、いつやるべきかを判断する 再発リスクを測り、それに応じた治療戦略を立てる ~急性骨髄性白血病の場合~
- 急性骨髄性白血病の最新治療 分化誘導や分子標的などの新療法の出現で飛躍的効果の足がかり


