急性骨髄性白血病の最新治療 分化誘導や分子標的などの新療法の出現で飛躍的効果の足がかり

千葉大学医学部付属病院
血液内科科長の
西村美樹さん
急性白血病は白血病細胞の種類により急性骨髄性白血病と急性リンパ性白血病に大別され、成人では80パーセント以上を急性骨髄性白血病が占めている。
5年生存率が40パーセントとの報告があるほど治癒するのが難しい病気だが、多剤併用療法など治療法の進歩により治療成績は徐々に向上しており、分子標的療法など新たな治療も行われるようになってきた。
造血幹細胞の成長過程で発生する血球のがん
急性骨髄性白血病(Acute Myelogenous Leukemia:AML)は血液の中にある細胞が腫瘍化したもの、いい換えれば血液がんの1つだ。血液を構成する血球の元になる「造血幹細胞」が、血球成分に成長していく過程のどこかでがん化し、無制限に増殖していく病気なので、血球のがんともいえる。
血液中の細胞がなぜ、がんになってしまうのか、千葉大学医学部付属病院血液内科の科長で講師の西村美樹さんに解説してもらった。
「私たちの体をめぐっている血液の中には、液体の成分以外に白血球、赤血球、血小板という細胞があり、それぞれ、感染を防ぐ、酸素を運搬する、出血を止めるといった重要な役目を担っています。これらの細胞はすべて骨の中にある骨髄という場所で作られています。骨髄の中には造血幹細胞とよばれる細胞があり、これは血液の細胞の卵といっていい細胞です」
この造血幹細胞は2つに分かれ、一方は骨髄系細胞で、成長すると赤血球や血小板、それに好酸球、好中球などの白血球になる。他方はリンパ系細胞で、成長するとBリンパ球、Tリンパ球といった白血球になる(図1参照)。
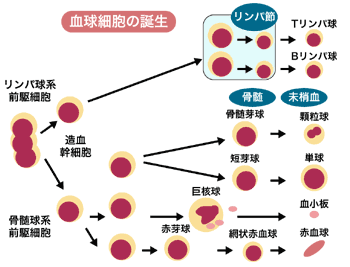
初発症状と診断方法
急性骨髄性白血病とは、骨髄系細胞のうち成長の過程にある細胞が突然、腫瘍化し、正常な成長をやめてしまったまま異常に増えてしまう病気だ。
「当然、腫瘍化してしまった白血病細胞が普通に成長していけば、血液の中に現れるはずの細胞は不足します。それだけではなく、白血病細胞の異常増殖により、骨髄の中で正常に成長している細胞を圧迫しはじめます。そうなると、正常な細胞は血液中に出てこられません。
正常な白血球が不足することでさまざまな感染に弱くなります。赤血球が不足することにより貧血になり、血小板が不足することにより出血が止まらなくなったり、多数の青あざができたりします。急性骨髄性白血病の初発症状として、貧血症状、紫斑、歯肉出血、発熱などがあげられますが、それは、今まで体を守ってきた正常な血液細胞が減少したために起こることなのです」
と西村さんは語る。

骨髄穿刺に使う専用針
このような症状が出たら急性骨髄性白血病を疑う必要があるが、さらに診断のためには、血液検査で正常な細胞の減少、白血病細胞の増加を認めることが重要。白血病というと白血球が増加していると思いがちだが、逆に、少なくなっている場合もあるので要注意、と西村さんは指摘する。
「確定診断をつけるには、骨髄の中を調べなければなりませんので、骨髄穿刺という、骨髄に針を刺して細胞を吸引する検査が必須となります。吸引された細胞はその形態だけでなく、細胞の表面にあるタンパク質、遺伝子の異常なども調べられて最終的に診断されます。また、ひとくちに急性骨髄性白血病といいますが、現在ではM0、M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7の8種類に分類されます」(図2参照)
| 病型 | 名称 | 全体における割合 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| M0 | 微未分化型骨髄芽球性白血病 | 5% | 白血球が最も未分化な状態の骨髄性白血病 |
| M1 | 未分化型骨髄芽球性白血病 | 15% | ほとんどの細胞が顆粒球に分化していない状態で増加 |
| M2 | 分化型骨髄芽球性白血病 | 25% | 顆粒球への分化傾向を伴う |
| M3 | 前骨髄球性白血病 | 10% | 前骨髄球が増殖する |
| M4 | 骨髄単球性白血病 | 52% | 骨髄系と単球系の両方への分化傾向を伴う |
| M5 | 単球性白血病 | 10% | 単球系細胞が増殖する |
| M6 | 赤白血病 | 5% | 骨髄芽球と赤芽球が増殖する |
| M7 | 巨核芽球性白血病 | 5% | 巨核芽球が増殖する |
多剤併用の化学療法が中心
急性骨髄性白血病の診断がついたら、速やかに治療が行われる。
「血液は全身をめぐっていますから、白血病と判明した段階で、全身性の病気であると考えます。手術や放射線では治療することができず、多剤併用の化学療法、つまり何種類かの抗がん剤の組合わせで治療をすることになります」
現在のところ、標準治療としてよく用いられている抗がん剤は、イダマイシン(一般名イダルビシン)、ダウノマイシン(一般名ダウノルビシン)、アドリアシン(一般名ドキソルビシン)、ノバントロン(一般名ミトキサントロン)などの抗がん性抗生物質、キロサイド(またはサイトサール、一般名シタラビン)などの代謝拮抗剤で、これらによる多剤併用化学療法が中心となる。
これらの抗がん剤は、白血病細胞を強力に攻撃するが、同時に正常な細胞にもダメージを与えてしまう。すると正常な血液細胞も著しく減少するため、さまざまな対策をとらなければならない。
「正常な白血球がほとんどなくなってしまい、細菌、真菌に無防備になってしまいますから、フィルターを通した清潔な空気をつくるラミナエアフローという器具(アイソレーターと呼ぶほうが一般的)をベッドに装着し、感染を予防する薬を内服するなどして感染症を防ぐように努めます。それでも感染症が起きてしまった場合は、抗生物質や抗真菌剤などを投与して対抗します。赤血球が著しく減少すれば輸血も行う必要がありますし、血小板が著しく減少すれば血小板製剤を輸注することも必要になります。
これら血液細胞へのダメージ以外にも、悪心、嘔吐などの消化器症状、脱毛、皮膚の色素沈着、心臓、腎臓、肝臓といった重要な臓器の障害など、抗がん剤にはさまざまな副作用があります。ほとんどの副作用は薬剤の投与が終了して一定期間経れば回復しますが、適切な量の範囲であっても症状が治まらないものもありえます」
同じカテゴリーの最新記事
- これから登場する分子標的薬に期待! 急性骨髄性白血病(AML)の治療はそれでも進化している
- 医学会レポート 米国血液がん学会(ASH2015)から
- 貴重な患者さんの声が明らかに!急性白血病治療後の患者QOL調査
- 経過観察から移植まで幅広い治療の選択肢がある 高齢者に多い急性骨髄性白血病 生活の質を重視した治療が大切!
- 新たな造血幹細胞移植法も出てきた! 化学療法と移植で根治を目指す急性骨髄性白血病の最新治療
- 予後予測に基づいて寛解後療法を選択。分子標的薬の開発や免疫療法もスタート リスク別薬物療法で急性骨髄性白血病の生存率アップを目指す
- リスクの大きな造血幹細胞移植をやるべきか、いつやるべきかを判断する 再発リスクを測り、それに応じた治療戦略を立てる ~急性骨髄性白血病の場合~
- 治療の主体は抗がん剤を用いた化学療法と造血幹細胞移植 新薬など進歩著しい急性骨髄性白血病の最新治療


