渡辺亨チームが医療サポートする:急性前骨髄球性白血病編
思いもかけない病気もATRA療法で寛解、職場へ復職
楠本茂さんのお話
*1 鼻血で疑われること
鼻血の多くは、アレルギー性鼻炎・副鼻腔炎や鼻腔腫瘍など鼻の中に病気があって起こるものです。しかし、まれですが血小板減少性紫斑病、白血病など、血液の病気で血が止まりにくくなって起こる場合もあります。
*2 貧血症状
めまい、動悸、息切れ、疲れなどの貧血症状は、鉄欠乏性貧血のほか、さまざまな病気が原因になって起こることがあります。大部分は一過性のものですが、安静にしても治らないときは、血圧、脈拍などくり返し測定し、重大な病気の前兆ではないか、経過をよくみる必要があります。
*3 汎血球の減少
普通の血液には白血球、赤血球、血小板など、正常に育った血液細胞のみが存在しますが、これらの正常の血液細胞が減少した状態を「汎血球の減少」といいます。白血病の多くは、血液検査により、汎血球の減少や異常な白血病細胞の出現が観察されることから発見につながります。
*4 白血病の症状
血液細胞の中で赤血球は体のすみずみに酸素を届ける役割を持ち、白血球は体に入ってくる菌や異物と戦い、血小板は血液を固める働きがあるので、白血病になるとそれぞれの血球の機能が著しく低下して、免疫力が衰えたり、めまいなどの貧血症状が現れたり、出血しやすくなるのです。
ただこれらは白血病特有の症状ではなく、しかも病状の進行も早いので発見が遅れがちで、それが命取りになってしまうことがしばしばあります。
*5 骨髄穿刺(マルク)
血液検査で異常が示され、白血病が疑われたとき、骨髄を調べるために骨髄穿刺という検査を行います。
骨髄穿刺は、胸骨(前胸部中心部の骨)または腸骨(いわゆる腰骨)に針を刺して骨髄液をとる検査です。
検査に先立って、痛み止めに局所麻酔を行います。十分な麻酔を行うことと骨髄液を採取する際に生じる一瞬の痛みのタイミングを十分に説明、理解していただければ、骨髄穿刺自体は比較的安全かつ痛み少なく行うことができます。
採取した骨髄標本は「ギムザ染色」と呼ばれる染色法で染め出して顕微鏡で観察します。白血病細胞があるかどうか、また骨髄性白血病かリンパ性白血病かなどを検査します。急性骨髄性白血病の中のどのタイプ、どの治療法がいいのかは、この骨髄検査でほとんど診断がつきます。これらの結果は、通常検査当日あるいは翌日にははっきりします。
なお、骨髄穿刺は、ドイツ語��「骨髄」を意味する「マルク」と呼ばれることもあります。
*6 白血病
骨の中心部である「骨髄」は、血液の工場です。ここでは、いろいろな血液細胞のおおもとである「造血幹細胞」が、まず「リンパ系細胞」と「骨髄系細胞」に分かれ、これらの細胞が「芽球」という状態を経て、リンパ系細胞は「リンパ球」に、骨髄系細胞は「赤血球」「血小板」「単球」「顆粒球」などの血球に成熟して、血液中に出ていきます。このような過程を分化といいます。
白血病とは、芽球や造血幹細胞ががん化して、骨髄や血液中に未成熟な白血球(白血病細胞)が増殖し、正常な血液細胞が造られなくなる病気です。
リンパ系細胞ががん化する「リンパ性白血病」と、骨髄系細胞ががん化する「骨髄性白血病」、さらに、がん化した白血球が芽球の段階で増える「急性白血病」と、成熟する過程の全段階で増える「慢性白血病」に分類されます。
白血病の中でも急性骨髄性白血病は、白血病の半分以上を占める病気です。この白血病には、細胞がどの時期にがん化するかによって8種類に分類されており、夏目雅子さん、渡辺謙さん、本田美奈子さんもこの病気にかかっています。
K-1のアンディ・フグ選手は、急性骨髄性白血病の1つである急性前骨髄球性白血病にかかって急死し、歌舞伎俳優の市川団十郎さんもこの病気と報道されています。
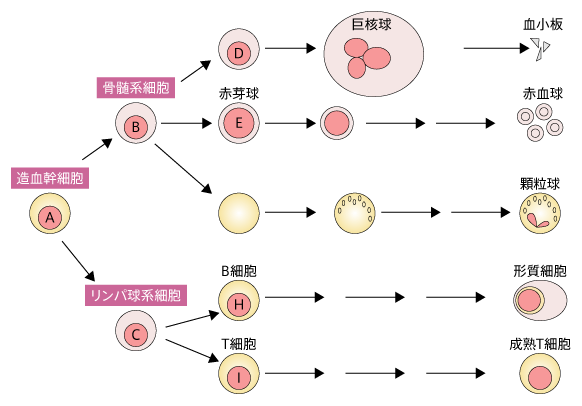
*7 急性前骨髄球性白血病
急性骨髄性白血病の中のひとつのタイプで、他の急性白血病が血液中に白血病細胞が増加することが多いことに比べて、汎血球減少を示すことが多いことが知られています。
もうひとつの特徴は血が固まりにくく出血しやすいDICと呼ばれる現象を高率に引き起こすことです。以前はこの白血病に化学療法を行うと脳出血や消化管出血など重篤な出血を起こして早期に10~15パーセントが死亡していました。
*8 寛解導入療法と地固め療法
白血病の場合、全身に白血病細胞が流れているため、手術や放射線照射などの方法で治すことは困難ですが、その一方、急性白血病は抗がん剤が効きやすいことが特徴です。そのため治療は抗がん剤を組み合わせた治療が中心となります。
急性白血病は、新しい治療薬が出たばかりでなく、「この人の病状ではどのくらい予後を期待できる」という考えに基づいたオーダーメイドの治療や、できるだけ合併症・副作用を軽くするための支持療法(補助療法)が改善・進歩したことから治療成績が向上しました。
抗がん剤治療は2段階に分けて行われます。第1段階の目標は骨髄中に占拠している白血病細胞を抗がん剤で減少させ、正常な細胞が増えるための場を取り戻すことです。
この治療を「寛解導入療法」といいます。この治療により白血病細胞が骨髄中の細胞の5パーセント以下になり、正常な細胞が増えてきた状態を「完全寛解状態」といい、7割が完全寛解になります。
ただし、急性白血病のなかでも、急性前骨髄性白血病の場合は、オールトランスレチノイン酸=ATRA(一般名トレチノイン、商品名ベサノイド)という薬を単剤あるいは抗がん剤と併用する治療を行います。
第2段階の抗がん剤治療は、「寛解後療法」とか「地固め療法」といい、完全寛解状態の数カ月後から行うのが普通です。完全寛解になっても、これは完全に治った状態(根治)ではなく、体内には「微小残存病変」といってかなりの数の白血病細胞が残っているため、ここで治療をやめると確実に再発します。
そのため第2段階の抗がん剤治療は再発率を減らすために行うのです。寛解導入法とほぼ同じ強さの治療を数回繰り返します。
急性前骨髄球性白血病は、ATRA療法のみで完全寛解を維持することは困難で、他の急性白血病と同様に抗がん剤による地固め療法が必要です。
急性骨髄性白血病の治療効果は、病気の種類や症状によりその効果も変わってきますが、治療法の進歩により徐々に改善しています。最近の報告では寛解導入療法による完全寛解率は約70~80パーセント、5年生存率は約30パーセントと報告されています。
*9 ATRA療法
1988年に中国で開発された療法で、オールトランスレチノイン酸(ATRA)を内服することにより、白血病細胞を正常な細胞に分化するように導く働きがあります。
この治療を「分化誘導療法」と呼びます。ただし、白血球が多い場合、あるいは経過中に白血球数が増えてきた場合に抗がん剤を併用することがあります。ATRAを用いた治療により急性前骨髄球性白血病の8~9割は、寛解状態に達します。
また、ATRAにより血が固まりにくい凝固異常が速やかに改善し、出血による早期死亡率の低下が寛解導入向上に寄与することがわかっています。
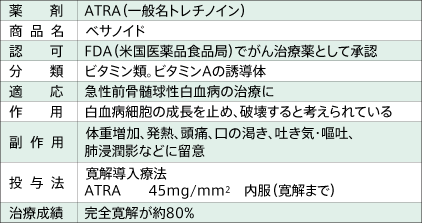
同じカテゴリーの最新記事
- これから登場する分子標的薬に期待! 急性骨髄性白血病(AML)の治療はそれでも進化している
- 医学会レポート 米国血液がん学会(ASH2015)から
- 貴重な患者さんの声が明らかに!急性白血病治療後の患者QOL調査
- 経過観察から移植まで幅広い治療の選択肢がある 高齢者に多い急性骨髄性白血病 生活の質を重視した治療が大切!
- 新たな造血幹細胞移植法も出てきた! 化学療法と移植で根治を目指す急性骨髄性白血病の最新治療
- 予後予測に基づいて寛解後療法を選択。分子標的薬の開発や免疫療法もスタート リスク別薬物療法で急性骨髄性白血病の生存率アップを目指す
- リスクの大きな造血幹細胞移植をやるべきか、いつやるべきかを判断する 再発リスクを測り、それに応じた治療戦略を立てる ~急性骨髄性白血病の場合~
- 治療の主体は抗がん剤を用いた化学療法と造血幹細胞移植 新薬など進歩著しい急性骨髄性白血病の最新治療
- 急性骨髄性白血病の最新治療 分化誘導や分子標的などの新療法の出現で飛躍的効果の足がかり


