渡辺亨チームが医療サポートする:急性前骨髄球性白血病編
度重なる難関にもめげず、新薬「三酸化ヒ素」にトライして成功
楠本茂さんのお話
*1 第2寛解
白血病は再発しても再度強力な寛解導入法を用いることにより、多くの患者さんが寛解に達することができるようになりました。1度白血病が再発して、再発後の治療により再び完全寛解となった状態を「第2寛解」と呼びます。しかしながら、通常の抗がん剤治療だけではこの「第2寛解」を長期間維持することは困難であり、造血幹細胞移植を含む強力な地固め療法が必要です。
*2 骨髄移植後の退院
大量の抗がん剤や全身放射線照射を前処置とした骨髄移植を行った場合、退院は移植後100日がおおよその目安になります。それまでは移植前処置や急性GVHD(移植片対宿主病)による臓器障害、感染症による発熱、免疫抑制剤の副作用などが高頻度に出現し、入院管理が必要となります。最近になって、造血幹細胞移植のなかでも移植前処置による骨髄抑制や臓器障害が比較的少なく、体への負担が比較的少ない「ミニ移植」が普及してきました。ミニ移植により、50歳以上の高齢者や臓器障害があって通常の移植ができない患者さんも同種移植の恩恵を受けることができます。また、入院日数も短くできるようになっています。
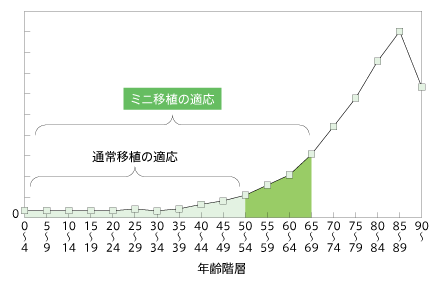
(厚生省統計情報部「人口動態統計」平成9年を参考にして改変)
*3 骨髄移植後の外来診察
骨髄移植は現在のところ、白血病に対する最も強力な地固め療法ですが、骨髄移植を行っても白血病再発が起こることがあります。完全寛解に達しても、これは見た目の白血病細胞がなくなっただけであり、まだ完全に白血病細胞を撲滅できていない可能性があるのです。また免疫機能がある程度回復したとはいえ、まだ完全ではなく、依然として感染症などにかかりやすい状態にあります。そのため、しばらくはGVHD予防のための免疫抑制剤や感染予防のための薬を飲み続ける必要があります。2~3週ごとに頻回に外来診察を受け、血液検査をすることが欠かせません。
退院約3カ月後から全身状態が順調に回復していれば、外来の受診間隔を延ばすとともに、職場や学校へ復帰できるようになります。
*4 再移植
急性白血病の移植後再発に対しては、抗がん剤治療を行って再び寛解になることもありますが、治療効果はあまり長く続かないのが普通です。免疫抑制剤投与中の再発であれば、��疫抑制剤を減量・中止することで病気のコントロールができることがあります。また、非常に早期の再発である場合は、ドナー(提供者)のリンパ球を輸注することで寛解になることがあります。
それ以外の場合では、最初のときと同じドナーから再び骨髄を提供してもらうか、それ以外のドナーを見つけて、再移植が行われることがあります。この場合の基準は、(1)初回移植から移植したあとの再発までの期間が長いこと(少なくとも1年以上)、(2)年齢が若いこと、(3)抗がん剤治療などにより再寛解に達していること、(4)全身状態が良好で主要な臓器の機能が保たれていること、などの条件が満たされていることです。しかし、再移植は、初回移植に比べて、移植関連死亡率が非常に高くなるため、慎重を要します。
*5 GVL効果
毒入りカレー事件などで、有害性が知られるようになったヒ素ですが、いくつかの漢方薬にはもともと使われていたのです。1990年代に中国の漢方医が使っていた「癌霊1号」という漢方薬などに三酸化ヒ素(亜ヒ酸)が含まれていて、急性前骨髄球性白血病に対して高い有効性を示すことが報告されました。その後、アメリカの白血病研究グループで臨床試験が実施され、ATRA療法に匹敵する有効性があることが確認されたのです。この成績をもとに、2000年9月にアメリカで承認され、次いで2002年3月にヨーロッパでも承認されました。そして日本でも、2004年10月に三酸化ヒ素製剤が保険承認を取得しました。この治療法もATRA療法と同じく、「分化誘導療法」と呼ばれていますが、ATRA療法の分化誘導とは作用のしくみが違うために、ATRA療法に耐性ができて再発した例でも、80パーセントに再寛解が認められます。しかしながら、長期間観察されたデータは少ないのが現状です。

欧米では再発・難治性急性前骨髄球性白血病の
第1選択薬になっている
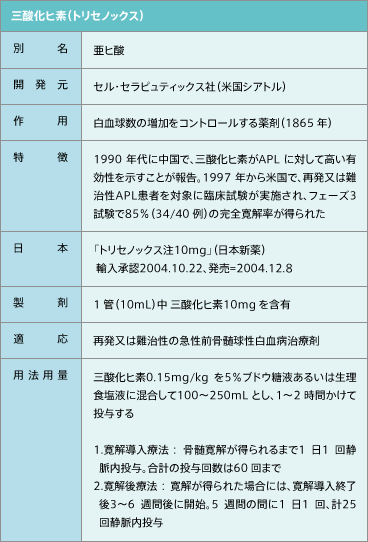
*6 三酸化ヒ素の副作用と支持療法
三酸化ヒ素の副作用としてとくに注意する必要があるのは、心臓の拍動をコントロールしている電気に異常が現われて、生命をおびやかす不整脈を引き起こす可能性があることです。そこで、三酸化ヒ素を点滴するときは、心臓を走る電気の様子を見るために心電図を監視します。また心臓の電気に関係する血液中の電解質(カリウム、カルシウム、マグネシウム)を採血によってチェックして、正常値であるように調整します。さらにこうした電解質に異常をもたらすような薬剤の併用を避けることが大切です。
そのほか三酸化ヒ素の副作用として、皮膚症状(かゆみ、乾燥、紅斑など)、消化器症状(吐き気、嘔吐など)、肝機能障害、神経毒性(手足のしびれ)などがあります。
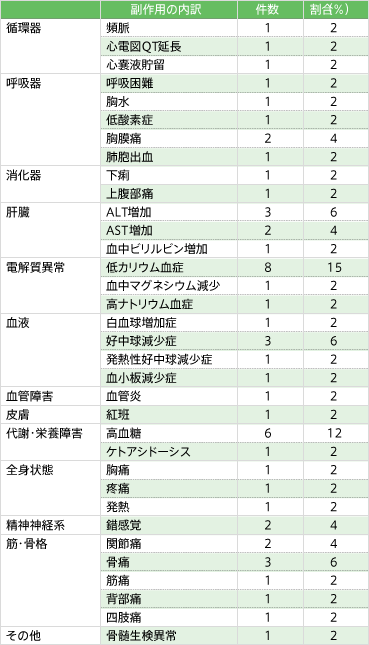
米国での1/2相試験、3相試験52例で出現したグレード3、4の副作用
*7 三酸化ヒ素による治療スケジュール
三酸化ヒ素は1日1回1~2時間かけて点滴を行い、最大60回(約2カ月)で寛解導入を行います。寛解終了後に3~6週後に地固め療法として、1週に5回投与を5週間、計25回の点滴を行います。
*8 急性前骨髄球性白血病の新しい治療
急性前骨髄球性白血病の治療では、いまやATRAは欠かせない薬となりましたが、さらに三酸化ヒ素やタミバロテンといった新薬まで登場してきています。また、第2寛解期の急性前骨髄球性白血病においては、ATRAにより十分に深い寛解になった場合には、より体にやさしい(移植関連合併症の少ない)自家造血幹細胞移植の成績が、他人から骨髄をもらう同種移植と同等かそれ以上であることが示されつつあります。
さらに大宮さんの例のように同種移植後再発しても、分化誘導薬は比較的安全に寛解導入することができる可能性を持っています。そして再移植を行うことになっても臓器障害合併のリスクを引き下げ、移植の良いタイミングを見つけるのに役立つと考えられます。
同じカテゴリーの最新記事
- これから登場する分子標的薬に期待! 急性骨髄性白血病(AML)の治療はそれでも進化している
- 医学会レポート 米国血液がん学会(ASH2015)から
- 貴重な患者さんの声が明らかに!急性白血病治療後の患者QOL調査
- 経過観察から移植まで幅広い治療の選択肢がある 高齢者に多い急性骨髄性白血病 生活の質を重視した治療が大切!
- 新たな造血幹細胞移植法も出てきた! 化学療法と移植で根治を目指す急性骨髄性白血病の最新治療
- 予後予測に基づいて寛解後療法を選択。分子標的薬の開発や免疫療法もスタート リスク別薬物療法で急性骨髄性白血病の生存率アップを目指す
- リスクの大きな造血幹細胞移植をやるべきか、いつやるべきかを判断する 再発リスクを測り、それに応じた治療戦略を立てる ~急性骨髄性白血病の場合~
- 治療の主体は抗がん剤を用いた化学療法と造血幹細胞移植 新薬など進歩著しい急性骨髄性白血病の最新治療
- 急性骨髄性白血病の最新治療 分化誘導や分子標的などの新療法の出現で飛躍的効果の足がかり


