慢性骨髄性白血病の治療を変えた分子標的薬5年の軌跡 全生存率89.4%。未治療の全病期で第1選択に
グリベックの登場。移行期、急性転化期でも効果を発揮
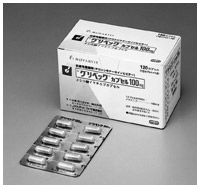
グリベックは、分子標的治療薬と呼ばれる新しい薬だ。
慢性骨髄性白血病は、前述したように、bcr-abl遺伝子という異常な遺伝子で発症する。グリベックは、この遺伝子が作るBCR-ABLチロシンキナーゼという異常タンパクを標的にして、この異常タンパクが出し続ける「白血病細胞を作れ」という指令を遮断する作用を持つ。
グリベックは、2001年5月、米国のFDA(食品医薬品局)で、フィラデルフィア染色体が陽性の慢性骨髄性白血病の治療薬として承認された。病気の進み具合に関係なく、慢性期、移行期、急性転化期で、ほかの治療を受けて効果がない場合に使われ始めた。
日本では2001年11月に承認され、現在、世界90カ国以上で使われている。
グリベックは、1998年6月に始まった薬の安全な投与量などを決める第1相試験の段階で、その並外れた治療効果が注目されていた。99年12月から始まった腫瘍の縮小効果などを評価する第2相試験の結果で、その期待はさらに高まった。
「慢性期でインターフェロン療法が効かない患者さん532人にグリベックを用いたところ、89.5パーセントで血液学的完全寛解が得られました。また、移行期の235人のうち35.3パーセント、急性転化期の260人のうち6.5パーセントで、同様の結果が得られました(図4参照)。
それまで、移行期、急性転化期には有効な治療法はなく、移植ができてもよい効果は得られませんでした。血液学的完全寛解はゼロでしたから、画期的な治療効果です。
この治療成績の結果を踏まえて、移行期と急性転化期の世界の標準治療では、第1選択はグリベックになりました。そして、グリベックで寛解が得られてから、可能なら移植を行います」と薄井さん。
血液学的完全寛解とは、白血球や血小板などが正常化し、脾臓の腫れなどの症状のない状態が4週間以上続いた場合のことをいう。
| 慢 性 期 インターフェロン不応・耐性 400mg n=532 1) | 移 行 期 400mg~600mg | 急性転化期 400mg~600mg | |
|---|---|---|---|
| 血液学的効果 | 89.50% | 67.70% | 28.80% |
| 完全寛解 | 89.50% | 35.30% | 6.50% |
| メジャー細胞 | |||
| 遺伝的寛解 | 54.70% | 23.00% | 15.00% |
| 完全寛解 | 36.50% | 16.60% | 16.50% |
| 部分寛解 | 18.20% | 6.40% | 8.50% |
インターフェロン療法をはるかに上回る治療成績
2000年6月から第3相試験が世界16カ国、117施設で開始された。IRIS(International Randomized Study of Interferon versus ST1571)試験と呼ばれる。
フィラデルフィア染色体が陽性で慢性骨髄性白血病の慢性期と診断された新規の患者1106人を対象に、無作為に、当時の第1選択のインターフェロンと抗がん剤のキロサイド(またはサイトサール。一般名シタラビン)の併用療法群とグリベックを服用した群とに分けて、その治療効果を比較検討した。18カ月後、骨髄細胞の中のフィラデルフィア染色体を測定した。
「フィラデルフィア染色体を治療目標まで減少、または消失させられたかを調べました。
その結果、完全細胞遺伝学的寛解(白血病細胞が消滅している状態)と部分的細胞遺伝学的寛解を合わせたメジャー細胞遺伝学的寛解の割合は、インターフェロン群は22パーセント、グリベック群では85パーセントと、非常に大きな差が出ました。
この時点では、グリベックの長期的な治療効果はわかりませんでしたが、従来の標準治療のインターフェロン療法よりははるかによい治療成績でした。そのため、試験の途中で、インターフェロンからグリベックに切り替える患者さんが続出しました。
こうした治療結果を見て、FDAは01年5月に、インターフェロンが効かない患者さんへのグリベックの服用を認めたのです」(薄井さん)
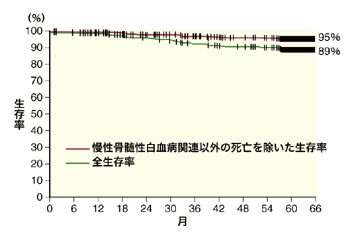
同じカテゴリーの最新記事
- 第3世代の新薬も登場! さらに進化する慢性骨髄性白血病の最新治療
- 深い寛解後に 70%が投薬中止可能~慢性骨髄性白血病の治療~
- 治療薬に新たにボスチニブが加わる 慢性骨髄性白血病の最新治療
- 慢性骨髄性白血病 治療薬を飲み続けなくてもよい未来
- 休薬してよいかどうかの臨床試験も始まり、将来的には完治できる可能性も! 効果の高い第2世代薬が登場!慢性骨髄性白血病の治療薬をどう選ぶか
- 慢性骨髄性白血病~新薬の登場で完全治癒への期待がふくらむ 新しい分子標的治療薬がもたらすインパクト
- 一生薬を飲み続けなくてもいい時代が来るかもしれない!? 完全治癒を目指して慢性骨髄性白血病の最新治療
- グリベックの10倍以上の効力を持つ新しい分子標的薬も近々承認 分子標的薬の登場で大きく変わる白血病治療
- 渡辺亨チームが医療サポートする:慢性骨髄性白血病編


