慢性骨髄性白血病の治療を変えた分子標的薬5年の軌跡 全生存率89.4%。未治療の全病期で第1選択に
未治療の慢性骨髄性白血病の全病期で第1選択に
2006年6月、ASCO(米国臨床腫瘍学会)でIRIS試験60カ月の治療成績が発表された。グリベック群の全生存率は89.4パーセント。慢性骨髄性白血病の関連による死亡はわずか4.6パーセント。この試験ではさらに以下のようなことも明らかになった。
(1)血液学的寛解の割合は98パーセント、細胞遺伝学的寛解は92パーセント、分子遺伝学的寛解(分子レベルの検査を行い、異常が見られない状態)は87パーセントと非常によい治療成績だった(図6参照)。
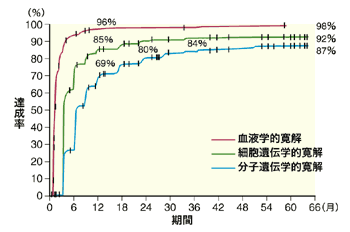
また、グリベックを飲み続ければ、その治療効果は遅くなっても得られる、スローレスポンスという現象が現れる。
(2)増悪するタイミングを見ると、2年後、3年後がピークで、4年後、5年後は減少している。グリベックを3年以上飲み続ければ、その後の増悪率は1パーセントを切る。
| 全期間累積発現 (n=551) | 2年目以降の発現 (n=456) | 4年目以降の発現 (n=409) | |
|---|---|---|---|
| 血液学的毒性/肝毒性 | 発現率 | ||
| 好中球減少 | 16.7 | 3.7 | 1 |
| 血小板減少 | 8.9 | 1.5 | 0.2 |
| 貧血 | 4.4 | 1.8 | 0.5 |
| 肝酵素上昇 | 5.3 | 0.4 | 0 |
| その他の薬剤関連毒性 | 17 | 5 | 2 |
[図8 グリベックによって起こる副作用]
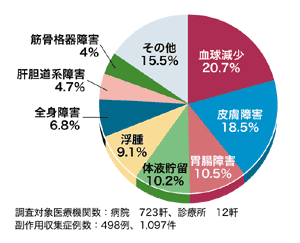
(3)治療開始後12カ月、18カ月の時点で、細胞遺伝学的効果が得られた患者は、その後、ほとんど移行期、急性転化期に進行しない。病気の進行を抑えることができる。
移植の5年生存率は50~70パーセント。移植が成功すれば、慢性骨髄性白血病を治すことができる。しかし、移植はリスクを伴う。そこで、今回のIRIS試験の結果をもとに、標準治療は次のようになった。
「慢性骨髄性���血病の未治療では、すべての病期で、グリベックが第1選択となりました。
グリベックが効かない場合には、グリベックの増量や、可能なら移植、あるいは化学療法を行います。この第2選択には順番はありません」(薄井さん)
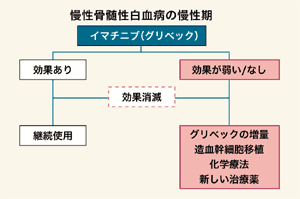
グリベックによる治療例
東京慈恵会医科大学付属病院血液腫瘍内科で、グリベックの治療を受けているAさん(33歳)のケースの治療経過は以下のようである。Aさんは、2002年夏、会社の健康診断で白血球の異常が見つかった。
白血球数は2万6000で正常値4000~9000を上回り、血小板数も190万で正常値15万~35万をはるかに超えていた。外来で骨髄検査を受けた。20分ほどの簡単な検査だ。
1週間後、フィラデルフィア染色体が陽性とわかり、慢性骨髄性白血病と診断された。グリベックを毎朝4カプセルずつ飲み始めた。1カ月後、血液学的寛解に入った。2カ月半後にはフィラデルフィア染色体がゼロになり、細胞遺伝学的効果が得られた。さらに、12カ月後には分子遺伝学的寛解が確認された。
Aさんは、最初の1カ月間、毎週1回ずつ外来通院。その後3カ月は毎月1回ずつ、それ以後は2~3カ月に1回ずつ外来通院を続ける。仕事は診断された以前とまったく変わりなく続けている。4年後の現在、その経過はきわめて順調だ。
服用期間、患者の経済的負担が今後の課題
「Aさんは治療開始後12カ月、18カ月で、細胞遺伝学的寛解が得られています。IRIS試験の解析を見ると、Aさんが移行期や急性転化期に進行する確率は5年間ではゼロパーセントと期待されます。当科ではAさんを含めて40人以上にグリベックを処方しています。未治療慢性期の患者さんの治療成績はIRIS試験とほぼ同じです」と薄井さんは言う。
グリベックに続いて、新しい分子標的治療薬の開発も進行中だ。
1つはダサチニブ(06年6月、米国FDA承認)で、BCR-ABLタンパク以外の異常タンパクにも作用する。
2つ目はニロチニブだ。グリベックの作用をパワーアップし、グリベックの第2世代の薬と呼ばれる。
「グリベックの効果がない場合の第2選択の治療として、この2つの新しい分子標的治療薬は、間もなく使われるようになるでしょう」(薄井さん)
グリベックの登場で、慢性骨髄性白血病の治療は、大きな変貌を遂げた。しかし、課題もある。いつまで飲み続けたらよいのかなど、その服用についてわかっていないことも多い。また、薬代がかなり高く、患者負担が大きい点も難点だ。今後はこうした問題も克服していく必要がある。
同じカテゴリーの最新記事
- 第3世代の新薬も登場! さらに進化する慢性骨髄性白血病の最新治療
- 深い寛解後に 70%が投薬中止可能~慢性骨髄性白血病の治療~
- 治療薬に新たにボスチニブが加わる 慢性骨髄性白血病の最新治療
- 慢性骨髄性白血病 治療薬を飲み続けなくてもよい未来
- 休薬してよいかどうかの臨床試験も始まり、将来的には完治できる可能性も! 効果の高い第2世代薬が登場!慢性骨髄性白血病の治療薬をどう選ぶか
- 慢性骨髄性白血病~新薬の登場で完全治癒への期待がふくらむ 新しい分子標的治療薬がもたらすインパクト
- 一生薬を飲み続けなくてもいい時代が来るかもしれない!? 完全治癒を目指して慢性骨髄性白血病の最新治療
- グリベックの10倍以上の効力を持つ新しい分子標的薬も近々承認 分子標的薬の登場で大きく変わる白血病治療
- 渡辺亨チームが医療サポートする:慢性骨髄性白血病編


