「不治の病」から「治癒可能な病」になったが、まだまだあなどれない これだけは知っておきたい白血病の基礎知識
正常細胞を保ちながら白血病細胞を減らす
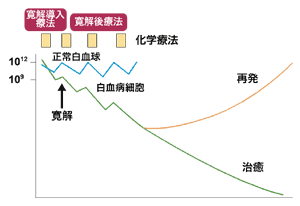
正常細胞が回復して寛解に持ち込めたら、そこからは同じような抗がん剤治療を何回か繰り返す。
「抗がん剤治療を行うと、白血病細胞も正常細胞も減りますが、抗がん剤を中止した後は、正常細胞のほうが早く回復してきます。そこで、正常細胞が回復するのを待ち、白血病細胞がまだ回復していない段階で、次の抗がん剤治療を行うのです。これを繰り返していくと、グラフに示したように、正常細胞と白血病細胞の差がどんどん大きくなっていきます。このような治療を“寛解後療法”あるいは“地固め療法”と呼んでいます」
白血病細胞を減らすことが目的なら、もっと強い治療を行って、一気にたたいてしまえばよさそうに思えるかもしれない。しかし、そうするわけにはいかないのだという。
「寛解後療法は、抗がん剤の副作用で減少した正常細胞が、1カ月くらいで回復できることを目安に抗がん剤治療を行います。1カ月くらいで回復しないと、血小板減少による出血や、白血球減少による感染症などで、患者さんが死亡してしまう危険性が高いからです。そのため、1カ月で回復する程度にしかたたけないのです」
このようにして寛解後療法を続けていくと、最終的に治癒に至ることがある。急性白血病で化学療法を受けた人の30~40パーセントが治癒するという。
強力な治療効果を発揮する造血幹細胞移植
白血病の治療では、造血幹細胞移植が重要な治療手段の1つになっている。白血病に冒された自分の血球細胞を徹底的にたたいて壊滅状態にし、そこにすべての血球を作り出す能力を持つドナーの造血幹細胞を移植する。そうして、がんに冒されていない血液を作ろうという治療法である。
かつては移植されるのは骨髄だけだったが、現在では末梢血(普通に血管を流れている血液)やさい帯血(胎児のへその緒の血液)の移植も行われている。普段末梢��には造血幹細胞はいないが、白血球を増やす薬を注射すると骨髄から末梢血に出てくるので移植に使えるようになる。また、さい帯血にはもともと造血幹細胞が多く含まれているためだ。そして、骨髄移植、末梢血幹細胞移植やさい帯血移植を総称して、造血幹細胞移植と呼ぶようになった。
「造血幹細胞移植を行うときには、その前に“移植前処置”という治療が必要になります。通常の化学療法よりも強力な抗がん剤治療を行い、さらに放射線治療も加えます。こうした徹底した治療を行うことで、白血病細胞も正常細胞も回復できない状態にしてしまうのです」
照射される放射線の量は12グレイだ。致死量が6グレイと言われているので、致死量の2倍の放射線を照射することになる。致死量の2倍の放射線を照射したら死んでしまうのではないか、と疑問に思うかもしれない。しかし、おかしくはないのだ。
「体を構成している細胞の中で、放射線に最も感受性の高いのは、血球を作り出す血液の細胞です。6グレイの放射線をかけると、この細胞がやられ、血液を作り出す能力が失われてしまいます。そこで、致死量が6グレイと言われているのです。その2倍の放射線をかけるので、血液を作る細胞は完全にやられますが、それ以外の組織は12グレイの放射線に耐えることができます。その結果、体の中で血液を作る細胞だけが死滅し、他の臓器には影響がないのです。つまり、致死量を超える放射線を照射しても患者さんが死亡しないのは、血液を作る細胞が死滅した代わりに、造血能力を持つドナーの幹細胞を移植するからなのです」
下図に示したように、抗がん剤治療と放射線治療による移植前処置を行うと、正常細胞も白血病細胞も完全にたたかれ、回復することができなくなる。この状態を作り出して、造血幹細胞を移植し、ドナーの正常血液を増やすのである。
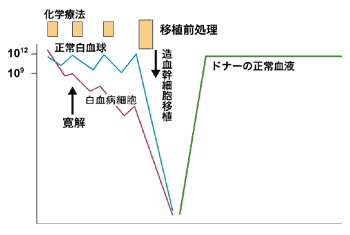
同じカテゴリーの最新記事
- ドナー不足を一気に解消したHLA半合致移植と移植後GVHDの新薬 白血病に対する造血幹細胞移植の最新情報
- 日本血液学会が『造血器腫瘍ゲノム検査ガイドライン』を作成 「遺伝子パネル検査」によりゲノム情報は、血液がんの正確な診断・治療に必須
- 血縁ドナーによる骨髄移植の成果に迫る 臍帯血移植は、難治性血液がんを救う切り札になり得るか
- 白血病に対する新しい薬物・免疫細胞療法 がん治療の画期的な治療法として注目を集めるCAR-T細胞療法
- 血液がんの上手な日常での副作用管理 感染症対策が最重要。骨髄移植した患者はとくに注意を!
- 治療が長引く可能性も 血液がん患者の口腔ケアはセルフケアと専門医とのタッグが重要
- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切
- “不治の病”とされていた血液がん。治療法の進歩で、治癒が目指せるがんへ これだけは知っておきたい! 血液がんの基礎知識 白血病編


