造血幹細胞移植を受けるにあたって知っておくべきこと 造血幹細胞移植―適応は、移植時期は、どの方法でやれば最善の選択か
骨髄異形成症候群の移植に適した時期とは?
図3は、骨髄異形成症候群について、高リスク群、低リスク群、中間リスク群1、中間リスク群2と分け、移植の時期と生存期間を分析したものである。
横軸は移植の時期で、右方向にいくほど遅い時期での実施となる(年単位)。縦軸はそれによって生存期間が延びるのか、短くなるのかをあらわす。
石川さんによると「高リスク群と中間リスク群2では、診断されたときに移植をしたほうが生存期間の延長につながるだろうし、低リスク群と中間リスク群1については、むしろしないほうがいいだろうということがいえます」
骨髄異形成症候群も他の白血病同様、予後が患者間で大きく違っている。そのため、診断時の予後予測にもとづいて、治療を選択する必要があるのだ。
「骨髄異形成症候群は骨髄移植をしないと治らないということはいえますが、低いリスクの場合は何年もの間きわめて落ち着いている時期があるというデータも出ているので、移植を受けていただく時期を決める際に参考になります」
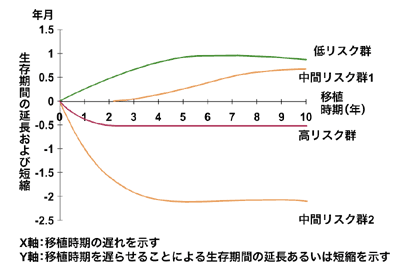
移植に伴う合併症前処置治療による副作用
造血幹細胞移植前に行われる、全身放射線照射や抗がん剤治療を前処置治療という。体内のがん細胞をできるかぎり死滅させることと、ドナーの造血幹細胞を受け入れるために患者さん自身の免疫力を弱めておくことが目的だ。
「前処置治療の方法は、造血幹細胞移植の種類や患者さんの年齢などの状況によっても異なりますが、全身放射線照射とエンドキサン(一般名シクロホスファミド)大量投与がベースにあり、それにキロサイド(一般名シタラビン)やラステット(またはベプシド、一般��エトポシド)を組み合わせるものがあります」
エンドキサン大量療法では、重い副作用として心毒性が知られている。心臓に負担がかかるため、患者さんの状況によってはアルケラン(一般名メルファラン)に変更することもある。
移植前治療で使う薬の副作用としては、吐き気・嘔吐、口内炎などの口腔粘膜障害、それに伴う痛みが多くみられる。粘膜で覆われている消化管の障害として下痢や腹痛が起こることもある。また全身放射線照射によっても、吐き気・嘔吐、口腔粘膜障害、疲労や食欲不振、皮膚症状などが出現してくる。
また、1998年ごろから、ミニあるいは緩和的前処置による同種移植が開発された。すなわち患者さん自身の免疫力さえ十分に弱めておけば、造血幹細胞が受け入れられることがわかったのだ。この方法は従来の前処置による移植に比べ、前処置による体のダメージが少ないことがわかっており、高齢者や合併症をもつ患者さんに広く行われるようになってきている。
免疫力の低下の影響で感染症への対策も重要
移植前治療で患者の白血球はほとんどゼロになっている。移植によって造血機能が回復するまで1カ月弱、極度に免疫機能が落ちた状態が続く。その間はさまざまな菌やウイルスに感染しやすく、感染すると重症化しやすいので無菌室ですごす。
「感染予防のために、あらかじめ抗生剤や抗真菌剤を服用します。たとえばアスペルギルスというカビは重症の肺炎を引き起こすことがあるため予防策が必須で、アスペルギルス肺炎が疑われる場合は、胸部CT検査などで早期に診断することが大切です」
また、患者さん自身の体内の細菌やウイルスにも注意が必要だ。
「以前にサイトメガロウイルスや水痘・帯状疱疹ウイルスに罹った患者さんは、ウイルスを体内にもっていて、免疫が落ちているとそれが暴れだします。自分の体内の細菌、たとえば腸内細菌を抑えるための抗生剤や、抗真菌剤、ウイルス感染症を予防するための薬を移植後早期からのんでいただきます」
白血球が回復してきたら、無菌室から一般病室に移る。免疫機能の回復を継続的にモニターし、リンパ球のなかでとくに抵抗力にかかわるCD4の値が200以下になるとカリニ肺炎の対策を、またガンマグロブリンが低値の人は、肺炎球菌などの感染の可能性もあるので、抗生剤で予防する。
「感染症の発症は、急性GVHD(移植片対宿主病)の治療でステロイドホルモン剤を使うか、また移植の種類(造血幹細胞の由来)などの要素によって変わってきます。ステロイドホルモン剤を使えば感染しやすくなりますし、さい帯血移植では造血機能の回復が遅く、免疫力の回復も遅いのではないかといわれています」
移植後、免疫抑制剤の使用を中止できるようになったら、慢性GVHDの程度などにもよるが、インフルエンザや肺炎球菌の不活化ワクチン接種が推奨されている。麻疹などの生ワクチンは免疫抑制剤をのんでいたり、慢性GVHDがあったりすると、控えるほうがよいとされている。
重篤になることもある移植片対宿主病
同種移植では、GVHD(移植片対宿主病)という合併症が起こってくることが多い。GVHDには「急性GVHD」と「慢性GVHD」とがあり、これは移植片(患者に移植したドナーの骨髄)に含まれるリンパ球が患者さん自身の細胞を異物として認識し、攻撃するために起こる免疫反応によって生じるものだ。
急性GVHDは移植後早期に起こってくる、皮膚(発疹)、肝臓(黄疸)、消化管(下痢)の症状である。軽いものでは皮膚に発疹がでる程度から、重症例では肝臓障害や大量の下痢のために重篤な状態を招くこともある。
それぞれの臓器の重症度をみるステージがあり(表4)、ステージの組み合わせからグレードを判定する。肝臓や消化管の症状があればグレード2、肝臓・消化管のステージが2以上ならばグレード3と判定される。
「グレード2、3であればステロイドホルモン剤を投与して、それが効かない場合は免疫抑制剤を変更して対処します。GVHDが重症化して免疫抑制剤で治療すると感染症のリスクが高くなり、難しいところです」
| ステージの定義 | |||
|---|---|---|---|
| ステージ | 皮膚 | 肝 | 消化管 |
| 皮疹 (%) | 総ビリルビン (mg/dl) | 下痢 (ml/day) | |
| 1 | <25 | 2~3 | 500~1,000または持続する嘔気 |
| 2 | 25~50 | 3~6 | 1,000~1,500 |
| 3 | >50 | 6~15 | >1,500 |
| 4 | 全身性紅皮症 (水泡形成) | >15 | 高度の腹痛・腸閉塞 |
| グレードの定義 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| グレード | 皮膚 | 肝 | 消化管 | ||
| ステージ | ステージ | ステージ | |||
| 1 | 1~2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 3 | or | 1 | 1 | |
| 3 | ― | 2~3 | or | 2~4 | |
| 4 | 4 | or | 4 | ― | |
慢性GVHDに多くみられる症状は、発疹などの皮膚の症状、口の中や眼球の乾燥、肺や食道の病変、肝臓障害など、さまざまな障害が起こることが知られているが、個人差も大きい。これらの症状に対しては、その程度に応じてステロイド剤やシクロスポリン、タクロリムスなどを用いた治療を行う。
「慢性GVHDの抗体療法として、悪性リンパ腫の治療薬であるリツキサン(一般名リツキシマブ)を用いて効く症例が報告されてきているので、今後期待される薬の1つです」
移植治療後、年数がたってから懸念されるのは2次がんだ。口腔内の扁平上皮がん、甲状腺がん、乳がんの発症リスクが上昇することが指摘されている。
「移植はリスクもある治療で選択が難しいものです。ただ、移植方法も合併症対策も進んできていますので、合併症の悩みが薬の適応などで改善してくることがあると思われます。今後は移植の適応や移植方法の使い分け、さらなる合併症対策が明らかになっていくことが期待されます」
同じカテゴリーの最新記事
- ドナー不足を一気に解消したHLA半合致移植と移植後GVHDの新薬 白血病に対する造血幹細胞移植の最新情報
- 日本血液学会が『造血器腫瘍ゲノム検査ガイドライン』を作成 「遺伝子パネル検査」によりゲノム情報は、血液がんの正確な診断・治療に必須
- 血縁ドナーによる骨髄移植の成果に迫る 臍帯血移植は、難治性血液がんを救う切り札になり得るか
- 白血病に対する新しい薬物・免疫細胞療法 がん治療の画期的な治療法として注目を集めるCAR-T細胞療法
- 血液がんの上手な日常での副作用管理 感染症対策が最重要。骨髄移植した患者はとくに注意を!
- 治療が長引く可能性も 血液がん患者の口腔ケアはセルフケアと専門医とのタッグが重要
- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切
- “不治の病”とされていた血液がん。治療法の進歩で、治癒が目指せるがんへ これだけは知っておきたい! 血液がんの基礎知識 白血病編
- 「不治の病」から「治癒可能な病」になったが、まだまだあなどれない これだけは知っておきたい白血病の基礎知識


