さい帯血移植の普及が白血病患者さんに治癒への希望を与えている さい帯血移植は骨髄移植と同程度の治療成績になってきた
骨髄移植とさい帯血移植の治療成績は同程度
さい帯血移植の治療成績はどの程度なのだろうか。
「当院と東京大学医科学研究所のデータでは、骨髄移植に劣らない治療成績が出ています。さらに、さまざまな国際的なデータを解析しても、両者は近年、ほぼ同等の治療成績を残しています。第1寛解期などに移植できる標準危険群では、骨髄移植もさい帯血移植も、共に6~7割が治癒に至っています」(谷口さん)
骨髄移植に遜色のない治療成績を誇るさい帯血移植だが、問題もある。最たる問題は、生着不全と生着遅延である。
移植された細胞が新しい場所で、その一部として生きて、機能し続けることを「生着」という。さい帯血移植などの造血幹細胞移植の場合でいえば、ドナーから移植した造血幹細胞が患者さんの骨髄の中に入り込んで、新たな白血球を作り始めることが生着である。
ということは、生着不全とは新しい白血球が作り出されないことで、生着遅延とは新しい白血球が作り出されるが、通常より時間がかかることになる。「さい帯血の中に含まれる造血幹細胞の数がには限りがあり、患者さんの体重あたりの細胞数がどうしても制限されるため、生着不全と生着遅延が起こりやすい」(谷口さん)という。とはいえ、最終的な生存率においては、骨髄移植に劣らない治療成績が近年出ている点は特筆すべきだろう。
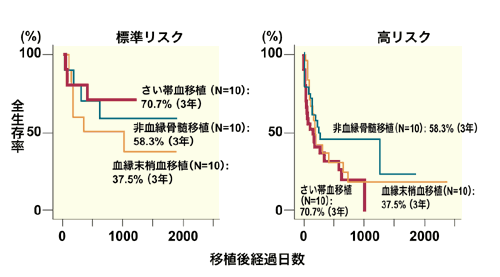
高齢者造血器疾患に対する幹細胞源間(さい帯血vs非血縁骨髄vs血縁末梢血幹細胞)のミニ移植成績の比較
さい帯血移植の可能性を広げた「ミニ移植」
骨髄移植もさい帯血移植も、移植を行う前には、前処置をする。通常は、大量の抗がん剤を投与し、なおかつ全身に多量の放射線を照射し、腫瘍細胞を叩いた上で移植を行う。これを「フル移植」という。
骨髄移植でもさい帯血移植でも、フル移植は臓器の機能が十分に保たれていて、比較的体力のある人にしか行えない。医療施設による違いがあるが、年齢も50歳以下や55歳以下といった制限が通常設けられている。
これでは、糖尿病や高脂血症などの何らかの持病を抱えている人や高齢者には移植ができない。そこで考えられるようになったのが「ミニ移植」である。
ミニ移植とは、移植前の抗がん剤治療と放射線治療を量を減らして行い、移植を行うことである。抗がん剤と放射線の量が少ない分、腫瘍細胞は残ってしまうが、体へのダメージは少なくてすむ。
実際、これまでにも、82歳の急性白血病の男性患者さんがミニ移植のさい帯血移植を受けた例が国内である。その患者さんは、この原稿を執筆している今現在、元気だという。
「腫瘍を叩くことを考えれば、抗がん剤と放射線はできるだけ多くかけたほうがよい。だから、若くて体力のある患者さんであれば、フル移植が望ましいでしょう。しかし、高齢者や体力のない方には、ミニ移植という選択肢もある。もっと正確にいえば、その人が耐えうる最大量の抗がん剤治療と放射線治療が最も望ましいといえます」(谷口さん)。ただし、この「耐えうる最大量」を見極めるのは決して容易ではないと谷口さんは話す。
さい帯血移植の副作用とそれに対する対応
さい帯血移植の副作用には、どのようなものがあるのだろうか。
移植後に最も起こる副作用は高熱だ。移植後、平均すると、9日後くらいから39~40℃ほどの高熱が出るため、谷口さんは「デイナイン・フィーバー」と名づけた。ほかには、湿疹や下痢なども起こりうる。
また、これらの副作用は「GVHD(移植片対宿主病)の1亜型でもある」(谷口さん)。
GVHDとは、移植されたさい帯血(移植片)の中に含まれているリンパ球が、患者(宿主)の組織や細胞を異物と認識して起こる免疫反応だ。一般的にさい帯血移植では、骨髄移植に比べてGVHDは重症化しにくいといわれる。
さて、デイナイン・フィーバーは、何の対策も講じなければ、100パーセント近く起こる。しかし、免疫抑制剤を投与することで、起こる割合はかなり減らせる。
「デイナイン・フィーバーが起きても、55歳以下の方なら、多くの場合、耐えられます。一方、55歳以上の方には通常、ステロイドの類の薬剤を投与します。すると、熱は一気に下がりますが、下げればよいというものでもない。それというのも、高熱が出ているというのは、免疫が活性化している証拠でもあるからです」(谷口さん)
特にミニ移植でさい帯血移植を行う場合は、腫瘍細胞が体内にかなり残っている可能性がある。すると、強烈な免疫反応が起きて、その反応によって、腫瘍は激烈に叩かれ、みるみる縮小していく。デイナイン・フィーバーが起きている陰では、こうした作用(「抗腫瘍効果」という)も働いているため、やみくもに解熱するのが望ましいわけではないのだ。
「デイナイン・フィーバーによって、最悪の場合、亡くなってしまう方もいます。しかし、デイナイン・フィーバーの背景には、抗腫瘍効果もある。デイナイン・フィーバーなどの副作用をどの程度抑えればよいのかは、医療現場としては難しい問題です」(谷口さん)
同じカテゴリーの最新記事
- ドナー不足を一気に解消したHLA半合致移植と移植後GVHDの新薬 白血病に対する造血幹細胞移植の最新情報
- 日本血液学会が『造血器腫瘍ゲノム検査ガイドライン』を作成 「遺伝子パネル検査」によりゲノム情報は、血液がんの正確な診断・治療に必須
- 血縁ドナーによる骨髄移植の成果に迫る 臍帯血移植は、難治性血液がんを救う切り札になり得るか
- 白血病に対する新しい薬物・免疫細胞療法 がん治療の画期的な治療法として注目を集めるCAR-T細胞療法
- 血液がんの上手な日常での副作用管理 感染症対策が最重要。骨髄移植した患者はとくに注意を!
- 治療が長引く可能性も 血液がん患者の口腔ケアはセルフケアと専門医とのタッグが重要
- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切
- “不治の病”とされていた血液がん。治療法の進歩で、治癒が目指せるがんへ これだけは知っておきたい! 血液がんの基礎知識 白血病編
- 「不治の病」から「治癒可能な病」になったが、まだまだあなどれない これだけは知っておきたい白血病の基礎知識


