白血病とは:治療~現状~診断
時間をおかずにただちに移植
さい帯血ミニ移植はさい帯血移植とミニ移植の両輪に支えられているが、それぞれのめざましい発展と特長について詳述してみよう。日本でさい帯血移植がスタートしたのは1997年。その後、2003年に1000例を突破し、04年末現在で2106例に達した。
「当初は16歳以下の子どもの患者を対象とする治療法との印象が強かったのですが、03年を境に成人のさい帯血移植が月を追うごとに急増し、もっとも歴史を有する骨髄移植に迫る勢いで増えてきました。事実、昨年の骨髄バンクを介した骨髄移植は798件なのに、さい帯血移植は697件と迫り、その8割近くが成人によって占められています」(谷口さん)
さい帯血移植が急増したのは第1に、先述したようにドナーと患者のHLAが完全に一致していなくてもよいため、それだけ移植可能なさい帯血が多いからだ。
第2にさい帯血は出産時に採取されるとただちにマイナス196度で凍結保存され、必要とされたときにすみやかに移植ができることも急増の大きな要因だ。
骨髄バンクを介した骨髄移植はHLAの適合ドナーが見つかっても、通常、バンクへ患者が登録し実際に移植を受けるまで平均約5カ月を要する。ドナーの検診や意思確認などのコーディネートを必要とするためだ。
「しかし、白血病が進展しそれをうまく抑えられなくなった移植希望患者の生存期間中央値は、6カ月に満たないのが現状です。当然、移植に間に合わない患者が後を絶たないのですが、すでに凍結保存中のさい帯血を使用するさい帯血移植では、そのような心配がありません」(谷口さん)
そして第3にさい帯血を採取する技術が向上し、移植に必要な十分な量が確保できるようになったことが要因としてあげられる。
さい帯血の造血幹細胞は骨髄のそれより増殖能力が旺盛だから、骨髄移植の約10分の1の量で足りる。それでも患者の体重1キロあたり2000万個が必要とされ、体重35キロの患者なら7億個の造血幹細胞を必要とする。
「以前はさい帯血から採取した造血幹細胞は平均7億個にとどまっていたため、移植可能な患者が子どもや体重の少ない大人に限られていました。最近はさい帯血の採取テクニックが向上し、体重の重い大人にも十分な量の造血幹細胞が確保されるようになってきました」(谷口さん)
一方、ミニ移植は1997年から始められ、50歳以上の高齢者や、心臓や肺、肝臓、腎臓などの重要な臓器に病気を抱えている患者に行われるようになった。とりわけ、急性骨髄性白血病の患者のうち60歳以上の患者が半数を超えるという報告もあり、高齢患者に造血幹細胞移植ができないのは大きな問題とされていたが、それを克服したのがミニ移植である。従来の抗がん剤の大量投与と放射線の大量照射に耐えられない患者を対象に、ここ7~8年のうちに急速に普及してきた。
治療の尽きた患者の1年生存率が33%
では、さい帯血ミニ移植の治療成績はどうかというと、これまでの骨髄移植などと比べ勝るとも劣らないといえる。
「虎の門病院では年齢中央値が58.5歳とかなり高齢な約170人の患者さんにさい帯血ミニ移植を行ってきましたが、33パーセントの患者さんが1年以上存命しておられます」(谷口さん)
さい帯血ミニ移植を受けたのは、すでに抗がん剤がまったく効かなくなり治療法も尽き、100日以上の生存を期待できない高齢の患者が数多く含まれているといった背景を考えると、非常に優れた治療成績だろう。
「ただし、さい帯血ミニ移植はまだ2、3年の歴史しかありません。治療成績の優劣は厳密な臨床試験(無作為比較試験)によってしか立証できないのですが、それもまだなされておりません。まだ臨床研究段階の治療法であることも忘れてはならないでしょう」(谷口さん)
さい帯血ミニ移植のリスクとしては、ドナーの造血幹細胞が患者の身体に根づき(生着)にくいということがあげられる。国際的にはさい帯血移植は10~20パーセントが生着不全を起こすと報告されている。
「虎の門病院のさい帯血ミニ移植の生着不全は8パーセントです。骨髄移植が3パーセント以下ですから、その点ではリスクが高いといえます」(谷口さん)
移植後、40日を超えても移植造血幹細胞からの白血球が増えてこないときは、生着不全=拒絶と判断する。そのままにしておくと患者は死亡するため、すみやかにもう一度他のさい帯血を用いて移植を試みる。
さい帯血ミニ移植のリスクとして、骨髄移植と比べると生着が遅れがちで、より時間を要するためそれだけ感染症にかかるリスクも高くなることもあげられる。
また、生着後は移植片対宿主病(GVHD)に対しても厳重な管理が行われなければならない。GVHDは造血幹細胞からつくられたリンパ球が、患者の身体を異物として認識・攻撃するために生じるさまざまな症状だ。このため、赤い皮疹や肝機能障害、下痢、腹痛などの症状が現れるが、さい帯血ミニ移植は、このGVHDによって白血病細胞なども死滅させるので、患者の限界内で我慢してもらう。
「患者さんが耐えられなくなったときは、シクロスポリンの増量やステロイドなどを投与して症状の改善をはかります」(谷口さん)
さい帯血ミニ移植は抗がん剤や放射線による死亡は少ないものの、感染症やGVHD等による治療関連死は無視できない。開発当初は移植後100日以内の死亡が40~50パーセントと大きな問題であった。現在では、GVHD予防法や感染症対策を再検討し、この高い死亡率がかなり減少してきている。
急性骨髄性白血病をはじめとする血液のがんは、年齢を重ねるほど発病率が高くなる。加えて、高齢者は兄弟姉妹の病気や死亡により、家族の中からHLA適合ドナーが得られにくい。
そういった条件を考えると、90パーセント以上の確率で移植可能なさい帯血が見つかり、高齢でも造血幹細胞移植を可能とするさい帯血ミニ移植に大きな期待が寄せられる。
さい帯血ミニ移植は造血幹細胞移植の歴史に新たな1ページを開いた。造血幹細胞移植が受けられなかった患者に移植できる道を拓いた功績は非常に大きい。早急に標準的治療として確立されることが望まれている。
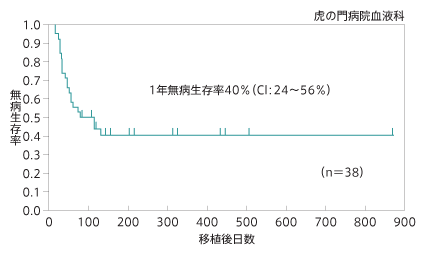
虎の門病院血液内科でさい帯血ミニ移植を受けた患者の無病生存率。
急性骨髄性白血病および骨髄異型性症候群を対象にしたデータ
同じカテゴリーの最新記事
- ドナー不足を一気に解消したHLA半合致移植と移植後GVHDの新薬 白血病に対する造血幹細胞移植の最新情報
- 日本血液学会が『造血器腫瘍ゲノム検査ガイドライン』を作成 「遺伝子パネル検査」によりゲノム情報は、血液がんの正確な診断・治療に必須
- 血縁ドナーによる骨髄移植の成果に迫る 臍帯血移植は、難治性血液がんを救う切り札になり得るか
- 白血病に対する新しい薬物・免疫細胞療法 がん治療の画期的な治療法として注目を集めるCAR-T細胞療法
- 血液がんの上手な日常での副作用管理 感染症対策が最重要。骨髄移植した患者はとくに注意を!
- 治療が長引く可能性も 血液がん患者の口腔ケアはセルフケアと専門医とのタッグが重要
- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切
- “不治の病”とされていた血液がん。治療法の進歩で、治癒が目指せるがんへ これだけは知っておきたい! 血液がんの基礎知識 白血病編
- 「不治の病」から「治癒可能な病」になったが、まだまだあなどれない これだけは知っておきたい白血病の基礎知識


