レブラミドやビダーザなどの新薬で治療成績は向上 新薬で白血病への移行をストップ!骨髄異形成症候群の最新治療
生存期間の延長が認められた新薬ビダーザ
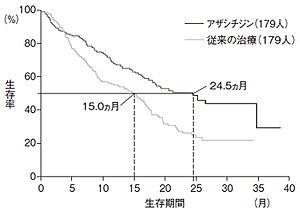
リスクが高い骨髄異形成症候群(芽球の増加を伴う不応性貧血)の治療法としては、根治治療としてまずは移植治療を考慮します。ただし、移植治療は身体的負担が大きいので、年齢、他の臓器に障害が少ないことなどが実施条件となります。なお、移植が適応となる年齢は、一般的には60歳以下とされています。
では、移植が難しい患者さんでは、どのような治療が行われるのでしょうか。
「移植ができない患者さんには薬物療法が選択されます」
と小倉さんは言います。
芽球の増加を伴う不応性貧血(RAEB-1、RAEB-2)は、これまで急性骨髄性白血病に準じた抗がん剤治療が行われていました。しかし、2011年に骨髄異形成症候群において、初めて生存期間の延長が認められたとして、ビダーザ(*)という薬剤が承認され、現在は第1選択薬として使用されています。
リスクの高い骨髄異形成症候群の患者さんを対象とした海外の臨床試験の結果では、従来の治療薬を使用した群の生存期間中央値が15カ月であったのに対し、ビダーザを使用した群の生存期間中央値は24.5カ月と、有意な延長が確認されました。
非常に高い確率で白血病へと移行していた骨髄異形成症候群の患者さんが、ビダーザによる治療で、白血病への移行が抑えられるようになったのです。
「ビダーザは残念ながら病気を根治することはできませんが、白血病への移行率が下がる点で非常にいい治療法だと思います」
また、ビダーザは注射剤であるため、通院などの患者負担はとても大きく、現在は治療負担を軽減するなどの観点から、経口薬の開発も進められています。
「経口薬は、患者さんにとって非常に楽な治療法です。こうした経口薬が出てくると、さらに治療の幅は広がると思います」
*ビダーザ=一般名アザシチジン
レブラミド今後の適応に期待
骨髄異形成症候群の患者さんの半数以上は、染色体の一部に異常が見られます。最もよく見られる染色体異常の1つに、5番染色体の長腕部の欠損があり、骨髄異形成症候群の患者さんの20~35%を占めているといわれています。このタイプの骨髄異形成症候群にはレブラミド(*)が第1選択薬となります。
このタイプの患者さんは、他のタイプの骨髄異形成症候群と比べてレブラミドの治療反応性がよいと考えられており、優れた治療効果が示されています。
2010年に承認されたレブラミドは、5番染色体に異常のある骨髄異形成症候群の患者さんにおいて、比較試験の結果、貧血を改善し、急性骨髄性白血病への進展リスクを上昇させず、死亡のリスクを低下させるという良好な結果を得ました。生存期間の中央値はレブラミド治療群で5.2年、レブラミド非治療群では3.8年でした。
レブラミドは他の病型への効果についても注目されており、現在、臨床試験が始まっています。将来、骨髄異形成症候群のすべての治療にレブラミドが使えるようになると、さらに治療の選択肢が増えることになります。
ただし、染色体異常が認められていても、芽球の数が増えている場合には、ビダーザが用いられるということです。
「現在、新薬のビダーザ、レブラミドは白血病への進行を遅らせるというエビデンス(科学的根拠)が得られています。臨床データが蓄積されると、どの病型によく効くのかについても今後わかってくるのではないでしょうか」
*レブラミド=一般名レナリドミド
骨髄異形成症候群と上手に付き合うために
患者さんが日常生活で最も気をつけなければならないことは、感染です。骨髄異形成症候群の患者さんは、骨髄で作られた血液細胞が不良品であるため、免疫力が落ちて感染しやすくなっています。
しかし、骨髄異形成症候群という病気は、病型にもよりますが、一般的にゆっくりと進行するため、病気の経過にさえ気をつけていれば、日常生活を支障なく送ることもできます。
「この病気はゆっくりと経過をたどりますから、定期的に病気の経過をみて、患者さんのライフスタイルや身体状態に合った治療を選択していく、というのが1番いいと思います。骨髄異形成症候群を『慢性疾患』と考え、身体状態がよい場合は『普通の生活を送る』ことを心がけるようにしてください」
ここ数年、遺伝子異常の解明に向けた研究は飛躍的に進んでおり、海外の血液学会などでは、遺伝子研究の発表が相次いでいるそうです。
「どの遺伝子に異常が起きているからこの病気になっているのかということが1つでもわかれば、グリベック(*)のような画期的新薬が出てくる可能性も夢ではありません」
今後の薬剤の開発にも期待がかかる骨髄異形成症候群。あきらめることなく、上手に病気と付き合うことが大切といえそうです。
*グリベック=一般名イマチニブ。慢性骨髄性白血病の治療に使われる薬剤
同じカテゴリーの最新記事
- 日本での新薬承認が待たれる 骨髄異形成症候群の最新薬物療法
- 骨髄異形成症候群(MDS)の正体を知ろう 高リスクの骨髄異形成症候群にはビダーザが決定打。今後の新薬承認に期待
- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切
- リスクに応じた治療戦略がカギ 骨髄異形成症候群の最新治療
- 治療法がなかなかなかった難治性の病気に、延命への希望が生まれた 2種類の薬の登場により骨髄異形成症候群の治療は新時代へ!
- 大型新薬の登場で、薬物療法の選択肢が広がっている 完治も期待できるレブラミド。高リスクに有効な新薬も承認間近
- 早期に見つけるには年1回以上の血液検査を 「貧血」「出血傾向」「抗がん剤経験者」に要注意!
- あなたの骨髄、血液細胞は大丈夫ですか? 要注意は高齢、抗がん剤、放射線被曝


