治療法がなかなかなかった難治性の病気に、延命への希望が生まれた 2種類の薬の登場により骨髄異形成症候群の治療は新時代へ!
高リスクと低リスクで治療法が異なる
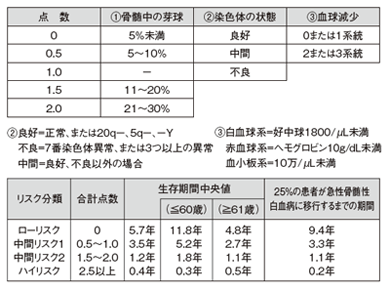
[表4 骨髄異形成症候群の治療]
| 薬物療法名 | 低リスク | 高リスク |
|---|---|---|
| ①エリスロポエチン製剤 (エスポー、エポジン、ネスプなど) | 日本では使えない | |
| ②蛋白同化ホルモン (プリモボラン、ボンゾール) | 効果がある可能性あり | |
| ③ビタミンK, D | 効果がある可能性あり | |
| ④免疫抑制療法 (シクロスポリン、サイモグロブリン) | 効果がある可能性あり | |
| ⑤レナリドミド(レブラミド) | 5q-タイプの骨髄異形成 症候群では標準的治療 | |
| ⑥メチル化阻害剤(ビダーザ) | 効果が望める(ただし、 副作用も予想される) | 効果がある可能性大 なので、最初に選ぶ |
| ⑦化学療法 | 効果がある可能性あり | |
| ⑧造血幹細胞移植 | 病状次第で実施 | 可能なら標準的治療 |
| ⑨支持療法(輸血・鉄キレート療法) | 標準的治療 | 標準的治療 |
この病気の治療に関しては、まず前提となる事実を知っておく必要がある。
「骨髄異形成症候群は、骨髄移植などの造血幹細胞移植でしか完治が望めない病気です。���般的には、移植の対象を65歳未満としている医療機関が多いので、半分くらいの患者さんは、対象からはずれます。そういった人たちは、最初から完治しない病気として治療に取り組む必要があるわけです」
では、治療にはどのような方法があり、どのように進められるのだろうか。
「治療方針を決めるときに大切なのは、その患者さんがどのような経過をたどるのかを把握することです。
そのために、国際予後判定基準(IPSS)が用いられます。骨髄中の芽球の割合、染色体異常の種類、減少している血液細胞の種類などを調べて点数を出し、その合計点数から予後の見通しを立てます」
具体的な点数のつけ方は表3に示した通り。これらの点数から、ローリスク、中間リスク1、中間リスク2、ハイリスクの4段階に分類する。
「どこに入るかで、予後は大きく異なります。たとえば、ハイリスクの場合、半年前後で半分の方が亡くなりますが、ローリスクの患者さんは、5年たっても半分以上が生存しています」
国際予後判定基準では4段階に分類するが、実際の治療では、低リスク(ローリスク+中間リスク1)と高リスク(中間リスク2+ハイリスク)の2つに分けて考えることが多いそうだ。
「このように2つに分けると、低リスクと高リスクで、病気の性質が違っていることがわかります。低リスクの患者さんは、正常な血球がつくれないことが主な問題。これに対し、高リスクの人たちは、異常な細胞である芽球がどんどん増えていることが問題なのです」
したがって、低リスクの治療では、不足している血球をどうにかして補うことが主な目標となる。それに対し、高リスクの患者さんでは、増えていく異常な細胞を、どうやって減らすかがポイントになるのだ。
高リスク患者の生存が初めて延びた薬
高リスクの場合、どのような治療が行われるのだろうか。
「予後が良くないので、積極的な治療を行います。移植が可能ならば、すぐに移植を受けることが勧められます。移植ができない場合は化学療法ですが、従来は化学療法による生存期間の延長は期待できませんでした」
化学療法には、大量の抗がん剤をまとめて投与する方法と、低用量の抗がん剤を継続して投与する方法があるが、どちらにも延命効果はなかった。低用量療法でQOL(生活の質)の改善が少し見られるだけだったのだ。
そこで期待されているのが、今年1月に承認され、これから使われるようになるビダーザ(*)である。海外で行われた高リスク患者を対象にした臨床試験では、従来の治療群の生存期間中央値が15.0カ月だったのに対し、ビダーザ治療群は24.5カ月と大幅に改善されたのだ。骨髄異形成症候群の患者さんは、最終的には白血病になる可能性が高いが、ビダーザによる治療で白血病への移行が抑えられるのだという。
「ビダーザは、高リスクの患者さんを対象にした臨床試験で、初めて生存期間が延びることを証明した治療薬です。高リスクに対しては、第1選択薬として使われるようになるでしょう」
ビダーザは注射剤で、1カ月のうち1週間だけ連日投与し、そのほかの日は休薬。それを繰り返していく。問題となる副作用は血球減少で、とくに使い始めの2~3カ月は大幅に下がる。
「ビダーザは低リスクの患者さんにも使える薬です。ただ、得られる効果と副作用の危険性を考えると、低リスクに対しても積極的に使うべきかどうか、まだ結論は出ていません」
*ビダーザ=一般名アザシチジン
副作用が少ないレブラミドの今後に期待
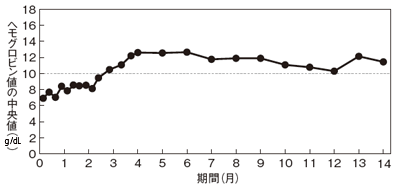
低リスクに対する治療では、再生不良性貧血の治療でも使われる蛋白同化ホルモンや免疫抑制剤による治療が行われたり、ビタミンKやDが使われたりしている。
これに加え、5q-症候群に対しては、昨年からレブラミド(*)が使えるようになった。
「レブラミドは5q-症候群の標準治療薬です。ただし、5q-症候群は欧米には多いのですが、アジアでは非常にまれです。したがって、この薬を使える患者さんは、日本ではあまり多くありません。ただ、5q-症候群以外のタイプにも効くのではないかということで、日本でも治験が始まっています。将来は、ほかのタイプにも使えるようになるかもしれません」
レブラミドがすべての骨髄異形成症候群に使えるようになると、治療の選択肢が増えることになる。レブラミドはビダーザに比べて副作用が軽く、経口剤という便利さもある。そこで、まずレブラミドを使い、それでだめならビダーザという使い方になるのではないか、というのが鈴木さんの予想だ。
低リスクの場合、移植をどうするかも問題になる。移植にはそれなりの危険性が伴うので、たとえ可能であってもあわてて行う必要はない。
- こまめに休息を取る(とくに赤血球が少ない場合)
- ケガをしないように注意する(とくに血小板が少ない場合)
- うがい・手洗いをまめにする(とくに白血球が少ない場合)
- 栄養バランスのよい食事をとる
「基本的には、低リスクから高リスクに移行する時点で、実施するかどうかを検討すればいいでしょう。そのほか、たびたび輸血する必要があるなど、生活に支障をきたしている場合も、可能ならば移植を考えていいと思います」
骨髄異形成症候群の治療は、新しい薬の登場で大きく進歩すると考えられている。実際にどのような成果が現れるのかに注目していきたい。
*レブラミド=一般名レナリドミド
同じカテゴリーの最新記事
- 日本での新薬承認が待たれる 骨髄異形成症候群の最新薬物療法
- 骨髄異形成症候群(MDS)の正体を知ろう 高リスクの骨髄異形成症候群にはビダーザが決定打。今後の新薬承認に期待
- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切
- リスクに応じた治療戦略がカギ 骨髄異形成症候群の最新治療
- レブラミドやビダーザなどの新薬で治療成績は向上 新薬で白血病への移行をストップ!骨髄異形成症候群の最新治療
- 大型新薬の登場で、薬物療法の選択肢が広がっている 完治も期待できるレブラミド。高リスクに有効な新薬も承認間近
- 早期に見つけるには年1回以上の血液検査を 「貧血」「出血傾向」「抗がん剤経験者」に要注意!
- あなたの骨髄、血液細胞は大丈夫ですか? 要注意は高齢、抗がん剤、放射線被曝


