大型新薬の登場で、薬物療法の選択肢が広がっている 完治も期待できるレブラミド。高リスクに有効な新薬も承認間近
エビデンスのある薬はほとんどなかった
「移植で救える患者さんは限られます。骨髄異形成症候群の治療では、薬物療法がメインになるべきだと私は考えています。しかし、骨髄異形成症候群ではこれまで、有効というエビデンスのある薬がほとんどなく、薬物療法の治療成績はなかなか上がりませんでした。このことは、骨髄異形成症候群の予後の悪さにもつながっています」
骨髄異形成症候群の薬物療法では、さまざまな薬剤による試行錯誤が繰り返されてきた。
「私がよく使っているのは、プリモボラン(一般名メテノロン)というたんぱく同化ステロイド剤。造血機能を高める働きがあり、貧血の場合、2~3割の人が改善します。一定条件に当てはまる患者さんには、シクロスポリン(一般名)という免疫抑制剤もよく効きます。この薬は造血幹細胞の減少を抑えると考えられ、5割以上の人の血液状態が改善します。しかし、まだ予後の延長効果までは確認できていません。また、ビタミンKには、芽球を自滅させる働きがあるので使ってみましたが、あまり奏効しませんでした」
そのほか、高リスク群では、キロサイド(一般名シタラビン)とアクラシノン(一般名アクラルビシン)、G-CSF(顆粒球コロニー刺激因子)を併用するCAG療法がよく行われる。副腎皮質ホルモン+ビタミンD併用療法などもある。しかし、いずれの治療法も、目立った効果はないのが現状だという。
24パーセントが完全寛解した
そうしたなか、骨髄異形成症候群の既存の薬物療法を一変させるような新薬が登場した。それがレブラミド(一般名レナリドミド)だ。
レブラミドは、サリドマイドの誘導体(構造が似ている化合物)で、がん化した細胞を自滅させたり、サイトカイン(細胞から分泌される生理活性物質)の産生によって免疫を高めたりする、さまざまな作用を持つと考えられている。
「骨髄異形成症候群には、5qマイナス症候群という特殊な病型があります。これは、細胞核内の染色体(1番~22番染色体、性染色体の計23対がある)のうち、5番染色体長腕部のみに欠失があるタイプ。芽球の割合��5パーセント未満で白血病に移行しにくく、予後は比較的よいとされています。ただし、貧血になりやすく、高頻度で輸血を余儀なくされる患者さんが少なくありません。レブラミドは、5qマイナス症候群に特異的に効くことが研究過程でわかったのです」
5番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群(低リスク群)の患者さん205名を対象とした海外第3相臨床試験では、1日10ミリグラムのレブラミドを投与した群(41名)のうち、約6割の人の赤血球輸血が不要になった。さらに、染色体異常に対する奏効率は42パーセントで、24パーセントが完全寛解(肉眼的にがんが消失すること)した。
「こうした効果は、今までの骨髄異形成症候群の薬では考えられなかったこと。染色体異常が消失する理由は不明ですが目下、その解明に向けて遺伝子レベルの研究が進行中です。また、レブラミドによって、長期間にわたる輸血や鉄キレート剤の使用から解放されることは、患者さんのQOL(生活の質)の向上にも貢献するでしょう。レブラミドは、5番染色体長腕部欠失のない病型でも研究が進んでおり、血球減少の抑制といった効果が期待されています」
レブラミドは2010年8月、5番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群の治療薬として、日本でも承認され、全国の医療機関で使われ始めた。
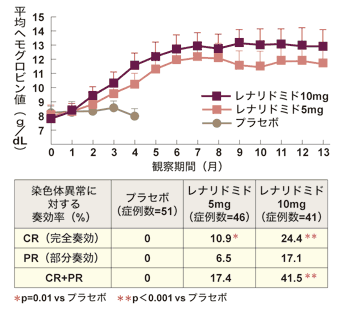
開発中の新薬も目白押し
骨髄異形成症候群では、さらなる大型新薬の登場が控えている。ビダーザ(一般名アザシチジン)とダコジェン(一般名デシタビン)だ。どちらもがん抑制遺伝子の働きを保つメチル化阻害剤で、海外ではすでに骨髄異形成症候群の治療薬として普及している。ビダーザは、早ければ年内にも日本で承認される見通しだ。
「ビダーザは、高リスク群の骨髄異形成症候群にも優れた効果があり、生存期間中央値を9カ月延ばすことが臨床試験でわかっています。5番染色体長腕部に欠失のあるタイプは日本人には少なく、骨髄異形成症候群全体の数パーセントなので、レブラミドを使える患者さんは限られます。しかし、ビダーザが日本に上陸すれば、多くの患者さんが恩恵を受けられるようになり、骨髄異形成症候群の生命予後のさらなる改善が期待されます」
このほかにも、ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤(*)のボリノスタット(一般名)、プリンヌクレオチド系代謝拮抗薬(*)のクロファラビン(一般名)、アルキル化剤のクロレタジン(一般名)など、開発中の治療薬は目白押しだ。
「劇的な効果は期待できないまでも、有望視されている新薬がいくつかあります。レブラミドやビダーザとともに、それらの薬も使えるようになれば、薬物療法の選択肢は広がり、治療成績も高まるでしょう」
骨髄異形成症候群の領域では最近、レブラミドと5qマイナス症候群のように、治療法の研究と遺伝子解析が同時並行で行われている。
「骨髄異形成症候群の遺伝子解析は複雑なため、時間がかかると思われますが、臨床と連動することでスピードアップする可能性があります。そうなれば、新薬開発にも弾みがつくという相乗効果が出てきます。薬物療法が骨髄異形成症候群の治療法の柱になる日も、そう遠くはないでしょう。骨髄異形成症候群の治療には、明るい展望が開けていると考えています」
木崎さんは、目を輝かせながらそう語った。
*ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤=がん細胞が分裂・増殖する際に必要なヒストン脱アセチル化酵素の働きを阻害する薬
*プリンヌクレオチド系代謝拮抗薬=がん細胞のDNA合成を妨げる抗がん剤の一種
| 商品名 (一般名) | 主な特徴 |
|---|---|
| ビダーザ (アザシチジン) | p15などのがん抑制遺伝子がメチル化という化学反応によって、その働きを失うことを防ぐメチル化阻害剤。高リスク群にも優れた効果がある。日本でも承認申請中 |
| ダコジェン (デシタビン) | ビダーザと同じメチル化阻害剤。白血病への移行を遅らせる効果がある |
| (ボリノスタット) | ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤。ダコジェンとの併用で骨髄異形成症候群に有効だったとの研究報告がある |
| (クロファラビン) | プリンヌクレオチド系代謝拮抗薬。高リスクの骨髄異形成症候群に著効を示したとの研究報告がある |
| ラムロスチン (クロレタジン) | アルキル化剤。第2相臨床試験で骨髄異形成症候群に有効という結果が出た |
同じカテゴリーの最新記事
- 日本での新薬承認が待たれる 骨髄異形成症候群の最新薬物療法
- 骨髄異形成症候群(MDS)の正体を知ろう 高リスクの骨髄異形成症候群にはビダーザが決定打。今後の新薬承認に期待
- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切
- リスクに応じた治療戦略がカギ 骨髄異形成症候群の最新治療
- レブラミドやビダーザなどの新薬で治療成績は向上 新薬で白血病への移行をストップ!骨髄異形成症候群の最新治療
- 治療法がなかなかなかった難治性の病気に、延命への希望が生まれた 2種類の薬の登場により骨髄異形成症候群の治療は新時代へ!
- 早期に見つけるには年1回以上の血液検査を 「貧血」「出血傾向」「抗がん剤経験者」に要注意!
- あなたの骨髄、血液細胞は大丈夫ですか? 要注意は高齢、抗がん剤、放射線被曝


