サリドマイドの誘導体レナリドミドの高奏効が明らかに。新薬も検討中 病態解明に確実な進歩。骨髄異形成症候群の最新治療
半数に急性骨髄性白血病
白血球も、他の血球と同じように骨髄の造血幹細胞が分化、成熟して作られる。これが、成熟途中で異常を起こすと、白血球になる前の「芽球」(ブラスト)と呼ばれる未熟な細胞が増えてくる。これがいわゆる白血病細胞だ。こうした状態が進行して骨髄の中で芽球が増えた状態を「前白血病状態」と呼ぶ。その中から、本当に急性骨髄性白血病になる人も出てくるのである。
小川さんによると、現在の診断分類(WHOの分類)では、骨髄に占める芽球の割合が、20パーセントを超えると、急性骨髄性白血病と診断されるとのこと。「最終的には、骨髄異形成症候群の半分ぐらいの人が急性骨髄性白血病になると推測されている」という。
| WHO分類 | |||
|---|---|---|---|
| 日本語名称(仮称) | 英語略 | 末梢血所見 | 骨髄所見 |
| 不応性貧血 | RA | 貧血 芽球(-) またはごくわずか | 赤血球系の異形成のみ 環状鉄芽球15%未満 |
| 多系統の異形成を伴う 不応性血球減少 | RCMD | 血球減少(2~3系統) 芽球(-) またはごくわずか Auer小体(-) 単球1×109/L未満 | 2系統以上で10%以上の細胞に異形成(+) 骨髄中芽球5未満Auer小体(-) 環状鉄芽球が総赤芽球の15%未満 |
| 鉄芽球性不応性貧血 | RARS | 貧血 芽球(-) | 環状鉄芽球15%以上 赤血球系の異形成のみ 芽球5%未満 |
| 鉄芽球増加がみられる 多系統の異形成を伴う 不応性血球減少 | RCMD-RS | 血球減少(2~3系統) 芽球(-) またはごくわずか Auer小体(-) 単球1×109/L未満 | 2系統以上で10%以上の細胞に異形成(+) 芽球5%未満Auer小体(-) 環状鉄芽球が総赤芽球の15%以上 |
| 芽球増加を伴う 不応性貧血-1 | RAEB-1 | 血球減少 芽球5%未満 Auer小体(-) 単球1×109/L未満 | 1~3系統で異形成(+) 芽球5~9%Auer小体(-) |
| 芽球増加を伴う 不応性貧血-2 | RAEB-2 | 血球減少 芽球5%未満 Auer小体(±) 単球1×109/L未満 | 1~3系統で異形(+) 芽球10~19%Auer小体(±) |
| 5q-症候群 | 5q-syndrome | 貧血 血小板数は正常 または増加 芽球5%未満 | 低分葉核をもつ巨核球が正常または増加 芽球5%未満染色体検査でdel(5q)の単独異常 Auer小体(-) |
| 分類不能型MDS | MDS-U | 血球減少 芽球(-) またはごくわずか Auer小体(-) | 赤血球系以外の1系統で異形成(+) 芽球5%未満 Auer小体(-) |
| 急性骨髄性白血病 | |||
| 骨髄異形成/骨髄増殖性疾患 | |||
実際には、骨髄異形成症候群はいくつかのタイプに分類されていて、それによって性格にも違いがある。WHOによる分類では、不応性貧血(RA)や鉄芽球性不応性貧血(RARS)は芽球が少なく、不応性貧血の側面が強い。
一方、芽球の増加を伴う種類の不応性貧血(RAEB)は前白血病状態が強い。つまり、より進行した状態といえる。「不応性貧血(RA)のまま経過する人もいる」そうだが、貧血が進行して輸血が必要になったり、RAEBに移行することも少なくない。そして、芽球が20パーセントを超えると、急性骨髄性白血病と診断されることになる。
ただ、急性骨髄性白血病という病名は同じでも、通常の急性骨髄性白血病と骨髄異形成症候群から発症した急性骨髄性白血病では、かなり性格が異なる。
「通常の急性骨髄性白血病の場合は、2、3カ月前まではとくに異常がなく普通にしていたのに、急激に白血病細胞が増加して症状が現れます。ところが、骨髄異形成の場合は数カ月から数年を経てジワジワと芽球が増加し、急性骨髄性白血病と診断されるようになります。5年ぐらい前から貧血や血小板減少があったなど、しばしば白血病の発症以前に健康診断などを契機として血液の異常が認められることが多いのが特徴です」と小川さんは説明する。
つまり、急性といってもだんだんと時間を追って芽球が増加し、急性骨髄性白血病になっていくのである。おそらく、遺伝子変異が積み重なって、骨髄異形成症候群から急性骨髄性白血病に移行していくのだろうと見られている。治療という点でも、両者には同じような治療が行われるのだが、通常の急性骨髄性白血病に比べて、骨髄異形成症候群から移行したタイプは治療に対する反応が悪く、白血病に対する通常の治療法では長期生存は難しいのが実情だという。
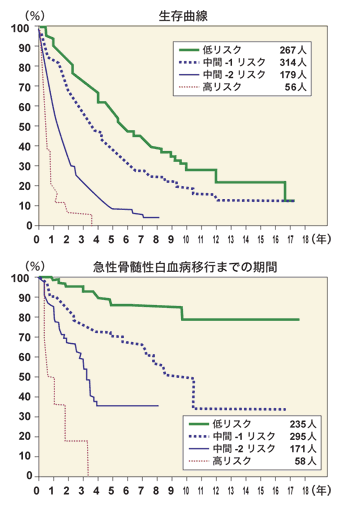
完治を望めるのは骨髄移植
では、治療にはどのような方法があるのだろうか。
小川さんによると、現在日本で行われている治療法は、(1)造血幹細胞移植、(2)抗がん剤による化学療法、(3)がんに対する積極的な治療は行わず、貧血には輸血、感染症には抗生剤など症状に応じて対症療法を行うサポーティブケア(支持療法)の3つが中心とのこと。
このうち、現在完治が期待できるのは、造血幹細胞移植に限られている。しかし「大まかに言って4割ぐらいは治りますが、残りの半分は再発し、半分は治療による副作用で命を落とす」というように、治療に伴うリスクも高いのが実情だ。
一方、化学療法では、急性骨髄性白血病に準じた強力な抗がん剤を使う「多剤併用療法」と少量の抗がん剤を使うマイルドな「低用量分化誘導療法」がある。小川さんによると、「芽球が増加して急性骨髄性白血病に近い状態の人が、強力な化学療法に反応することもある」のだそうだ。この場合は、キロサイド(一般名シタラビン)を基本にイダマイシン(一般名イダルビシン)やダウノマイシン(一般名ダウノルビシン)を組み合わせることが多い。ただし、劇的に効果があるというわけではなく、寛解に持ち込めたとしても、再発する可能性が大きい。副作用による治療関連死の危険もあり得る。
実際には、この病気は高齢者に多いので、低用量のキロサイドにアクラシノン(一般名アクラルビシン)、ノイトロジン(一般名レノグラスチム)を組み合わせたCAG療法が行われることも多いそうだ。
「この治療法がよいというはっきりしたエビデンス(科学的根拠)があるわけではないのです。骨髄異形成症候群の病態は多様で、患者さんもしばしば強力な治療に耐えることができない高齢者の方が多く、治療はすべての患者さんにとって同じではあり得ません。患者さんと病気の特性を考慮に入れた上で、それぞれの病態に適した治療法を選択することが大切なのです」と小川さん。そこで、治療方針を決める際に重要な目安になるのが、国際予後判定システム(IPPS)だという。
同じカテゴリーの最新記事
- 日本での新薬承認が待たれる 骨髄異形成症候群の最新薬物療法
- 骨髄異形成症候群(MDS)の正体を知ろう 高リスクの骨髄異形成症候群にはビダーザが決定打。今後の新薬承認に期待
- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切
- リスクに応じた治療戦略がカギ 骨髄異形成症候群の最新治療
- レブラミドやビダーザなどの新薬で治療成績は向上 新薬で白血病への移行をストップ!骨髄異形成症候群の最新治療
- 治療法がなかなかなかった難治性の病気に、延命への希望が生まれた 2種類の薬の登場により骨髄異形成症候群の治療は新時代へ!
- 大型新薬の登場で、薬物療法の選択肢が広がっている 完治も期待できるレブラミド。高リスクに有効な新薬も承認間近
- 早期に見つけるには年1回以上の血液検査を 「貧血」「出血傾向」「抗がん剤経験者」に要注意!
- あなたの骨髄、血液細胞は大丈夫ですか? 要注意は高齢、抗がん剤、放射線被曝


