進行は穏やかでも予後が極めて悪い場合もあるので、早期診断が大切 新薬が開発され、可能性が広がる皮膚T細胞リンパ腫の治療
治療方法の要である光線療法
では、治療の要ともいえる光線療法とは、どのような治療法なのか。
光線療法にはプーバ(PUVA)療法やナローバンドUVB療法がある。プーバ療法はオクソラレン(*)という薬を「塗る」か「飲む」か「入浴する」のいずれかの方法で体になじませてから紫外線をあてる。
外来で実施しやすいのはナローバンドUVB療法だ。これは、紫外線の発がん性の高い部分をカットした光線を用いる治療で、岡山大学で導入している照射装置では、週1~3回、1~3分程度当てるという簡便さが利点である。必ずしも入院の必要はないが、入院した場合だと、週5~6回行う。
「プーバ療法とナローバンドUVB療法の効果はほぼ同等といったところです。早期では皮膚表面だけ当てればよいのでナローバンドUVB療法を行い、病変が深部に達していてナローバンドUVB療法では効果が限定的と予想される場合、プーバ療法に切り替えることもあります」
ただし光線療法で気になるのは、やはり発がん性の問題。例えば、ナローバンドUVB療法では、発がん性の高い部分をカットした光線を用いてはいるが皮膚がんを発生させるという報告もある。しかしこれを回避すべく、光線治療装置も進化しているという。
「狭い範囲に強い光線を当てられるハンディタイプの機器が導入されてきています。小さな病変部分に数秒あてるだけでいいので照射時間が短縮でき、正常な周囲には当たらないため発がんリスクが減ります。これは大きなメリットです」
日本では保険適応になっていないが、チガソン(*)という内服薬を加えたプーバ療法を行うことがある。チガソンには皮膚を薄くするなどの副作用もあるが、免疫調整作用があり、併用によって光線療法の有効性が高まることから、診療ガイドラインでは併用療法も推奨されている。
| メトキサレンを塗る方法 | メトキサレンを飲む方法 | メトキサレ���を入れた 風呂に浸かる方法 |
| 薬を塗る手間がかかる。照射は塗ってから30分後に行うので、待ち時間が生じる。UVAは紫外線の一種であるため、当たった部分が日焼けする(日焼けするくらいまで当てなければ有効性がない)。そのため、「赤みは取れるけれども日焼けで肌が黒くなる」という副作用が出てくる | 飲み薬による治療は日焼けの影響も少なく効果も高い。メトキサレンは紫外線への感受性を高めるので、代謝の関係上、服用して2時間ほどしてから照射する。その後、直射日光に当たらないよう、日が暮れてから帰宅するなどの制約がある。吐き気で薬が飲めない人もいる | 湯をためた浴槽に液体のメトキサレンを入れ、10~15分浸かる。風呂の設備が必要で、衣服の着脱などで手間がかかる。風呂に浸かった後は、光線をあてるためにふらつく患者さんもおり、転倒の危険がある。照射後はもう1度シャワーで薬液を洗い流す。外来で実施するなら風呂の設備が必要 |
*オクソラレン=一般名メトキサレン
*チガソン=一般名エトレチナート
化学療法は腫瘍細胞の量を減らすのが目的
化学療法は通常のリンパ腫で行われるCHOP療法(*)がベースとなり、単剤でラステット(*)を用いることもある。
また、現在はあまり行われていない治療だが、脳のう腫瘍などに適応されている注射薬のニドラン(*)を塗り薬に転用した外用化学療法という方法もある。しかし現状では薬の管理の問題と保険の制約から、あまり実施されていない。
*CHOP療法=アドリアシン、オンコビン、エンドキサン、プレドニンを用いた多剤併用療法
*ラステット=一般名エトポシド
*ニドラン=一般名塩酸ニムスチン
新薬の登場や計画中の治験に期待
「皮膚リンパ腫は希少なものばかりで患者数が少ないため、治験が難しいこともあり、新薬開発が進まないといった深刻な問題があるのですが、最近やっと治療薬のレパートリーが増えました」
2011年9月にゾリンザ(*)という薬が発売されたのだ。菌状息肉症の盛り上がりや浸潤のある病変(局面)や潰瘍を伴い増殖する病変(腫瘤)、紅皮症(*)に対して効果が期待でき、新しい腫瘤の発生を予防し、痒かゆみも軽減させる。
「臨床試験では治療抵抗性の症例に対して、ゾリンザ単独で効果があったのは3割程度でしたので、光線療法、放射 線治療などとの併用が必要でしょう。長期の予後もまだわかりませんが、それでもこれまでまったく薬がなかったところに出てきたことは朗報です。ゾリンザという選択肢ができたのは大きな意味があるといえます」
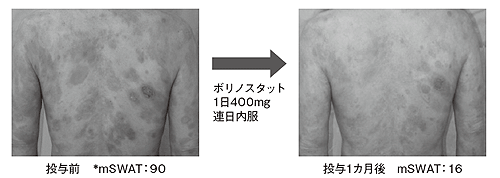
もう1つ新規薬剤としてはベキサロテン(一般名)というレチノイド系(ビタミンA誘導体)の薬の治験が進行中だ。欧米ではすでに使われており、ゾリンザとベキサロテンを併用した治療を有効とする報告もある。
他の薬剤治療には、インターフェロンγがある。海外で使われているインターフェロンαは日本では未承認で、現在、日本では1種類のインターフェロンγ製剤がある(ただし、自費診療)。
2012年5月ごろからインターフェロンγの治験が予定されており、その結果にも期待したい。
*ゾリンザ=一般名ボリノスタット
*紅皮症=紅斑が体表面積の80%以上に及ぶものをいう。病期でいえばT4
同じカテゴリーの最新記事
- 病勢をうまくコントロールして共存 原発マクログロブリン血症/リンパ形質細胞性リンパ腫(WM/LPL)の最新治療
- 希少がんだが病型が多い皮膚リンパ腫 なかでも圧倒的に多い「皮膚T細胞リンパ腫」の最新治療
- 再発・難治性の悪性リンパ腫のCAR-T細胞療法 キムリアに続き新薬が次々と登場!
- 古典的ホジキンリンパ腫に免疫チェックポイント阻害薬が承認 慎重な投与時期の検討が必要、重篤な合併症にも注意
- 悪性リンパ腫治療の最近の動向
- 血栓症リスクを知り、血液がんの治療中は症状に早く気づき受診を
- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切
- 病型ごとに治療の開発が進む B細胞性リンパ腫
- 小児がんの新薬開発で再発治療の充実を!


