リツキサンに続き、ゼヴァリン、トレアキシン登場で治療成績が向上 新薬の登場で悪性リンパ腫治療に光明が!
再発・難治性の患者さんに新薬登場
非ホジキンリンパ腫の治療は、CHOP療法にリツキサンを加えることによって、明らかに治療成績は向上し、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫のように、患者さんの生存期間の延長も見られるようになってきた。そういった意味で、非ホジキンリンパ腫治療において、リツキサンの登場は大きな意味を持つといえる。
ただ、リツキサンの効果にも人によっては限界があるようだ。渡辺さんによると「ろ胞性リンパ腫の場合、いったん寛解に入っても中には残念ながら再発する人もいる」という。
ろ胞性リンパ腫は、低悪性度で分裂増殖もゆっくりしている。従来の抗がん剤は、分裂速度の速い細胞に効果が高いので、ろ胞性リンパ腫のようながんは、抗がん剤だけでは比較的効きにくい。経過は緩慢でも、再発しやすく治癒の難しいリンパ腫なのである。
ここに登場したのがゼヴァリン(*)やフルダラ(*)、トレアキシン(*)といった新規抗がん剤だ。いずれも「再発または難治性の低悪性度B細胞非ホジキンリンパ腫およびマントル細胞リンパ腫」が適応だ。
なかでも、ゼヴァリンは全く新しい仕組みで作用する。ゼヴァリンも、B細胞のCD20を標的とする抗体なのだが、リツキサンとの大きな違いは、イットリウム-90という放射性同位元素を抱えている点だ。
ゼヴァリンはCD20に結合してβ線を放出する。つまり、体内でCD20に結合して集中的にがん化したB細胞に放射線を照射するのである。
「深部にあったり、血管の発達が悪く抗がん剤が到達しにくいがん細胞、CD20抗原が不均一にしか発現していないがん細胞を治療する上で、リツキサンより有利と考えられます」と、渡辺さんは語っている。
*ゼヴァリン=一般名イブリツモマブチウキセタン
*フルダラ=一般名フルダラビン
*トレアキシン=一般名ベンダムスチン
いかに長期奏効者を見分けるか
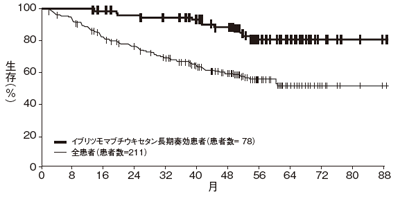
渡辺隆, 血液フロンティア2007;17:37-44より一部改変
渡辺さんによると、ここで重要なのは「ゼヴァリンが、長期にわたって効果がある人をいかに見分けるか」だという。実は、ゼヴァリンによる治療は全額自己負担だと、併用する薬剤費も含めて総額500万円程度と極めて高価なのだ。「一生再発せず根治するのであればそれでも許容できますが、1~2年で再発したのではあまりに負担が大きいです」と渡辺さんはいう。
これまでの海外で行われた4つの臨床試験でゼヴァリンの投与を受けた人の中で、1年以上病勢が進行しない長期にわたって効果が維持される人は211名中78名で37パーセントであった。これをいかに見分けるか。
渡辺さんによると「まだどのような患者さんに長く効果が現れるかを予測する方法ははっきりわかっていませんが、4つの臨床試験を合わせた分析では完全奏効する人と、病変の大きさが5センチより小さい人に勝算が高いという報告があります」ということだ。
低悪性度の再発に効果
ゼヴァリンは、白血球・血小板数の減少という副作用があるが、従来の抗がん剤と比べると、副作用も少ない。
一方、フルダラやトレアキシンは抗がん剤だが、フルダラは経口の抗がん剤で、脱毛や吐き気などの副作用がないこと、そしてろ胞性リンパ腫のような分裂の遅いがんにも効果があるのが大きな特徴だ。R-CHOP療法で再発したろ胞性リンパ腫の患者さんなどにリツキサンと併用すると、高い奏効率を示す。
一方、これよりさらに、「ろ胞性リンパ腫の再発に効果が高い」と渡辺さんが指摘するのが、2010年末に認可されたばかりのトレアキシンだ。
単独、あるいはリツキサンと併用して2日間点滴する。再発したろ胞性リンパ腫やマントル細胞リンパ腫を対象に、国内で行われた臨床試験では効果が認められている。
「日本人では結構吐き気が出るので、吐き気止めを十分に使う必要が出てきます。他の治療が効かない人には朗報です」と渡辺さんは語っている。
また、イノツズマブオゾガミシンは、CD22というB細胞の抗原を標的とする抗体で、カリケアマイシンという抗がん剤を抱えている。カリケアマイシンは、それを全身投与した場合には毒性が強い抗がん剤だが、イノツズマブオゾガミシンは抗原に結合して細胞内部に侵入し、抗がん剤を放つ。まさにピンポイントで抗がん剤を効かせるので「脱毛や強い嘔吐などの副作用は少ない」そうだ。ただし、肝障害や血小板減少が一過性に出現する
T細胞リンパ腫にも抗体治療薬
他にも、開発中の有望な治療薬は多い。たとえば、渡辺さんが期待するのがT細胞をターゲットとした抗体治療薬。T細胞は免疫の要の働きをしているため、これまでその働きを阻害する抗体治療薬はなかった。
ところが、開発中の抗体治療薬はCCR4という抗原を持つT細胞のみに作用し、「成人T細胞リンパ腫などこれまで治療が難しかったT細胞リンパ腫の治療に大きな期待」が寄せられている。
「悪性リンパ腫の場合、リツキサンなど新しい分子標的薬が出たといっても、慢性骨髄性白血病ほどよく治るようになったわけではありません。ろ胞性リンパ腫の再発では何をどういう順番で使うのか、またびまん性大細胞型B細胞リンパ腫はリツキサンを用いるようになってから再発が少なくなりましたが、それでも再発する人は、リツキサンが使えなかった化学療法だけの時代に再発した人より救援療法で治りにくいかもしれないのではなど、新たにクリアすべき問題もあります。
しかし、今後登場する薬も多いのでさらなる治療成績の向上が期待できます」と渡辺さんは語っている。
同じカテゴリーの最新記事
- 病勢をうまくコントロールして共存 原発マクログロブリン血症/リンパ形質細胞性リンパ腫(WM/LPL)の最新治療
- 希少がんだが病型が多い皮膚リンパ腫 なかでも圧倒的に多い「皮膚T細胞リンパ腫」の最新治療
- 再発・難治性の悪性リンパ腫のCAR-T細胞療法 キムリアに続き新薬が次々と登場!
- 古典的ホジキンリンパ腫に免疫チェックポイント阻害薬が承認 慎重な投与時期の検討が必要、重篤な合併症にも注意
- 悪性リンパ腫治療の最近の動向
- 血栓症リスクを知り、血液がんの治療中は症状に早く気づき受診を
- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切
- 病型ごとに治療の開発が進む B細胞性リンパ腫
- 小児がんの新薬開発で再発治療の充実を!


