従来のサルベージ療法に比べ、穏和で優れた効果を持つフルダラとゼヴァリン 2つの新薬で大きく変わる悪性リンパ腫
B細胞腫瘍の再発治療に新しい治療薬が登場
B細胞腫瘍の治療は、最近になってさらに大きな進歩を見せている。
再発した場合に使用できる薬として、2007年にフルダラ(一般名フルダラビン)、2008年にゼヴァリン(一般名イブリツモマブチウキセタン)が承認されたからである。これらの薬はどのような場面で使われるのだろうか。
「B細胞腫瘍は、前述のとおり、進行の速さによって、低悪性度リンパ腫と中高悪性度リンパ腫に分類されます。低悪性度であれば、R-CHOP療法で80~90パーセントは完全寛解(悪性の病巣がすべて消失したと考えられる状態)になります。中高悪性度の場合、完全寛解になる割合は、それより10~15ポイント低い程度です。がんの悪性度によって多少の違いはありますが、B細胞腫瘍であれば、過半数は完全寛解になるわけです」(鵜池さん)
完全寛解になっても、悪性化した細胞が完全になくなったとは限らない。そのまま再発しなければ治癒したことになるが、再発してくるケースが多いのだ。
「完全寛解になっても、低悪性度は9割程度再発します。中高悪性度では6~7割くらいです。低悪性度は進行が遅く、1度は薬がよく効くのですが、そのほとんどが再発してしまいます。低悪性度のほうが再発しにくいように思えますが、そうではないのです」(鵜池さん)
R-CHOP療法で完全寛解に至っても、そのうちの多くは再発してしまう。完全寛解から再発までの期間はさまざまだが、2~3年のことが多いそうだ。
「フルダラやゼヴァリンが登場する以前は、再発した場合には、R-CHOP療法より強い化学療法が行われてきました。サルベージ療法と呼ばれる、これまで使用していない抗がん剤の組み合わせによる多剤併用療法です」(鵜池さん)
サルベージ療法はうまくいけばもう1度完全寛解に持ち込めるが、この治療の副作用は大変強く、患者さんにとっては辛い治療になる。R-CHOP療法で抜けていた毛髪がようやく生えてきたのに、また抜けてしまう。吐き気も発熱もある、といった具合だ。うまく完全寛解に持ち��めたとしても、また再発する可能性が高く、再発までの期間も短くなるのが一般的だ。
「これまで苦労してきた再発後の治療は、フルダラやゼヴァリンが登場したことで、大きく変わりました。これらの薬は副作用が軽いのに加え、フルダラは内服薬なので外来治療が可能、ゼヴァリンはたった2回注射するだけなので治療期間が短いという特徴があります。サルベージ療法としての多剤併用療法に比べてはるかに楽な治療なのに、完全寛解になる率が高く、次の再発までの期間も長くなるのです」(鵜池さん)
悪性リンパ腫の治療は、この2つの新薬の登場で、大きく変わったのである。
中高悪性度の場合には幹細胞移植も考える
低悪性度の再発にはフルダラやゼヴァリンが使えるが、中高悪性度の再発は適応外である。そこで、中高悪性度は年齢、病期、全身状態などから判断する国際予後因子(IPI)によって、予後を推測し、それに応じた治療法を選択することになる。
「予後が悪いと判断できた場合、最初の完全寛解後、患者さんが65歳未満であれば、引き続き、造血幹細胞(赤血球・白血球・リンパ球など、血液細胞の供給源となる細胞)の自家移植(自分の幹細胞を採って凍結保存しておき、それを用いて移植をする方法)が行われるようになっています。現在、この治療の効果を確認するための臨床試験が進行中です」(鵜池さん)
国際予後因子が比較的よい場合には、最初の治療で完全寛解になったところで治療を中止。再発したらサルベージ療法を行い、完全寛解になった時点で自家移植を行うのが標準治療になっている。この治療は欧米で臨床試験が行われ、すでにエビデンス(根拠)があるという。
フルダラは内服薬なので外来治療が可能になる
さて、進歩が著しい低悪性度B細胞腫瘍の最新治療に話を進めることにしよう。フルダラは、体内に入ると細胞の中に入り込み、核の合成を阻害することで、がん化した細胞を死滅させる。その働きは他の多くの抗がん剤と同じだが、多くの抗がん剤が分裂期の細胞に効果を発揮するのに対し、フルダラは静止期の細胞に働きかける。そのため、進行の遅い低悪性度のB細胞腫瘍に効果を発揮するのである。
「フルダラは単独で使うよりも、リツキサンを併用するほうがよりよい効果を発揮します。また、経口薬なので、外来でも治療が可能です。5日間連続服用し、休薬期間をはさんで、1ヵ月後にまた5日連続で服用します。これを最大6コースまで繰り返します。つまり、外来治療が可能なのですが、治療期間は比較的長くなります」(鵜池さん)
副作用は、従来のサルベージ療法には比べものにならない。吐き気などの消化器症状が出ることがあるが、程度は軽い。問題になるのは、リツキサンと併用した場合、免疫抑制状態が起きることがある点だ。治療後数年間は、ウイルス感染や真菌感染に注意する必要があるという。
抗体と放射線の働きでがん化した細胞を攻撃
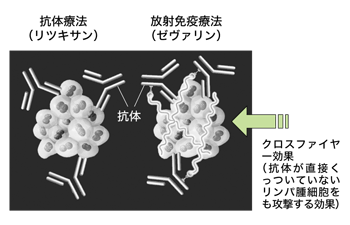
[ゼヴァリンによる抗腫瘍効果]
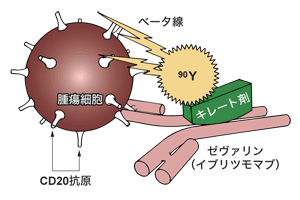
ゼヴァリン(注射液)はユニークな薬である。リツキサンのような抗体薬に、イットリウム90という放射性同位元素(放射能をもつ同位元素)を抱合させた構造になっている。抗体部分はリツキサンと同様に、B細胞腫瘍がもつ抗原、CD20をターゲットにして細胞に取りつく。そして、イットリウム90から出る放射線が悪性細胞を攻撃する。
「普通の放射線療法は体外から照射しますが、ゼヴァリンは体の中で悪性細胞に取りついて、放射線を照射します。この治療を放射免疫療法と呼ぶのですが、ゼヴァリンは日本で唯一の放射免疫療法剤です」(鵜池さん)
体の中に放射性物質を入れて大丈夫なのだろうか、と心配になる人もいるだろう。しかし、イットリウム90は半減期(放射性元素の半分が崩壊する期間)が64時間と短く、放射されるのがベータ線(放射線の一種)なので到達距離がきわめて短い。
そのため、主に悪性細胞だけを攻撃することになり、副作用はごく軽いのが特徴だ。脱毛や吐き気などで患者さんを苦しめることはない。気をつけなければならないのは血小板減少で、日本人の場合、投与後数週~8週の間に、ほとんどの患者さんに現れるという。必要に応じて輸血などで対処する必要がある場合もある。
また、ゼヴァリンは特殊な薬だけに、投与は慎重に行われる。投与前にイットリウム90の代わりにインジウム111という放射性同位元素を抱合させた抗体を注射し、体内のどこに集まるかを画像検査でチェックする。それがリンパ節に集まっていればいいが、骨髄や正常臓器に集まっていたら、危険な有害事象(副作用)が起こる可能性があるので、治療を中止しなければならない。
このため、ゼヴァリンによる治療を行うために、血液内科医、放射線科医、薬剤師が、そろって専門の研修を受ける必要がある。安全に治療を進めるために、このような措置がとられている。
「ゼヴァリンは検査、治療と、計2回の注射が必要ですが、それですべてが終了となります。患者さんにとって、実に楽な治療ですね」(鵜池さん)
フルダラとゼヴァリン、どちらがより優れているか
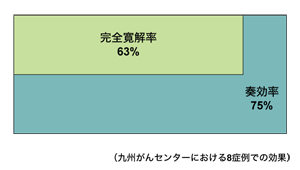
フルダラとゼヴァリンは、従来のサルベージ療法と比べ、優れた治療成績を残している。
「当院のゼヴァリンの治療経験では、再発患者さんの3分の2は完全寛解に入り、部分寛解まで入れると8割以上の人に効果がありました」(鵜池さん)
2つの新薬による治療はまだ始まったばかりなので、本当の実力がわかってくるのはこれからになるが、治療を受けた患者さんたちからは、「入院などの長期の治療が必要ない」「副作用が軽い」などの点が喜ばれているという。フルダラとゼヴァリンを比較して、どちらがより優れているか、という点については、現在、「ゼヴァリンVSリツキサン+フルダラ」という国際第3相臨床試験が進行中で数年後には結論が出る予定だ。
また、フルダラとゼヴァリンをどのような患者さんに使えばいいのか、という使い分けの方法も、今後明らかになっていくだろう。
同じカテゴリーの最新記事
- 病勢をうまくコントロールして共存 原発マクログロブリン血症/リンパ形質細胞性リンパ腫(WM/LPL)の最新治療
- 希少がんだが病型が多い皮膚リンパ腫 なかでも圧倒的に多い「皮膚T細胞リンパ腫」の最新治療
- 再発・難治性の悪性リンパ腫のCAR-T細胞療法 キムリアに続き新薬が次々と登場!
- 古典的ホジキンリンパ腫に免疫チェックポイント阻害薬が承認 慎重な投与時期の検討が必要、重篤な合併症にも注意
- 悪性リンパ腫治療の最近の動向
- 血栓症リスクを知り、血液がんの治療中は症状に早く気づき受診を
- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切
- 病型ごとに治療の開発が進む B細胞性リンパ腫
- 小児がんの新薬開発で再発治療の充実を!


