従来の薬では治らないと言われていた難治性のがんに力を発揮する 悪性リンパ腫の治療は新薬の登場で新しい時代を迎えた
たった1回の治療で約7割が完全寛解に
ゼヴァリンによる治療は、血液の副作用が遅れて出てくるという特徴がある。
「ふつうの抗がん剤治療だと、投与後10日ほどで、白血球や血小板の減少がもっとも強くなります。白血球数が下がりすぎると感染症の危険があるので、白血球数を上げる薬を使ったり、入院させたりします。また、血小板が下がりすぎると出血しやすくなりますので、血小板輸血が必要になる場合もあります。ゼヴァリンでも白血球や血小板は下がりますが、通常の抗がん剤に比べれば、投与からかなり後になって起きてきます。ただし、きちんと検査して確認していれば、白血球や血小板が低下したときでも、外来治療が可能です」
その他の副作用は比較的軽い。通常の抗がん剤治療では、脱毛、吐き気、手足のしびれなどがよく起こるが、ゼヴァリンによる治療では、こうした症状もほとんど現れない。副作用の強さはグレード1~4で表わされるが、ゼヴァリンの投与では、現れたとしてもグレード1~2程度の副作用だという。
この薬は治療回数も独特だ。多くの抗がん剤治療では、薬を繰り返し投与する。少なくても3~4コース、平均して6コース程度。中悪性度の悪性リンパ腫の初回治療では、8コースの治療が行われることもある。それに比べ、ゼヴァリンの治療はたった1回で終わりになる。
「患者さんにとって非常に楽な治療ですが、効果は優れています。日本で行われた治験では、すでにリツキサンやCHOP療法(エンドキサン、アドリアシン、オンコビン、プレドニゾロンの4剤併用療法)などの抗がん剤治療を受けて再発した低悪性度B細胞リンパ腫の患者さんと、これらの治療でよくならなかった難治性の患者さんが対象になっています。それでも、たった1回の治療で、67.5パーセントの人が完全寛解になるという結果が出ました」
完全寛解とは、画像検査で腫瘍がほぼ完全に消失したと判断される状態のこと。腫瘍は残っているが半分以下に縮小した場合を部分寛解といい、奏効率はここまで含めて求められる。この治験における奏効率は82.5パーセントだった。
「ゼヴァリンによる治療の特徴をわかりやすくまとめると、1回ですみ、副作用が少なく、効果が高い、ということになります。治療対象は再発または治療抵抗性の低悪性度B細胞リンパ腫とマントル細胞リンパ腫ですが、どちらも治りにくい病気で、初回治療を受けた後に多くの人が再発しています。こういう患者さんにとっては、まさに朗報と言えるでしょう」
ゼヴァリンは画期的な作用機序を持つ薬だが、その効果も画期的で、大きな期待が寄せられている。今後は、再発後だけでなく初回治療として用いたり、他のタイプの悪性リンパ腫に適応を広げる、といった進展も期待されているという。
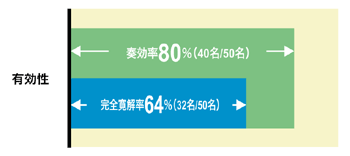
[ゼヴァリンによるRI標識抗体療法の効果]
| 解析例数 | 抗腫瘍効果(例数) | 奏効率(≧PR) 〔例数(%)〕 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 完全寛解(CR) | 部分寛解(PR) | 安定(SD) | 増悪(PD) | |||
| 低悪性度B細胞性 非ホジキンリンパ腫 | 46 | 14 | 16 | 14 | 2 | 30(65) |
| マントル細胞リンパ腫 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | ―― |
内服薬のフルダラは外来治療に適している
新しく認可されるがんの治療薬は分子標的薬が多いが、フルダラは化学療法剤で、従来の抗がん剤と同じように殺細胞作用を持つタイプの薬だ。ただ、その効果はこれまでの抗がん剤とは異なり、従来あった化学療法の限界を打ち破る抗がん剤として期待されている。
「フルダラが新しいのは、細胞分裂の盛んな中悪性度や高悪性度のがん細胞だけでなく、細胞分裂がゆるやかな低悪性度のがんにも効果がある点です。通常の抗がん剤の多くは、細胞が分裂期に入ったときに作用しますが、フルダラは分裂期に入っていない静止期の細胞に対しても、効果を発揮します。そのため、低悪性度リンパ系腫瘍に効くだろうということで開発されたのですが、まさにその通りだったのです」
フルダラは内服薬なので、外来治療を行いやすいという長所も持っている。もともと注射薬として先に開発された薬だが、悪性リンパ腫の薬として我が国で開発する段階で、外来治療が行いやすいように内服薬での開発にしたのだという。
「飲み薬のフルダラで悪性リンパ腫の治療に最初に成功したのは日本で、その治験データは世界的に評価されています」
フルダラの治療対象となるのは、再発または難治性の低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫とマントル細胞リンパ腫だ。これらの悪性リンパ腫には、初回治療として、リツキサンとCHOP療法を組み合わせた「R-CHOP療法」が行われている。古くから行われてきたCHOP療法にリツキサンが加わることで、治療成績は明らかに向上してきた。しかし、それで治癒しているのかというと、必ずしもそうではないのだ。
「以前は、R-CHOP療法で治療して再発したら、もっと強い薬を使うしかありませんでした。そのため、副作用が大変でしたが、現在はフルダラとゼヴァリンがあるので、これらを使えます。どちらも副作用として白血球減少が起こりますが、脱毛、手足のしびれ、便秘などが起こるCHOP療法と比べると、ずっと楽ですからね」
フルダラやゼヴァリンの登場は、副作用の面でも大きな改革だったのだ。
抗がん剤治療を受けた気がしない
小椋さんは、リツキサンとフルダラの併用療法を、発売前の治験として8人の患者さんに行ってきた。全員が低悪性度B細胞リンパ腫の初回治療としてR-CHOP療法を受けていったんよくなったものの、再発した人たちだ。結果は、8人中6人が完全寛解に入った。
「患者さんたちは、最初に受けたR-CHOP療法に比べてすごく楽な治療法で、雲泥の差がある、とおっしゃっていました。患者さんの半数は女性でしたが、髪が抜けないのがうれしかった、ともおっしゃっていました。R-CHOP療法のときに経験した副作用がないのに、腫瘍が消えていくのが、患者さんたちにはうれしい驚きだったようです」
ゼヴァリンに関しては、治験で8人の患者さんに投与している。やはり、R-CHOP療法を受けて再発した人がほとんどだった。
「ゼヴァリンは、治療しているときにはまったく副作用が出ません。そのため、抗がん剤治療をしている気がしないと言われました。投与時は(治験ということもあって)入院で行いましたが、8人中7人は再入院することなく外来で治療を続けました。腫瘍が消えた人が8人中5~6人。ある患者さんは、『こんなにいい治療法なんだから、もっと広まるといいですね』と話していました」
ゼヴァリンを使うには、放射性同位元素を抗体部分に結合させる調剤作業を、それぞれの医療機関で行う必要がある。また放射線を出す薬なので、放射線の取扱いに習熟していることも大切だ。そこで、日本アイソトープ協会の講習を受けた施設でないと、ゼヴァリンは投与できないことになっている。そうしたこともあって、ゼヴァリンによる治療を行える医療機関は、現在のところ非常に限られている。ただし、これは順次増えていく予定だ。
また、ゼヴァリンは特殊な薬なので、治療を受ける患者さんにも心得ておいてほしいことがある。治療前に十分な説明を受け、いったん受けると決めたら重大な理由無く変更しないことだ。なぜなら、イットリウム90の半減期は64時間なので、ゼヴァリンは保存しておくことができない。いったん製造したら、決められた日に投与しなければ、そのゼヴァリンは破棄することになるのである。
「治療を受けると決まって治療日程が決まったら、予定の日に確実に投与できるようにしてください。こうした点が、普通の薬とはまったく違います」
ゼヴァリンは注文が入ってからオランダとフランスの工場で放射性同位元素の生産が始まり、日本に空輸されて製剤化されるのだという。気楽にキャンセルできる治療でないことは、よく理解しておきたい。
同じカテゴリーの最新記事
- 病勢をうまくコントロールして共存 原発マクログロブリン血症/リンパ形質細胞性リンパ腫(WM/LPL)の最新治療
- 希少がんだが病型が多い皮膚リンパ腫 なかでも圧倒的に多い「皮膚T細胞リンパ腫」の最新治療
- 再発・難治性の悪性リンパ腫のCAR-T細胞療法 キムリアに続き新薬が次々と登場!
- 古典的ホジキンリンパ腫に免疫チェックポイント阻害薬が承認 慎重な投与時期の検討が必要、重篤な合併症にも注意
- 悪性リンパ腫治療の最近の動向
- 血栓症リスクを知り、血液がんの治療中は症状に早く気づき受診を
- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切
- 病型ごとに治療の開発が進む B細胞性リンパ腫
- 小児がんの新薬開発で再発治療の充実を!


