進行別 がん標準治療 分子標的薬の出現で大きく飛躍した悪性リンパ腫の治療法
治療方針の決定に重要な種類と病期
悪性リンパ腫は、下の円グラフのようにがん化したリンパ球の種類や遺伝子の異常によって多くの種類に分けられます。しかし、古くからホジキンリンパ腫と非ホジキンリンパ腫にわけて考えられてきました。
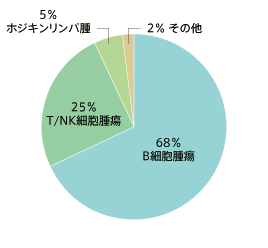
堀田さんによると、ホジキンリンパ腫の場合は首のリンパ節から脇の下のリンパ節、脾臓というように連続して順番に病巣が広がっていくのが特徴です。これを「接続性の進展」といいます。8割方はリンパ節を中心に腫れていくそうです。この病巣の広がり方、つまり病期が、治療方針を決める重要な要因になります。
一方、非ホジキンリンパ腫の場合は、病巣の進展は接続性とは限らず、飛び離れたところにポンと出たり、また約半分がリンパ節以外から出てくるのが特徴です。したがって、ホジキンリンパ腫とは治療の組み立て方が異なります。欧米では悪性リンパ腫の3分の1がホジキンリンパ腫ですが、日本人の場合、圧倒的に非ホジキンリンパ腫が多く、ホジキンリンパ腫は10パーセント足らずだそうです。
非ホジキンリンパ腫が中高年に多いのに対し、ホジキンリンパ腫は若い人にも多く、20代から30代と60代に2つのピークがあります。若い人に縦隔の巨大腫瘤が多いといいます。
ホジキンリンパ腫の治療
4種類の抗がん剤を組み合わせたABVD療法
病理学的(顕微鏡で見たがん細胞の形の違い)には、4つのタイプに分けられますが、基本的には病期、つまりがんの広がりの状態で治療方針が決定されます。
簡単にいうと、1期は右の首のリンパ節だけ、あるいは左の脇の下だけなど、1つの領域のリンパ節にがんが止まっている場合。領域が1つならば、リンパ節が2個腫れていても1期で。また、リンパ節以外の臓器に限局したリンパ腫も1期です。これが、2つの領域に及び、その領域が横隔膜をまたがない場合が2期。横隔膜をはさんで上下にまたがるリンパ節領域やリンパ組織に及ぶと3期になります。4期は、骨髄や肝臓などリンパ節以外の臓器に遠隔転移を起こしているケースです。
治療は、限局型か否かによって、異なります。限局型には1期と2期の一部が含まれます。堀田さん���よると「放射線を照射するときに、1つの照射野におさまるものが、限局型になる」そうです。ですから、2つの領域に及んでいても、近くのリンパ節領域で一緒に放射線を照射できれば、限局型になるのです。
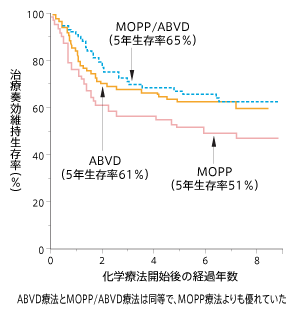
ホジキン病の限局型の場合、以前は放射線治療が中心でしたが、「今は短期間抗がん剤で化学療法を行い、そのあとで局所に放射線を照射するのが標準的」だそうです。ただし、縦隔(左右の肺の間の部位)にもリンパ節があり、ホジキン病はここに大きなコブを作ることがあります。この場合は、化学療法で十分にがんを叩き、ダメ押しの形で放射線治療を行います。つまり、化学療法を主に放射線を補助的に使うわけです。
一方、がんの進展期、すなわち病期が3期から4期になると、化学療法が中心になります。いずれの場合も、アドリアシン(一般名ドキソルビシン)、ブレオ(一般名ブレオマイシン)、エクザール(一般名ビンブラスチン)、ダカルバジン(一般名も同じ)という4種類の抗がん剤を組み合わせた併用療法(ABVD療法)が、標準的な治療法です。進展期に化学療法のみを行う場合は、6~8コース、限局型で放射線を組み合わせて行う場合は、化学療法を4コース行って放射線を照射するのが標準的です。
幸い、ホジキンリンパ腫はがんの中では治りやすいほうに入ります。堀田さんによると「限局期にきちんと治療を行えば、8割の人が再発しないで長期に生存しています。進行期でも6割ぐらいの人は長期に生存している」そうです。むしろ、ホジキンリンパ腫についてはすでに治療法はある程度完成。治療は行き着くところまで行っているので、今後画期的治療法が出てこない限り、治療成績の向上は難しいといわれています。
| 1期 | 1つのリンパ節領域(たとえば頸部とか鼠径部など)、またはリンパ組織(扁桃腺、脾臓、胸腺など)に病変がとどまっている場合。リンパ節以外の臓器の限局的なリンパ腫の病変も1期 |
|---|---|
| 2期 | 横隔膜を境界として、その上または下いずれか一方に限局した2つ以上のリンパ節領域、リンパ組織の病変。 |
| 3期 | 横隔膜の両側に及ぶリンパ節領域またはリンパ組織の病変。 |
| 4期 | リンパ節以外の臓器への広汎な浸潤。たとえば、骨髄、肝臓などの臓器に病変がある場合は4期。 |
| E:リンパ節以外の臓器の(限局した)病変がある場合“E”とつける。 B:継続または繰り返す38℃以上の原因不明の発熱、寝汗、6カ月以内での10%以上の体重減少、などのどれかの症状があるときは“B”とつける。 X:巨大な腫瘤があるとき。最大径が10cm以上または胸部レントゲン写真で胸椎の5番、6番の高さでの胸郭(胸の幅)の1/3以上の胸腔内のリンパ腫病変を巨大腫瘤とする。 | |
ホジキンリンパ腫の治療と副作用
現在、ホジキンリンパ腫の化学療法はABVD療法が標準治療です。その前は、MOPP療法が一般に行われていました。これは、ナイトロジェンマスタードとオンコビン(一般名ビンクリスチン)、プレドニゾロン、ナツラン(一般名プロカルバジン)を組み合わせた治療法です。日本ではナイトロジェンマスタードは認可されていないので、代わりにエンドキサンが使われていました。
堀田さんによると、ABVD療法はMOPP療法が効かない人や治療後再発した人を対象に開発された療法だそうです。ところが、ABVD療法のほうが治癒率が高く、副作用が少ないというので、こちらが新たな標準治療となったそうです。
「治癒を目指してホジキン病の治療を行った場合、問題になるのが晩期毒性でした。その代表が不妊と白血病などの2次発がん(治療によって発生するがん)だったのです」と堀田さんは語っています。ABVD療法のほうが、こうした毒性が少なく、不妊率も2次発がんの比率も低下したそうです。
一方、放射線治療を行うと、急性期には多かれ少なかれ食道炎や皮膚炎を起こしますが、これは一時的なもの。問題は、唾液の分泌低下や2次がんの発生など数年後に発生する遅発性の有害反応です。これを防ぐためには、できるだけ範囲をしぼって放射線を照射することが大切です。化学療法をまず行って、がんを縮小させ、限局した部位に放射線を照射することは、こうした副作用の緩和にも効果があるのです。
同じカテゴリーの最新記事
- 病勢をうまくコントロールして共存 原発マクログロブリン血症/リンパ形質細胞性リンパ腫(WM/LPL)の最新治療
- 希少がんだが病型が多い皮膚リンパ腫 なかでも圧倒的に多い「皮膚T細胞リンパ腫」の最新治療
- 再発・難治性の悪性リンパ腫のCAR-T細胞療法 キムリアに続き新薬が次々と登場!
- 古典的ホジキンリンパ腫に免疫チェックポイント阻害薬が承認 慎重な投与時期の検討が必要、重篤な合併症にも注意
- 悪性リンパ腫治療の最近の動向
- 血栓症リスクを知り、血液がんの治療中は症状に早く気づき受診を
- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切
- 病型ごとに治療の開発が進む B細胞性リンパ腫
- 小児がんの新薬開発で再発治療の充実を!


