抗腫瘍効果が大きく、副作用が少ないレブラミドにより治療成績が大きく向上 患者さんに朗報!新薬の登場で治療の手だてが増えた多発性骨髄腫治療
新薬登場で治療成績が大きく変わった
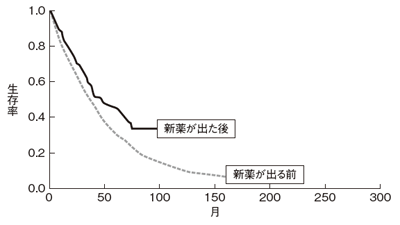
[多発性骨髄腫に対するレナリドミドの効果(無増悪生存率)]
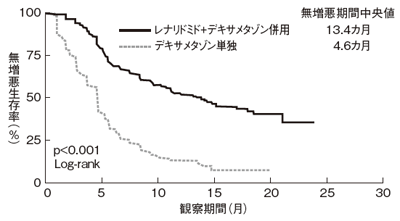
●ベルケイド
がん細胞の増殖を抑える物質が長時間分解されないようにする作用を持っており、近年、難治性の多発性骨髄腫に対する有効性が数多く報告されています。
●サレド
胎児に対する催奇形性のために60年代に使用中止になった薬剤ですが、がん細胞に栄養を送る血管をつくらせないようにする効果があり、多発性骨髄腫の治療薬として08年に承認されました。
●レブラミド
薬剤の重要性から、申請から異例の短期間で承認された多発性骨髄腫の治療薬です。がん細胞を死滅させたり、がん細胞に栄養を与える血管をつくらせないようにする、がん細胞を攻撃する免疫細胞を活性化するなど、様々な作用があります。
「レブラミドはサレドに似た分子構造をしていますが、抗腫瘍効果はサレドに比べはるかに高く、副作用はずっと少ないという特徴があります」
再発・難治性の多発性骨髄腫患者を対象とした海外の2つの大規模試験において、目を引く治療成績が出ました。
レブラミドとデキサメタゾン(一般名)という副腎皮質ホルモンとの併用で、それまでよく用いられていたデキサメタゾン単独療法より、奏効率では約60パーセント対約22パーセント、病気が悪化しない期間をみると、約13カ月対約4カ月で3倍、全生存期間では38カ月対約31カ月と、いずれもレブラミドを用いたほうが、効果が高かったのです。
また、レブラミドとサレドを比較した臨床試験でも、レブラミドを用いたほうが、治療成績がいいという結果が出ています。
完全奏効率(CR)は、レブラミド+デキサメタゾンが14パーセントだったのに対し、サレド+デキサメタゾンは6パーセント。また、良好な部分奏効率(VGPR)は、21パーセント対9パーセントと、いずれもレブラミドはサレドを上回る効果が出ています。
「治療の初期の段階で、いかに骨髄腫細胞を減らすかが重���です。完全奏効を目指すのがベストですが、少なくとも良好な部分奏効を得ることが大切です」
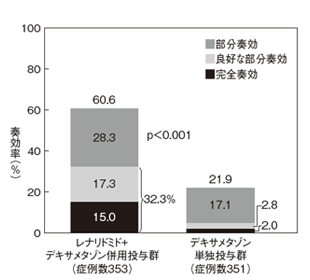
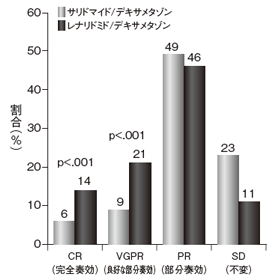
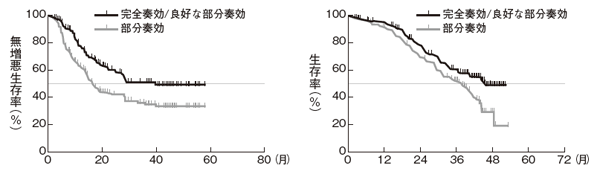
新薬はそれぞれ副作用も異なる
| 血液 | 神経 | 消化器 | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| サリドマイド | 血球減少 血栓症 | 末梢神経障害 鎮静 | 便秘・吐き気 | 発疹 |
| レナリドミド | 血球減少 血栓症 | 倦怠感 | 吐き気 | 感染症 |
| ボルテゾミブ | 血球減少 | 末梢神経障害 | 便秘・下痢 | ウイルス感染症 (帯状疱疹) 発熱 肺炎 |
では、以上の3薬はどう使い分けるのでしょうか。
「欧米からは初回の治療で3剤を用い、すぐれた治療成績が報告されています。しかし日本の保険承認では、現状ではいずれも再発・難治性の場合のみでしか認められていません。それらの事情とそれぞれ出やすい副作用などを勘案して薬剤を決めることが多いです」
いくつかの例をあげましょう。「たとえば再発・難治性のなかで、腎機能が低下している人は、ベルケイドを選択するケースが多いでしょう。というのも、レブラミドは腎臓から排泄されるため、腎機能の低下した患者さんでは正常の患者さんに比べて、体内でのレブラミドの濃度が高いままになる時間が長いので、副作用が出やすくなるからです」
ただしその場合、用量を調節するそうです。
一方、ベルケイドは手足がピリピリしたりチクチクして痛む末梢神経障害が患者さんの6~7割に現れるといいます。また、便秘や下痢などの症状も現れやすいことが報告されています。したがって、「胃や大腸などの疾患があったり、末梢神経障害が出ては困る高齢者では、便秘や末梢神経障害のリスクがほとんどないレブラミドがずっと使いやすいのです」と末永さんは話しています。
再発しても新薬を組み合わせた治療が可能に
再発しても新たな薬剤が出たことで、治療選択も広がってきました。とくに昨年レブラミドが多発性骨髄腫の治療に加わったことで、再発治療は大きく変わりました。
たとえば、初期治療などで、自己末梢血幹細胞移植のできる人では、前治療として高用量のデキサメタゾンを使い、ベルケイド+デキサメタゾンを投与して末梢血を採取、移植することが多いそうです。しかし残念ながら、その後再発してしまった場合には、まず抗腫瘍効果の高いレブラミドを選択。レブラミドにデキサメタゾンを加えた治療を行うことが多いと末永さんは説明します。
一方、移植ができない患者さんに対しては、MP療法を行い、効果があまり見られない場合には、サレドやベルケイドを併用する治療を行います。しかし、そういった治療を行っても再発した場合には、患者さんの全身状態などを考慮した上で、レブラミドを選択。レブラミドにデキサメタゾンを併用した治療を行っているそうです。
このように、レブラミドが多発性骨髄腫の治療に加わったことで、再発治療も大きく変わってきたのです。
しかし、今後の課題もあります。それは欧米では初期治療から3剤を用いた治療ができますが、日本では再発や難治性の場合にしか使うことができないことです。
「欧米のように、初期治療の段階から、新薬を使えるようになれば、今後治療成績はもっと上がるのではないでしょうか」
多発性骨髄腫治療の今後を、末永さんはこう語っています。


