多岐にわたる多発性骨髄腫の症状と、その診断法とは 早期発見・正確な診断で患者さん1人ひとりに合った治療を!
多彩な症状。診断をしっかりつける
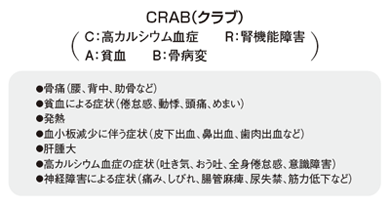
[検査で確認する内容]
| 種 類 | 確認する内容 |
|---|---|
| 尿検査 | 尿中の異常タンパクの有無 |
| 血液検査 | ●血液細胞(赤血球・白血球・血小板の数) ●Mタンパク、それ以外のタンパク、抗体の量や型 ●カルシウム量 ●肝臓や腎臓などの機能 |
| 骨髄検査 | 骨髄腫細胞の有無や割合 |
| 画像検査 | 骨の状態(骨折の有無、骨のもろさ) |
多発性骨髄腫は病状がさまざまで個人差が大きい。つまり、1人ひとりの患者さんに合った治療をすることが必要だが、そのためにも診断をしっかりつけることが大切だ。
では、多発性骨髄腫の診断は具体的にどうつけるのか、見てみよう。
「多発性骨髄腫の主要な症状である高カルシウム血症(C)腎機能障害(R)、貧血(A)、骨病変(B)は、CRABと総称されますが、このCRAB症状の有無が1つの目安となります。腰痛があって貧血がある、骨折していて腎臓が悪いといったところから、多発性骨髄腫を疑う場合が多いですね。
疑いを持ったら、免疫グロブリンを調べます。血液中に同一の免疫グロブリン(Mタンパク)が大量にあったら、まず間違いありません」
くわしい診断基準になっているのは、2003年に国際骨髄腫ワーキング・グループ(IMWG)が提唱した分類。血中のMタンパク量、骨髄腫細胞が骨髄に占める割合、臓器障害の有無、がん細胞の塊の有無により分類する。
最も初期的なのは「意義不明の単クローン性ガンマグロブリン血症(MGUS、通称エムガス)」。簡単にいうと「機能しないMタンパクが増えている状態」。すべての多発性骨髄腫はエムガスの状態を経て発症するといわれ、治療は不要。経過観察しても5年、7年、10年と安定していることが多い。
次の段階の「無症候性骨髄腫」は別名「くすぶり型」。Mタンパクも骨髄中のがん細胞も多いが、症状も臓器障害もあまりない。この段階で治療を開始したほうがいいという医師がいる一方で、経過観察だけでいいという医師もいる過渡期的な段階だという。
そして「症候性骨髄腫」。この段階に進行したら、治療を開始することが多い。ただし、この分類では臓器障害が重視されているため、先に説明したCRAB症状が一定以上の数値を示していたら、治療を開始することが多い。
このほか、骨髄腫なのにMタンパクが検出されない「非分泌型」、骨に1カ所だけ病変ができる「骨の形質細胞種」などは区別して分類される。
| 種 類 | Mタンパク | 骨髄腫細胞 | 特 徴 |
|---|---|---|---|
| 意義不明の単クローン性 ガンマグロブリン血症(MGUS) | 3g/dL未満 | 10%未満 | 機能しないMタンパクが増えているが、症状はない。治療は不要で経過観察 |
| 無症候性骨髄腫 (くすぶり型) | 3g/dL以上 | 10%以上 | Mタンパク、骨髄腫細胞がみられるが、症状も臓器障害もあまりない |
| 症候性骨髄腫 | あり | あり | Mタンパク、骨髄腫細胞の増加とともに臓器障害*による症状がみられ、治療を要する |
| 種 類 | Mタンパク | 骨髄腫細胞 | 特 徴 |
|---|---|---|---|
| 非分泌型骨髄腫 | - | 10%以上 | Mタンパクは見られないが、症候性骨髄腫と同様の症状が現れる |
| 骨の形質細胞腫 | ± | なし | 骨の1カ所に骨髄腫細胞の塊ができ、一部は症候性骨髄腫に進行する |
| 髄外性形質細胞腫 | ± | なし | 骨以外の場所(口腔、鼻咽頭など)に骨髄腫の塊ができ、一部は症候性骨髄腫に進行する |
| 形質細胞性白血病 | + | あり | 血液中に骨髄腫細胞が存在し、症候性骨髄腫と同様の症状がある |
ISS分類法とリスク分類で正確に診断
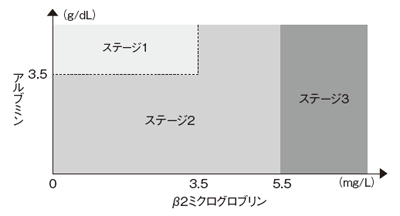
さらに、鈴木さんは言う。
「IMWGは2005年、世界中の多発性骨髄腫患者約1万8000人のデータをもとに、病気の進行度(ステージ)を決定する基準『ISS分類』を発表しました。全身状態を現す血清アルブミンと、腫瘍細胞の出すタンパク質β2ミクログロブリンという2つの数値で病期を1~3に分類しますが、今後の病気の経過や治療の時期を予測するのにかなりよい分類です。
これにリスク分類を加えると、多発性骨髄腫のタイプはより正確に診断できます。リスク分類では、骨髄腫細胞の染色体の構造によってハイリスク群(25パーセント)と標準リスク群(75パーセント)に分け、病状を診断するのですが、こちらも非常に精度の高いものです」
最近は病気のメカニズムがかなり解明され、病気を抑えるメカニズムもわかってきているという。正確な診断に従い、適切な治療を受けることは、とても重要だ。
多発性骨髄腫は慢性病。長く元気に生きよう
多発性骨髄腫の治療は長く決め手がなかった。造血幹細胞の移植が登場したものの、移植は体へのダメージも大きく、治療には覚悟が必要だった。これが「新3薬」と呼ばれるベルケイ ド(*)、サリドマイド(*)、レブラミド(*) の登場で激変する。5年ほど前のことだ。生活の質(QOL)を保ちながら生存期間を延ばし、必要に迫られたときに体調と相談して移植に踏み切る、という治療が可能になったのだ。
「今では10年、12年と生存可能になり、ゾメタ(*)など骨病変の異常に効果的な薬もできて、昔のように骨折で寝たきりになったり、痛さに苦しんだりすることも減りました。多発性骨髄腫は慢性病になったということです。早い時期に治癒を目指して強い治療をするより、QOLを大事にして、長く元気に日常生活を送ることが大切だと思います。
その意味でも、早く診断をつけ、必要な時期に必要な治療を受けることです。病状が進んで骨がぼろぼろになったり、腎不全で透析を受けるようになったりすると、QOLが落ちるだけでなく、治療を効果的に受けることも難しくなります」
多発性骨髄腫の検査は血液検査などのほか、骨髄に針を刺して骨髄液をとる骨髄穿刺が行われるが、穿刺の必要のない遺伝子診断も確立される可能性があるとのこと。多発性骨髄腫はあらゆる点で、絶望しなくてよい病気になりつつある。
*ベルケイド=一般名ボルテゾミブ
*サリドマイド=一般名同じ
*レブラミド=一般名レナリドミド
*ゾメタ=一般名ゾレドロン酸


