大きく変わりつつある多発性骨髄腫の最新治療 注目されるサリドマイド、レブラミド、ベルケイドの新御三家の力
サリドマイドは難治再発例の救世主
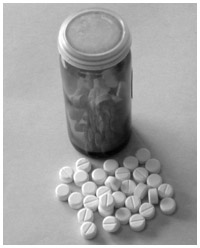
では、再発例や難治例では、痛み対策などの対症療法以外に、どんな手が打てるだろうか。現在注目されているのが、今までの抗がん剤やステロイド剤とは違う3つの薬だ。
「ひとつがサリドマイド、ひとつがサリドマイド誘導体(サリドマイドをベースにして作り出された薬)のレブラミド(一般名レナリドミド)、もうひとつが、タンパク質分解酵素プロテアソームの働きを阻害するベルケイド(一般名ボルテゾミブ)で、いずれも再発、もしくは治療抵抗性の難治性骨髄腫に有効なことが明らかになっています」(服部さん)
このうち、国内外で最も多く検討されているのはサリドマイドだ。
ご存知のように、20世紀半ばに手足欠損という深刻な障害を生み出した大規模薬害で知られる薬だ。しかし、今日の欧米で、難治性・再発性の骨髄腫には第1選択だ。
事実、世界で数百もの臨床試験が行われ、投与法の明確な論文だけでも42ある。難治例、再発例の30パーセントでMタンパクが減る有効性が認められ、デカドロンや抗がん剤を併用すると、有効性が50パーセント程度に上がるといわれている。
投与量も明確になってきた。
「欧米人で1日400ミリグラム程度、日本人なら100~200ミリグラムが目安と考えられています。ただし、長く飲み続けると、手足のしびれや麻痺などの抹消神経障害が出ます。ほかに静脈血栓症、眠気や便秘といった副作用も起こります」(服部さん)
| 発表指数 | 1日投与量 (mg/日) | 症例数 | 反応率 (MR+PR) | 部分 寛解率 | グレード3以上の有害事象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自治医大 | 100~200 | 26 | 38% | 12% | - |
| 慶応義塾大学 | 100~400 | 37 | 43% | 31% | 好中球減少症、末梢神経障害 間質性肺炎、肺高血圧症 |
| 日本医大 | 100~400 | 11 | 36% | - | 眠気、肝機能障害 |
| 自治医大 大宮医療センター | 100 | 15 | 60% | 33% | - |
| 虎の門病院 | 100~300 | 24 | 58% | - | 頻脈、好中球減少症 皮疹、末梢神経障害、眩暈 |
| 福岡大 | ≧200 | 12 | 80% | - | 水分貯留 |
| 東京女子医大 | 100~300 | 20 | 50% | 25% | 眠気、好中球減少症 便秘、皮疹 |
| 聖隷浜松病院 | 50~200 | 24 | - | 33% | 末梢神経障害 |
サリドマイドさらに初期治療へ適応拡大
サリドマイドの多発性骨髄腫に対する有効性が知られるにつれ、日本では医師による個人輸入が急増。2003年には53万錠にも達した。
しかし、安全管理に対する危機感が強まり、2004年には日本血液臨床学会と厚労省が「多発性骨髄腫に対するサリドマイドの適正使用ガイドライン」を発表。倫理委員会の承認や認定施設での使用、使用患者の登録などが定められているが、現在はこれをどう徹底していくかが重要課題となっている。
しかし、ガイドラインが示されたことで、サリドマイドを多発性骨髄腫に広く使う素地が、日本にもできたようだ。
「最近の傾向としては、サリドマイドの初期治療への適応拡大が挙げられます」(服部さん)
自家移植前の初期治療にサリドマイドとデキサメタゾンを併用し、VAD療法より効果があるとした報告、同じく自家移植前にサリドマイドやベルケイドを使い、反応がいいうえに造血幹細胞もちゃんととれたとする報告、高齢者の初期治療としてMP療法にサリドマイドを追加したところ、生存期間も改善したとする報告など、有効性を示す報告が多数行われている。
少量投与で再発予防も。新規薬剤の動向に注目!
レブラミドはそのサリドマイドをベースに開発された「サリドマイドの誘導体」で、サリドマイドと同じ量を使うと、数千倍の抗骨髄腫作用があるとされている。「血球減少という副作用がありますが、昨年、アメリカとヨーロッパで大規模な第3相試験が行われ、どちらも難治例にデキサメタゾンと併用したところ、部分寛解は60パーセントを超えています。日本でももう治験が始まっていい頃ですが、まだそういった話は聞きません」(服部さん)
ベルケイドも、難治例に有効だ。サリドマイドの効かなかった症例に効くとか、13番染色体が欠失しているケースでも反応がいいといった報告もあり、初期治療に使うことで、完全寛解への導入率が非常に上がったとの報告もある。
ベルケイドとデキサメタゾンの比較併用試験(第3相試験)の国際共同研究では、完全寛解率が38パーセントに達している。
「ただ、痺れ、血小板の減少、胃腸症状などが副作用のほか、日本人がこの薬を使うと、なぜか呼吸器障害が頻発するので、注意が必要です。患者さん自身も気をつけ、おかしいと思ったらすぐ医師に告げるようにしてください」(服部さん)
こうした新規薬剤を少量投与することで、維持療法への可能性も開けるのではないかという。
「実際に移植後3カ月たってもMタンパクの残る患者さんに飲んでいただいていますが、今のところ最長で4年弱、サリドマイドを飲みながら会社におつとめされている患者さんもいます」(服部さん)
多発性骨髄腫の最新治療はおよそこのようなものであるが、新規薬剤の登場は大きな事件であり、骨髄腫の標準治療は向こう2~3年の間に根本的に変わる可能性がある。患者の皆さんもその動向を、ぜひ注意深く見守っていただきたい。


