渡辺亨チームが医療サポートする:多発性骨髄腫編
ステージ3。年齢と全身状態から「VAD療法+自家移植」を選択
| 関根秀雄さんの経過 | |
| 2004年 8月20日 | 激しい腰痛で近くの整形外科を受診 |
| 8月21日 | 市民病院を受診。血液検査の結果、多発性骨髄腫の疑い |
| 8月24日 | がんセンターの血液内科を受診。多発性骨髄腫と確定診断 |
| 8月25日 | VAD療法と骨病変の治療を開始 |
| 10月30日 | VAD療法を終了 |
| 11月17日 | 自家末梢血幹細胞採取のためのエンドキサン大量療法を開始 |
3期の多発性骨髄腫と診断された関根秀雄さん(62歳)は、骨病変や高カルシウム血症が致命的な問題に結びつく危険性があるとして、緊急入院となった。
治療はVAD療法という寛解導入に加え、大量化学療法と自家末梢血幹細胞移植が行われる一方、骨病変への放射線照射とビスフォスフォネート製剤による治療も行われている。
まもなく骨痛も止まり職場に復帰することもできたが……。
医師は「すぐに入院したほうがいい」と
「入院が必要なのでしょうか?……いつぐらいから?」
Hがんセンター血液内科の三木和雄医師から「多発性骨髄腫」との診断を受けた関根秀雄さん(62歳)はこう聞いた。
そのとき彼は、「イタタター」と顔もゆがめた。全身あちらこちらに引きちぎられるような痛さが走ったからだった。医師はこう答えている。
「だいぶ心配な状態のようですね。さいわい現在はベッドが1つ空いています。今日はこのまま入院されたほうがいいでしょう。このあと、病気の拡がりや程度(病期)を決めるための詳しい検査が必要になります(*1多発性骨髄腫の病期)。それに合併症の骨病変でいつどこで骨折するかわかりませんからね。もし転んだりして胸の骨が折れて、それが心臓や肺に突き刺さるという事故でも起こったらたいへんですから。骨が溶け出して高カルシウム血症の状態になっているので、意識障害が起こることがあるし、心臓や腎臓も心配です。まず放射線治療と薬物治療で骨病変への対策(*2)を図っていく必要があるでしょう」
関根さんは予期しない話に驚いた。すぐ横にいる妻の峰子さんも「えーっ」と声をあげている。たった今、正式に病名を聞かされたばかりであり、そのまま入院するような準備などしていない。とはいえ、それだけ自分がただならない状態であるということを思い知らされたわけでもある。
「1度家へ帰って会社へ連絡して、部下に仕事の引継ぎをしたいのです��……」
「今は仕事のことをお忘れになったほうがいいですよ。どうしてもお話が必要なら、会社の方に病院へ来てもらったらどうですか?」
関根さんは「この数日間で、自分の人生の何もかもが変わってしまった」と思えた。
「治療はだいぶ長期間になるのでしょうか?」
「そうですね。初期治療は最低半年くらいはかかるとみてください」
またも、驚くようなことを聞かされた。さらにおずおずとした調子で聞いてみる。
「ずっと退院できないかもしれない?」
「いいえ、そんなことはありません。骨病変の治療で骨折の心配がなくなったら、いったん退院もできるようになりますよ。その後は化学療法を行うようになれば入院していただくことになりますが、基本的にはご自宅からの通院で治療ができます。多発性骨髄腫はとても難しい病気ですが、1度は必ずいいほうに向かうと思います」
関根さんには、医師が「いったん」とか「1度は」という言葉を強調しているように聞こえる。この病気は、「不治の病」なのかと改めて思い知らされる。
「突然のことでお困りかとも思いますが、奥さんはご主人の入院の仕度をお願いします。詳しい治療方針についてのご説明は、明日の夕方改めて血液内科病棟の面談室で行いますので」
その後、関根さんは、車椅子に乗せられて病室へと移った。
ステージ3と全身状態からVAD療法を選択
「関根さん、関根さん。面談室へどうぞ」
8月25日夕方4時過ぎに、病室のスピーカーから看護師の声が流れた。関根さんは前日痛み止めの注射を受け、この日は骨病変部への放射線治療も受けているが、全身の痛みはあまり治まっていない。ゆっくり体を動かしながら車椅子に乗り込むと、峰子さんが押してくれた。
面談室には丸いテーブルが置かれ、三木医師のほか、まだ30歳前と思われる医師らしい人物が1人、看護師が2人席に着いていた。夫婦がテーブルに着くとすぐに三木医師は、「研修医の高橋先生に、看護師の三浦君と柴田君です」と紹介する。
「どうですか。昨日はよく眠れましたか?」
その日の朝の回診で1度顔を合わせているはずなのに、関根さんの緊張した表情を見てとったためか、医師は最初にそんなふうに尋ねた。
「いえ、あんまり……。痛いのと慣れないところで寝たのとの両方で」
関根さんはこう言って顔をしかめてみせる。
「そうですか。では、痛み止めをもう少し工夫してみましょうね。夜はなるべくよく寝て体力を落とさないようにしないといけませんね」
医師は優しい声で話した。
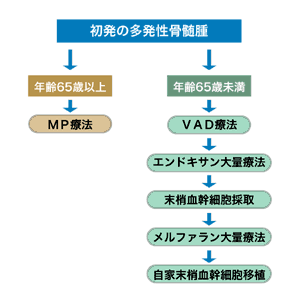
「それでは、今後の治療方針についてご説明しましょう。私たち専門医にとっても、多発性骨髄腫の治療は相当複雑なものですからね(*3多発性骨髄腫の治療の選択)」
そういうと三木医師は立ち上がって傍らのホワイトボードに向かう。
「関根さんの病期は、骨髄腫の細胞数からいっても、血液中や尿中のMタンパクの量からいっても、いちばん進行したステージ3といえます。この段階では、治療せずに放置すると、寿命は半年しかありません。そこで病期と、関根さんの年齢や全身の状態などの条件から、私たちはまず抗がん剤を使用する化学療法をお勧めしたいと思います」
ここで医師は、ホワイトボードにまず「VAD療法」という文字、そして「大量化学療法+自家移植」という文字を書いた。
「最初に4カ月ほど、このVAD療法と呼ばれる化学療法を行って寛解(*4)に導きます。次に血液の種である造血幹細胞を採取しておき、ここでエンドキサン大量療法を行って、がんを徹底的に叩くのです。そのあと冷凍保存しておいた造血幹細胞を再び戻して、再び血を作るようにします。これが自家移植(*5)です」
5カ月かけて行われた治療で寛解に
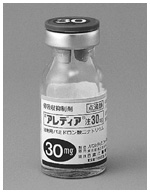
ビスフォスフォネート剤のアレディア
8月25日から、関根さんに対して自家移植の前提としてVAD療法と呼ばれる化学療法が始まり、同時に骨病変治療のためのビスフォスフォネート製剤の投与が行われた(*6VAD療法と自家移植の流れ)。それまでの人生で経験したことのない持続点滴という治療を受けるため、関根さんは1日の大半をベッドの上で過ごさなければならなくなったのである。
が、その治療の効果はすぐに現れ始めた。入院から3日目には関根さんは久しぶりに食欲を覚えた。病院食はすべて平らげたほか、峰子さんが自分の昼食用に用意していたサンドイッチも2切れ食べている。激しいのどの渇きも治まっていった。ただVAD療法を始める前に測定したとき、元気な頃より7~8キロも少なくなっていた体重は、まだほとんど回復してはいなかったのである。
入院から1週間目くらいで関根さんの激しい痛みは消えていた。三木医師は、「血液中のカルシウム値がかなり下がっていますね。これでひと安心です」と話している。さらに医師は関根さんに、「体力をつけるために、病院内を積極的に歩くようにしてください」と話した。
さらに2週間を経て、化学療法は2コース目に入った。この頃、すでに薄毛が目立っていた関根さんだが、髪の毛がまとまって抜けることに気づく(*7VAD療法の副作用)。抗がん剤の副作用である。しかし、まわりを見てみると、同じフロアの病室に入院中の患者たちは、女性も男性もみんな坊主頭だということに改めて気づいた。「このフロアでは、みんなやっかいな血液のがんに苦しんでいるんだな」と考えると、少しほっとするような気持ちになってくる。
9月30日、病室を訪れた三木医師はこう話した。
「関根さんは順調に効果が出ているようです。退院していただいて大丈夫だと思います。このあと、3コース目と4コース目の治療のときに、それぞれ4泊5日の入院をしていただくようにしたいと思います」
こうして関根さんは、久しぶりに世間の空気を吸うことができるようになったのである。


