渡辺亨チームが医療サポートする:多発性骨髄腫編
渡辺亨チームが医療サポートする:多発性骨髄腫編
金成元さんのお話
*1 骨痛を招く病気
骨病変が直接生命に関わることはほとんどありませんが、それによって起こる痛み(骨痛)が日常生活の動作に支障を来たしたり、生活の質を落とす原因になります。骨痛を招く病気としては、一般的には骨折や骨粗鬆症、変形性脊椎症などがおなじみです。
注意しなければならない例として、肺がんや前立腺がん、乳がんなどのがん(固形がん)が骨に転移して痛みを生じている場合があります。さらに多発性骨髄腫という血液のがんは、骨髄に由来する腫瘍化した形質細胞が近接する骨に侵入し、それが骨を破壊することによって骨痛が起こります。
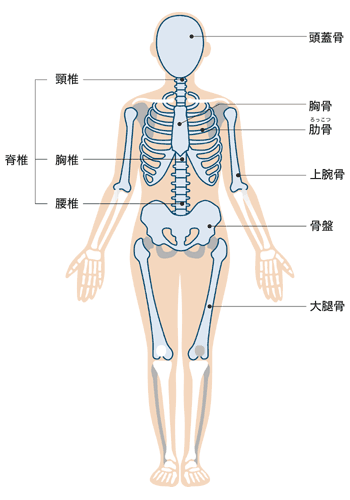
*2 骨痛の検査
骨痛があって病変があることが疑われるとき、次のように画像診断を中心に調べます。
【骨X線】
骨病変を調べる最も一般的かつ必須の方法です。骨髄腫の場合には、痛みのある部位以外にも変化が出ることがあります。頭蓋骨が2~3センチの円形に打ち抜かれたように見える「パンチドアウト像」と呼ばれる病変は有名です。そこでX線検査では痛みのある部分を中心に骨の変形や骨が溶けて薄くなっていないか、または逆に骨が硬化していないかなどを調べます。
【CT(コンピューター断層撮影)検査】
いろいろな角度で撮影したX線写真をコンピューター処理し、人体を輪切りにした面を合成できます。詳細な病変を検出することができるので、脊椎骨の病変を捉えることができます。
【骨シンチ検査】
アイソトープ(弱い放射能を持つ同位元素)を注射した後にシンチカメラというカメラで検査を行います。血流により骨に運ばれたアイソトープが、骨代謝や反応の盛んなところに集まる性質を利用しています。骨腫瘍だけでなく、骨の炎症・骨折などでも反応が現れます。
【MRI(磁気共鳴画像)検査】
磁場を用いて物を分子レベルで観察できるので、撮影した画像から異常な部位を検出します。詳細な病変を探り出すことができ、また骨粗鬆症との鑑別も可能です。
【骨代謝マーカー】
骨代謝マーカーとは、骨の破壊時や形成時に血中や尿中に出てくる物質のことで、それぞれ骨吸収マーカー、骨形成マーカーといいます。骨代謝マーカーだけでは診断せず、画像診断と併せて総合的に判断する必要があります。骨粗鬆症ではよく用いられますが、それ以外ではあまり使用されません。
*3 高カルシウム血症
高カルシウム血症は、血液中のカルシウムの濃度が異常に高くなる病態です。がんが高カルシウム血症の原因となる場合がありますが、この場合、のどの渇き、食欲不振、吐き気、頭痛、骨の痛み、脱力感(体がだるいと感じる)、意識障害などが生じることがあります。
*4 多発性骨髄腫
骨の中にある骨髄は、幹細胞という血液の種から血液を作る「血液の工場」です。工場が正しく働いていれば、赤血球や白血球、血小板などいろいろな役割を持った血液細胞が作られていき、正常な血液が産生されます。白血球には顆粒球やリンパ球などの種類があって、このうちリンパ球から形質細胞という細胞が作られていきます。この形質細胞が“がん”になってしまうのが多発性骨髄腫です。
正常な形質細胞は体に侵入したウイルスや細菌などの異物を排除する作用を持った「免疫グロブリン」というタンパク質(抗体)を作ります。ところが、形質細胞ががん化すると、Mタンパクと呼ばれる不良品の免疫グロブリンをたくさんつくって、これがからだに悪さをするようになるのです。がん化した形質細胞を「骨髄腫細胞」といいますが、骨髄腫細胞自身もやたらに増えるために、他の血液細胞が作れなくなるなどの問題を引き起こします。
多発性骨髄腫は、作り出されるMタンパクの種類によってIgG、IgA、IgD、IgE、ベンス・ジョンズ・タンパク(BJP)などのタイプに分けられます。このうちBJP型は血中にMタンパクが検出されず尿中にBJPというタンパクが見つかります。
多発性骨髄腫は、発症のピークが65~70歳にみられ、40歳未満の発症はまれです。男性が女性より多く発症し、約60パーセントが男性です。これまで多発性骨髄腫の発症頻度は人口10万人に対して2人程度といわれていましたが、高齢化社会の到来とともに増加する傾向がみられます。
最近では地域の住民検診や人間ドックの際に行われる血液生化学検査で異常が発見され、精密検査によって多発性骨髄腫と診断されるパターンが徐々に増えています。
*5 多発性骨髄腫の症状
多発性骨髄腫の症状は様々で、種類や程度は1人ひとり異なります。
最も多い症状は、骨病変によるもので、腰、背中、肋骨などの骨の痛みです。がん化した形質細胞がまわりの骨を破壊しながら増え続けるため起こることで、痛みだけでなく全身の至るところの骨が弱く折れやすくなります。痛みはじっとしていると軽く、動くときに強くなり、また痛む場所があちこち動くのも特徴です。
正常な血液を造る働きが損なわれるために現れる症状もあります。赤血球が少なくなって貧血になり、疲労、脱力、顔面蒼白、体のだるさ(倦怠感)、めまい、動悸、息切れ、頭痛、食欲不振などが現れます。正常な白血球が少なくなることにより発熱しやすくなり、細菌やウイルスと戦う正常の抗体が作られにくくなるので、感染症に対する抵抗力も弱まります。血小板が少なくなれば血液を固める機能を低下させるため、あざや出血が生じやすくなります。
病気が進行すると骨折したり、背が低くなったりします。また骨が溶け出すことにより高カルシウム血症で、意識障害などが出現することもあります。さらに腎機能が悪くなり、むくみなどの症状もでてきます。また、神経炎による痛みや神経障害による腸管マヒ、尿失禁、筋力低下などがみられることもあります。
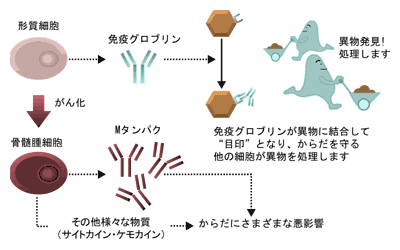
*6 MP療法
多発性骨髄腫の初期治療(寛解導入療法)としての標準的な治療法は、MP療法と呼ばれる1970年代からある化学療法で、アルケラン(一般名メルファラン)という抗がん剤とプレドニン(一般名プレドロニゾン)というホルモン剤の併用です。この治療法を行っても、平均生存期間は3年、奏効率(骨髄腫を示すMタンパクが半分以下になること)は50パーセントに過ぎなかったのです。
MP療法の大きな問題は、血液の種になる幹細胞まで殺してしまうために、血液を再生できなくなってしまうことです。そのため、近年よく行われる自家末梢血幹細胞移植併用大量化学療法のための造血幹細胞採取ができなくなります。MP療法より奏効率が高く、幹細胞にダメージを与えない寛解導入療法があるため、MP療法は70歳以上の高齢者や大量化学療法を行わない患者さんなどを対象として行われるものになろうとしています。
*7 多発性骨髄腫の原因
多発性骨髄腫の原因は不明ですが、近親者に生じることから、遺伝が関係していると考えられています。また放射線被曝や環境汚染も原因になりうるとされています。ヘルペスウイルスの一種であるHHV-8(ヒトヘルペスウイルス8型)も、この病気に関係している可能性があるのではないかといわれています。多発性骨髄腫の原因はわかっていないため、予防法もありません。
*8 骨髄穿刺
胸の前の骨(胸骨)や腰の横の骨(腸骨)に少し太めの針を刺して、骨髄の細胞を取り出し、顕微鏡で調べる検査です。

骨髄穿刺に使う専門針
*9 多発性骨髄腫の確定診断
臨床症状から多発性骨髄腫が疑われる場合には、血液や尿の検査を行います。血清中や尿中にMタンパクが陽性で、骨髄穿刺液中に骨髄腫細胞が10パーセント以上認められ、さらにレントゲン写真で多数の骨破壊病変が認められれば診断がつきます。しかし、まれにMタンパクが検出できない場合もあります。厳密には、Southwest Oncology Group (SWOG)の診断基準というものが最もよく用いられています。


