渡辺亨チームが医療サポートする:多発性骨髄腫編
渡辺亨チームが医療サポートする:多発性骨髄腫編
金成元さんのお話
*1 自家末梢血幹細胞移植の手順
自家末梢血幹細胞移植は、まず血液の種である造血幹細胞を採取するためにエンドキサンという抗がん剤を大量投与する治療を行います。これにより骨髄腫がダメージを受けるとともに、正常な骨髄もダメージを受けます。しばらくすると先ほどの造血幹細胞が骨髄内で増えてきます。ここでG-CSFという白血球を増やす薬を使うと、末梢血に幹細胞が誘導され、幹細胞を採取することができるようになります。
採取した末梢血幹細胞はいったん凍結保存しておきます。幹細胞が十分に採取できたことを確認した後に、今度はアルケランという抗がん剤を大量投与して血液を製造する骨髄を空っぽに近い状態にします。このままでは好中球数がゼロに近い状態が続き非常に危険なので、アルケランの大量投与の翌々日、凍結保存しておいた末梢血幹細胞を解凍し、患者さんの体の中に点滴で返すのです。この自家末梢血幹細胞移植を伴う大量化学療法により、生存期間が延長することが証明されています。自家移植は多発性骨髄腫だけでなく、白血病など他の血液がんの治療にも用いられることがあります。
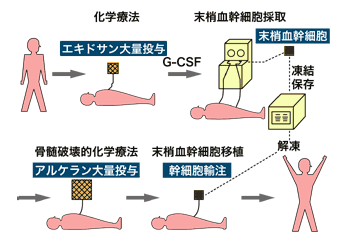
[全国で行われている自家移植の数の推移]
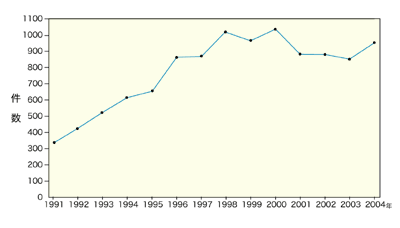
*2 プラトー期
多発性骨髄腫の抗がん剤治療は、数カ月~数年間の安定期と再発を繰り返すのが一般的です。骨髄腫細胞が減りも増えもせず、とくに症状もない安定期のことをプラトー(「平らな土地」を意味する言葉)と呼びます。
一般的に多発性骨髄腫の初期の段階では治療が奏効し、プラトー期を迎えるのが普通です。この時期にはずっと抗がん剤治療を続けると、治療による2次的な合併症が起こってくる心配があるので、いったん中止して様子を見るということが必要になってきます。
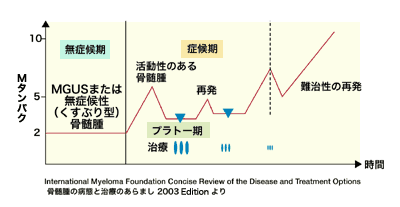
*3 再発とサルベージ療法
それまで骨髄腫を抑えていた治療法がもう効かなくなって、がんが再び進行し始めることを「再発」といいます。そして、初回治療の反応性が悪い患者さんや再発した患者さんに行う治療がサルベージ療法です。
サルベージ療法では前回の治療法(薬)の効果が、ある���度の期間長続きしていたのであれば、またそれが効く可能性があるので、まず前回と同じ治療法を検討してみるべきです。何度も同じ治療を繰り返し行っても効果が得られる患者さんもいます。
しかし、前回の治療の効果が長続きしなかったときは、同じ治療をしてもあまり効果は期待できません。同じ抗がん剤でも投与法を変えたり、それまでに使っていない抗がん剤を使う方法、新しい治療薬を使う方法などが考えられます。
*4 ミニ移植
多発性骨髄腫で大量化学療法+自家移植の治療をした後に再発した場合、次の治療法にミニ移植が選択されることがあります。
自家移植は大量の抗がん剤でがん細胞を叩き、骨髄機能が非常に低下するため、自分の造血幹細胞を輸注して骨髄機能の回復を早めるというだけですが、ミニ移植は他人(ドナー)から造血幹細胞をもらい、そのドナーのリンパ球が持っている免疫力でがん細胞を攻撃する治療法です。ですから、自家移植とミニ移植では、効果の中身が全然違います。
他人からもらった造血幹細胞を移植する場合、その前処置として大量の抗がん剤と全身放射線照射を行って、完全に骨髄細胞を破壊してからドナーの骨髄を移植し、これを「フル移植」といいます。これに対して、患者さんの骨髄の抗がん剤治療に、あまり大量の抗がん剤を使わずに(全身放射線照射を追加する場合、照射量を6分の1~3分の1に減らす)、患者さんの負担を軽くしたものをとくに「ミニ移植」と呼びます。ミニ移植がうまくいけば、高い生存率が得られる上、完全奏効になり、理論上骨髄腫が完治する可能性もあります。
しかし、ミニ移植では自分の体の中に他人の免疫細胞が入り込むことになり、患者さんの臓器がこれによって攻撃を受け、移植片対宿主病(GVHD)という合併症が生じます。
具体的には皮膚炎、黄疸、ひどい下痢、食欲不振などの症状が出ます。
GVHDとそれに関連した感染症などにより、非常によく効く(完治する)人と同じくらいの2~3割の患者さんがすぐに亡くなり、そうでなくても、合併症が強く出る人は寝たきりで苦しみ続けるという場合もあります。
骨髄腫はほかの治療だけでかなり長く生きられる可能性があるので、ミニ移植を選択することは少なくなっています。あまり進行しすぎるとミニ移植の効果は落ちることが知られており、ミニ移植のタイミングの決定は非常に難しいのが現状です。
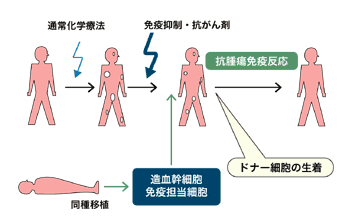

*5 サリドマイド
サリドマイドは1957年、西ドイツの製薬企業から発売された睡眠・鎮静薬ですが、妊婦では胎児の臓器形成に障害を与えて奇形を生じさせるアザラシ肢症を生じさせるなどの副作用が明らかとなり、欧米諸国では1961年、日本では1962年に使用が禁止されました。
ところが、最近になって皮肉なことに社会問題となったこのサリドマイドが、多発性骨髄腫などの難治性疾患に対する治療に役立つことがわかってきました。サリドマイドに毛細血管などの組織を作るのを妨げる血管新生阻害という作用があることが、1994年動物実験で発見されたのです。
ほぼ同時期に、骨髄腫患者は正常者に比べ骨髄中の微小血管が非常に豊富であり、骨髄血管新生は骨髄腫細胞の増殖や病状の活動性に関与しているとの研究報告がされました。
このことから、骨髄腫患者に血管新生阻害剤としてサリドマイドを使用すれば、がん細胞に栄養を送るのをブロックして骨髄腫の増殖を抑えられるのではないかという仮説が立てられ、実際1999年、アメリカで治療抵抗性骨髄腫にサリドマイドを投与したところ、およそ3分の1の患者に有効であるとの報告がされました。
再発難治性の骨髄腫患者を対象にした欧米の臨床試験では、200~800ミリグラムを毎日内服した結果、Mタンパクが25パーセント以上減少した患者が30パーセント以上もいたと報告されています。
またサリドマイドだけでは効かない人でも、ステロイドホルモンのデキサメタゾン(デカドロン)という薬と併用すると有効になる場合があり、この2剤の併用により5割前後で有効であるとされています。そのため、現在ではこの2剤の併用が再発・難治例の標準的治療法として確立されました。
日本でもサリドマイドは多発性骨髄腫などの病気の治療のために、一部で医師を通じて個人輸入されて利用されてきました。2004年には日本血液臨床学会と厚生労働省が「多発性骨髄腫に対するサリドマイドの適正使用ガイドライン」を作っており、事実上サリドマイドの治療は公認されていたわけです。
まもなく日本でも多発性骨髄腫治療薬としての製造販売が厚生労働省に承認される予定です。ただし、処方の対象になるのは多発性骨髄腫の患者のうち、サリドマイドの服用以外の治療法で十分な効果が得られない患者とされています。
また、再発だけでなく未治療の方に対してサリドマイドとデキサメタゾンを併用した場合、7割近くの奏効率があると報告されました。そのため、発病当初からサリドマイドを使用すべきかどうか検討されています。
今後サリドマイドとデキサメタゾンについて長期に渡って観察したデータが出てくれば、今まで第1選択とされていた寛解導入療法→大量化学療法+自家移植に代わって、こちらが第1選択になるかもしれません。
サリドマイドの副作用として、便秘や脱力感、眠気あるいは神経の障害で、とくに手足のしびれ、白血球の一種である好中球の減少などが報告されています。また、欧米ではとくに深部静脈血栓症を起こしやすいとされ、それに対する予防薬の併用が勧められています。


