渡辺亨チームが医療サポートする:多発性骨髄腫編
渡辺亨チームが医療サポートする:多発性骨髄腫編
金成元さんのお話
*1 サリドマイドの用法・用量
サリドマイドは経口薬で、一般的に1日1回、就寝前に服用します。ただし、サリドマイドの投与量や投与スケジュールは、未だ確立されていません。これまでの臨床試験で、投与量を200ミリグラムから800ミリグラムまで、段階的に増量させると腫瘍縮小効果が上昇することがわかっています。
しかし、日本人においては、1日あたりの投与量が400ミリグラム以上になると副作用が強く、多くの施設では1日100~200ミリグラムで治療されています。最もよい投与量や投与スケジュール、血栓症などの副作用の予防法については、今後の研究結果の報告が待たれます。
*2 デキサメタゾン
難治性多発性骨髄腫に対してサリドマイドと副腎皮質ホルモン剤、とくにデキサメタゾンとの併用療法で、サリドマイド単剤よりさらに治療効果が向上するとの報告が多数あります。サリドマイドとデキサメタゾンの相乗効果により、難治性の患者さんに対し50パーセントを超える奏効率(腫瘍が小さくなる割合)が報告されています。
現在のところサリドマイドとデキサメタゾンの併用療法の投与量、投与スケジュールは確立されていません。日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG)においても、再発・再燃・治療抵抗性の症候性多発性骨髄腫に対するBD(ボルテゾミブ+デキサメタゾン)療法とTD(サリドマイド+デキサメタゾン)療法の無作為化比較試験を準備中です。
*3 サリドマイドの有効性
多発性骨髄腫に対するサリドマイドの有効性については、欧米を中心に報告が相次いでいます。14パーセントの患者さんがCR(完全奏効)ないしそれに近い結果に、30パーセントの患者さんがPR(部分奏効)以上となり、有効な場合は骨髄所見や貧血の改善もみられたとされています。また、2年無再燃生存率は20パーセント、2年全生存率は48パーセントとなっています。
日本国内では、慶応大学病院からの報告によると、26名の患者さんにサリドマイドを投与し、評価可能であった22名のうち、36パーセント(8名)に50パーセント以上のMタンパクの減少を認めました。このようなサリドマイドが有効な患者さんでは、骨髄中形質細胞数の減少とあわせ、骨痛の消失、貧血の改善、正常ガンマグロブリン値の回復も認められたと報告されています。
*4 ベルケイド(一般名ボルテゾミブ)
ベルケイドは、骨髄腫細胞が増殖するために必要なタンパク質(酵素)の働きをブロックして、骨髄腫細胞だけをやっつける働きを持つ分子標的薬で、プロテオソーム阻害剤と呼ばれます。また、骨髄の微小環境に作用することでも抗腫瘍効果を発揮するといわれ、���れまでの薬剤とは異なる全く新しい効き方をする薬剤です。
欧米でベルケイドの有効性を調べる大規模な「エイペックススタディ」と呼ばれる臨床試験が行われました。多発性骨髄腫に効果があることがわかっているデキサメタゾンのパルス療法と比較したものです。これによると、奏効率はベルケイドが38パーセント、デキサメタゾンが18パーセントという結果が得られました。1年生存率も、ベルケイドが80パーセント、デキサメタゾンが66パーセントと、ベルケイドが従来の治療法を超える優れた治療法であることが示されています。
日本では、2004年4月よりこれらの海外臨床試験を基に「再発又は難治性の多発性骨髄腫患者」を対象とした臨床試験(対象患者34名)が行われ、有効性(CR + PR)が33パーセントであり、海外臨床試験に匹敵する成績でした。
ベルケイドはすでに世界77カ国(2006年9月現在)で承認されています。日本でも2006年10月に製造販売が承認され、同年12月に販売が開始されています。
現在はベルケイドをほかの化学療法薬と組み合わせて、さらに効果を高める治療法の研究が進んでいます。また、初回治療として使っても有用であることも報告されているので、将来は最初からベルケイドのような薬が使われるようになる可能性もあると考えられています。

*5 ベルケイドの用法・用量
ベルケイドは注射用の薬で、数秒間で静脈内に注射します。1回投与量は体表面積1平方メートルあたり1.3ミリグラムを週に2回、2週間にわたって投与するのが一般的です。そのあとの1週間を休薬し、この3週間を1サイクルとして行われます。なお、ベルケイドの薬は1バイアル(3mg)16万8348円です。
- 投与量1.3mg/m2
- 週2回、2週間(1、4、8、11日目)
- 急速静注
- 10日間(12~21日目)休薬
- この3週間を1サイクルとする
- 最大8サイクルまで継続

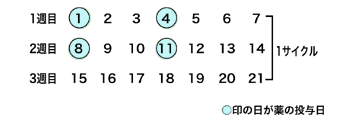
*6 ベルケイドの副作用
ベルケイドは非常に有望な治療薬でありながら、抗がん剤に比べれば副作用は軽く、吐き気や下痢あるいは血小板の減少、末梢神経障害と呼ばれるしびれ感などの副作用があります。しかし、国内臨床試験の患者さんや個人輸入製剤を使用した患者さんでは、急性肺障害および間質性肺炎が起こったと報告されており、死亡した患者さんも出ました。
このように重篤な肺障害の発現が認められることから、海外に比べて日本人での肺障害の発現頻度が高い可能性があります。肺障害が起こりやすい要因や原因などはまだわかっていません。国内で行われた治験対象患者数は極めて限られているため、ベルケイドの承認条件として、販売後一定数のデータが集積されるまでの間は、全患者さんを対象に詳細な使用成績調査を実施することとされています。
*7 レブラミド(一般名レナリドミド)
サリドマイドの誘導体といわれる薬で、サリドマイドと良く似た構造をしていて、サリドマイドよりも効果的で安全であることが証明されています。サリドマイドと同じようにがん細胞が成長するのに必要な血液の供給を邪魔する働きがあるといわれますが、詳しいメカニズムはわかっていません。最近米国では、少なくとも1回以上の治療を受けている多発性骨髄腫患者さんに対しての使用が承認されました。ただし、デキサメサゾンとの併用が必要です。
アメリカでは、ほかの治療法で効果がなかったり、サリドマイドに反応しなかった多発性骨髄腫の患者さんを対象とした臨床試験で50~60パーセントの患者さんにおいて少なくとも25パーセントのMタンパクの減少が認められました。レナリドミドはデキサメタゾンとの組み合わせでボルテゾミブが無効だった患者さんにも有効であったという報告もあります。
また、レブラミド(カプセル剤)はサリドマイド(錠剤)と同じく経口服用しますが、吐き気や脱毛といった抗がん剤特有の副作用がありません。主な副作用は血球減少で、サリドマイドと違って、鎮静作用や、便秘、神経障害などはあまり現れないといわれています。
米国メイヨークリニックのレブラミドをデキサメタゾンと併用した治療法の臨床試験では、骨髄腫と診断されたばかりの患者さんの80パーセント以上が奏効することがわかっています。
*8 これからの骨髄腫治療
海外では多発性骨髄腫治療の新薬が次々登場し、治療の選択肢がかなり増えています。そして、日本では「骨髄腫治療の診療指針」もできて、全国でこれらの新しい治療が受けられる態勢になろうとしているところです。
こうしたなかで、骨髄腫の治療はこれから数年のうちに根本的に変わっていく可能性があります。現在、初期治療で標準的に用いられるMP療法やVAD療法と呼ばれる化学療法も、近いうちにサリドマイドやベルケイドなどの新規治療薬を使った治療に取って代わり、さらなる生存期間の延長や治癒が望めるようになる可能性があります。
また進行性の患者さんにとっても、骨痛や帯状疱疹などのつらい症状が出てきたり、Mタンパクの上昇など病気の状態を示す数値が上がってきたら、それに応じてなんらかの対策を考えられるようになってきました。先に行けば行くほど新しい優れた治療法に出合える可能性が出てくるわけですから、患者さんにとっては、希望を持って病気に取り組んでもらえる時代になってきたといえます。


