肉腫の治療を牽引する、GISTの患者、医療者一体の取り組み
副作用をコントロールしながら新薬でGISTの予後をつなぐ
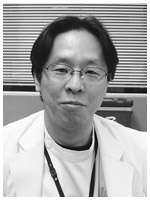
国立がん研究センター東病院内視鏡部の
土井俊彦さん
GISTとは、胃や小腸、大腸などの消化管壁の筋肉層にある特殊な細胞(カハール介在細胞)が異常に増殖し、腫瘍となる病気だ。原因の多くは遺伝子の異常で、GISTの80パーセントはC-KITと呼ばれる遺伝子が突然変異して起こる。その結果、細胞増殖に関与する酵素であるチロシンキナーゼの一種であるKITタンパクが異常になり、増殖シグナルを出し続けるようになる。残りの20パーセントのうちの半数、つまり全体の10パーセントでは、KITタンパクとよく似たPDGF-Rαと呼ばれるタンパクの異常が原因とわかっているが、残り10パーセントについては不明だ。
「GISTの多くは内視鏡検査や消化管造影検査で発見されます。ほとんどの場合、GISTに特有なKITレセプター(受容体)の発現が認められるので、組織をとって『免疫染色』という方法で染めて、発現しているかどうかで最終的に診断します。ただし、免疫染色で陰性であってもC-KIT遺伝子に異常があるケースが5~6パーセントであり、陰性でも遺伝子検査をしたほうがいいと専門家も言われています」と語るのは、わが国の数少ないGISTの専門医の1人である国立がん研究センター東病院内視鏡部の土井俊彦さん。
GISTの予後は不良で、とくに転移があると治癒は難しかったが、グリベックの登場により、初めてGISTの予後を改善する治療法が確立された。「国内の臨床試験では、切除不能または転移性の患者さんにグリベックを1日1回400ミリグラムを投与したところ、半年後に腫瘍が50パーセント以上縮小した人(PR)が46.4パーセント、進行が止まった人(SD)が53.6パーセントで、PRとSDを加えた病勢コントロールはほぼ100パーセントに達しました」グリベックは異常なKITタンパクに結合して、増殖シグナルを阻害する。また、PDGF-Rαタンパクの異常に対しても、ある程度効果がある。「KITタンパクの異常にもいくつかのパターンがあり、エクソン11という部分に変異があるものには、非常によく効き、5年生存率50パーセントといわれています。これに対してエクソン9の異変では、現在の承認用量である400ミリグラムでは効きが悪く、半数以上は1年ぐらいで再発し、エクソン13の変異やワイルドタイプと呼ばれるものに至っては、ほとんど効果が期待できず、1~2カ月しか効かない場合もあります」
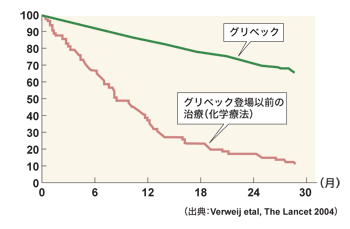
薬を増量できない理由
「欧米の標準治療では、グリベック1日400ミリグラムで効果がない場合、600~800ミリグラムに増やします。ところが日本では増量が認められていません。国内での臨床試験において有効性が示されておらず、安全性もGISTに対しては少数例の症例しか証明するデータがないからです」
GISTの患者は世界的にも数少なく、臨床試験も多国籍で行われることが多い。しかし、日本は専門の施設も専門医も少なく、患者も分散しているので、データが得られるか疑わしいと、このような大規模多国籍臨床試験に参加を呼びかけられることが少ない。
ただ、ここでも希少がんゆえの問題点がある。GISTやグリベックをよく知らない医師だと、副作用が出ると1日200ミリグラム以下に減量するケースがある。土井さんは、「グリベックは1日300ミリグラム以上でないと一般的には十分な治療効果は得られず、無意味に少ない量だと腫瘍の急性増大や耐性を早めることが推測されており、安易に行うべきではありません」と話す。
マルチターゲットのスーテント
グリベック耐性のGISTに対して使用が認められたのがスーテントだ。
「グリベックがKITタンパクだけを狙い撃ちにするシングルターゲットなのに対して、スーテントは複数のターゲットを狙い撃つマルチターゲット型チロシンキナーゼ阻害剤で、腫瘍増殖と血管新生とを阻害する働きがあります」(土井さん)
グリベックに耐性ができた患者さんを対象にした臨床試験で、スーテントを服用群の無増悪生存期間(がんの増殖を認めなかった期間)の中央値が27.3週、プラセボ群が6.4週と、明らかな差がみられ、無増悪生存期間の有意な延長が認められた。
効果が大きい反面、副作用もある。血小板減少、手足症候群、食欲不振、肝機能異常、疲労、リンパ球減少などだ。
「とはいえ、危ない薬というわけではなく、副作用を上手くコントロールして使えば高い効果が期待できる薬です」(土井さん)
これら副作用による深刻な事態を防ぐため、発売後、一定症例のデータが集積されて適正使用の態勢が整うまで、処方する医師や施設を限定されてもいる。
投与にあたり、気をつけていることとして、土井さんは「グリベックもスーテントも経口剤なので外来での治療が可能ですが、患者さんや家族の自己管理がとても重要になってきます。医師が情報を提供し、いかに患者さんがこちらにフィードバックしてくれるかが大事です」
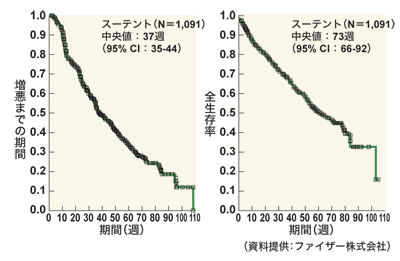
一方、サードライン(3次治療)の薬剤の臨床試験もすでに国内で始まっている。「タシグナ(一般名ニロチニブ)」という新規チロシンキナーゼ阻害剤で、2008年9月から、グリベックやスーテントに耐性を示す患者さんを対象に、国内第2相試験が実施されている。
土井さんは、これからますます必要になるのは“先を見越した医療”という。
「患者さんに、まずはグリベックやスーテントを使うためにどうするか考え、同時にその先も考えます。治験などの新薬においては、グリベックやスーテントの投与方法が不適切であれば参加できない場合もあり、治療のチャンスを失う場合もありますから、そういったことを見越して診断・初期治療から治療法を選択します。初回治療において専門家の指示・処方のもとで現在の主治医との併診をすることがもっともよいかもしれません。たとえば、私の場合、欧米で行われている臨床試験の結果を考慮に入れ、それが使えるようになったときには、十分な効果を期待できるように、患者さんをマネジメントしています。たとえば、外科切除を優先するあまり、経口摂取ができにくくなったり、胃切除により薬の吸収ができなくなる恐れがあるような場合には、胃の全切除などは避けられるのであれば避けるほうがいいなど、先を見越した治療選択をします」
また現在、医療が均てん化されても、希少疾患では問題は解決しない。土井さんはこう指摘する。
「GISTの場合、たとえ医者が薬を上手に使えるようになっても、1人の医師が診る患者さんは1~2人では、たとえ均てん化しても逆に先端医療はされにくくなるでしょう。それよりむしろ1カ所のセンターに集中させたほうが患者さんにとってのメリットは大きいかもしれません。そのためには、遠方の人が来やすいような制度づくりが重要だし、そこから全国に情報を発信し、医師や患者さんと情報を共有していくことも大切です」


