進行別 がん標準治療 劇的な生存率の向上を生んだ抗がん剤と手術併用の進歩
骨肉腫の9割は悪性度の高いがん
もう一つ、がんの進行度(病期)ですが、通常、がんの大きさとリンパ節転移、遠隔転移の差で分類するTNM分類が利用されます。でもこのがんでは、エネキンのサージカル・シテージング・システムと呼ばれる分類がよく使われます。こちらのほうが外科的に手術すべきかどうかが明確にわかるからです。
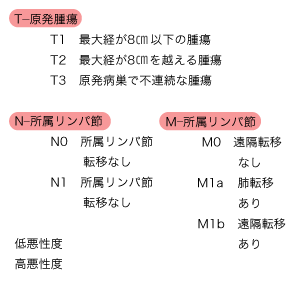
| 病期 | グレード (悪性度) | T | N | M |
|---|---|---|---|---|
| 1A期 | 低 | 1 | 0 | 0 |
| 1B期 | 低 | 2 | 0 | 0 |
| 2A期 | 高 | 1 | 0 | 0 |
| 2B期 | 高 | 2 | 0 | 0 |
| 3期 | どちらでも | 3 | 0 | 0 |
| 4A期 | どちらでも | どんな大きさの 腫瘍でも | 0 | 1a |
| 4B期 | どちらでも | どんな大きさの 腫瘍でも | 1 | どちらでも |
| どちらでも | どんな大きさの 腫瘍でも | どちらでも | 1b |

M1とは局所的なスキップ転移もしくは遠隔転移を意味する

骨肉腫の単純X線写真

滑膜肉腫の単純X線写真
この分類法にはコンパートメントと呼ばれる概念が導入されている点が新しいところです。コンパートメントとは、筋肉なら筋肉、骨なら骨の中に腫瘍が収まっているのか、出ているのかで分類する方法で、これにより手術の適応が容易に判明できるわけです。
それで、悪性骨腫瘍の代表として、骨肉腫にこの分類を当てはめてみると、病院を訪ねてくる患者の7、8割は2B期です。そして3期の人は2割、1A~2A期の人はわずか1割という少なさです。つまり、骨肉腫の9割は悪性度の高いがんというわけです。悪性度が高いということは、遠隔臓器に転移をしやすいということ。だからこうしたがんに対しては抗がん剤治療が不可欠になります。
その場合の治療法は、術前に抗がん剤治療を行ってから根治的手術をします。さらにそのうえに術後にも抗がん剤治療するというのが標準治療です。術前の抗がん剤治療をする意義は、一つは、すでに転移を起こしているかもしれない微小がんをたたいて転移を防ぐ、もう一つは、抗がん剤で腫瘍をたたいて縮小し、切除範囲を小さくするためです。
もう少し具体的にいうと、使用する抗がん剤は、標準としては3剤。メソトレキセート(一般名メトトレキサート)、ランダ(もしくはブリプラチン、一般名シスプラチン)、アドリアシン(一般名ドキソルビシン)です。加えて、近い将来、標準治療薬になりそうなのが、イホマイド(一般名イフォスファミド)。この薬剤はまだ日本に導入されてから10年ほどで、最近になってようやく長期の治療成績が報告されつつあります。そのデータが十分に蓄積されれば標準治療薬として定着するでしょう。
では、この3剤、4剤の抗がん剤をどう組み合わせ、どういう間隔で使用していくかですが、これは下図を見てもらえばわかるように、まず、メソトレキセートを単剤で1週間おきに投与することからスタートします。次いでランダとアドリアシンの併用投与で3週間間をおいて、この治療が効いているかどうかを調べます。痛みの具合、X線検査の評価、腫瘍マーカーのアルカリフォスファターゼの3つで調べ、効果が現れていれば、その治療をもう一度繰り返して手術を行います。効果がなければ、別の抗がん剤、イホマイド単剤の治療をしてからやはり手術をします。
ここで、手術により腫瘍組織が取れるので、その後の抗がん剤治療をどうするかを決めるために、組織学的な面から治療効果を確認します。腫瘍の壊死の割合が90パーセントを超えていれば「効果あり」と評価され、90パーセント以下なら「効果なし」です。
効果があれば、これまでの治療を繰り返し、効果がなければ、メソトレキセート単剤に代わってイホマイドを加えた4剤併用の強力な治療を行っていきます。また、前に効果がなく、イホマイド単剤の治療をしている患者に対しても、やはり4剤併用の治療をしていきます。
これがNECO93、NECO95と呼ばれる臨床試験で実証された骨肉腫に対する治療戦略です。
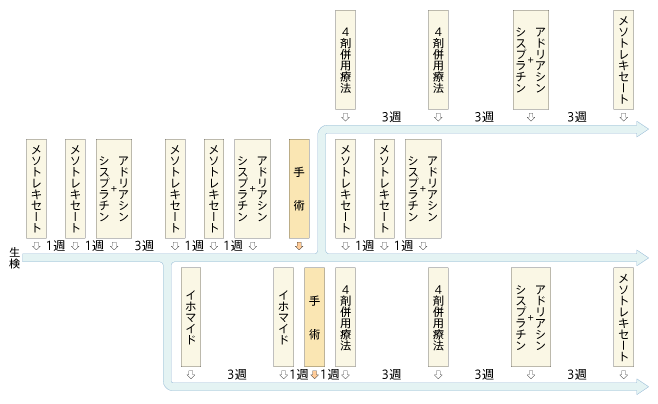

骨肉腫の標準治療薬であるアドリアシン

ランダ

近い将来標準治療薬に
なる可能性があるイホマイド
重粒子線治療が第一選択のがん

悪性骨腫瘍の脊索腫の治療では
第一選択になっている重粒子線治療
手術についてもふれておきます。前にも書いたように、画像診断の発達により、肉腫が広がっている領域を特定できるようになったお陰で、肉腫とまわりの組織を安全に切除する広範囲切除と呼ばれる手術法が生まれました。そこから「患肢温存手術」が可能になったのです。患者のほとんどがこの治療法を望まれます。
温存手術では、手術後、骨や金属製の人工関節を用いて移植する再建手術が行われます。骨移植では、自分自身の骨(自家骨)と他人の骨(同種骨)を移植する方法がありますが、悪性腫瘍の場合、切除範囲が大きいため、自家骨移植は行えないようです。ですから他人の骨を利用します。死亡した人や事故で切除された骨を冷凍保存し移植するのです。
一般によく行われるのは、人工関節による再建です。人工関節だと、手術後、数週間で歩行が可能になりますが、時間がたつにつれ緩みや破損が起こる心配があります。また、成長期の子供にこのような伸長しない関節を入れるのは適切でないと考える医師も多いようです。いずれにしても、今後に残された課題になります。
さて、3期の場合は、ほとんどが肺転移が起こっている状態です。肺以外では骨に転移していることが多いのですが、その場合もたいていは肺転移を伴っています。この3期の場合も、2期で使用されるのと同じ抗がん剤治療を行います。ただし、病状が進んでいる分、2期よりも予後が悪くなることは否めません。
遡って、数の少ない1期の場合は、抗がん剤治療をしないで手術をすることもあります。しかも、悪性度が高くなければ、その手術だけで治療は終了ということもあります。ただ、骨肉腫の中でも、20~40代に発症することが多い傍骨性骨肉腫では、放射線治療も行われています。もっとも、効果があったという報告はあまりないようです。しかし、脊髄や骨盤にこの肉腫が生じた場合は、放射線でも、病巣部にピンポイント照射ができる重粒子線治療が効果を上げています。
また、骨肉腫とは異なる脊索腫という種類の骨腫瘍は、仙骨と頭にできやすく、この治療では重粒子線治療が第一選択になっています。
骨肉腫に次いで多い軟骨肉腫は、軟骨の細胞ががん化するもので、中高年に多いがんです。この肉腫は悪性度が比較的低く、1B期や2期が多いので、抗がん剤治療をせずに、手術をするのが標準治療です。きちんと広範切除ができれば再発率は10パーセント以下に抑えられます。
また、10代に多いユーイング肉腫と、中高年に多いMFH(悪性線維性組織球種)というがんは、抗がん剤の種類と量こそ変わりますが、骨肉腫と同じ治療戦略で抗がん剤と手術を組み合わせた治療を行うのが標準治療になっています。


