個別化治療が進むなか、大きな役割を果たす病理診断 乳がんの顔つき、大きさを見極め、今後の治療方針を決める病理診断
病理診断で浸潤の有無と乳がんのタイプがわかる
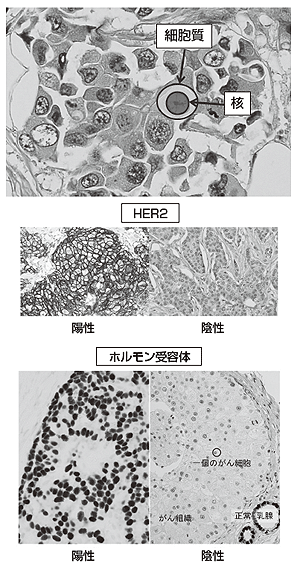
乳がんの治療や予後に重要な因子は浸潤の有無で、非浸潤性乳がん、浸潤性乳がんの2種類に分けられます(図6)。非浸潤性乳がんとは、母乳を運ぶ乳管内にがんが発生し乳管内に留まっている状態をいいます。一方、乳管外への浸潤を認めると浸潤性乳がんに分類されます。病理診断では、この浸潤の有無を判断します。
また、病理診断ではどんなタイプのがんなのか、なども確認できます。現在、乳がんはがんの持っている性格(顔つき)によって大きく4つのタイプに分けられ、それによって行う薬物治療も異なっています。
4つのタイプとは、図7のように分類され、がん細胞が女性ホルモンに反応して増殖する性質の有無(ホルモン感受性(*)あり、ホルモン感受性なし)、HER2と呼ばれるがん細胞の増殖に関連するタンパク質の有無(HER2陽性、HER2陰性)などのリスクを組み合わせたもので分類されます。
このように、病理診断によってがんの種類や性格を判断し、個々に合わせた最善の治療法を選択していくことが重要になります。
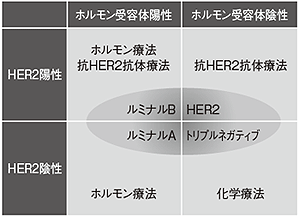
*ホルモン感受性=ホルモン受容体の有無
病理診断時に注意しなければならないこと
病理診断で注意しなければならないことは、稀に針を刺した部分からの出血で皮膚の下に血のかたまり(血腫)ができることです。また、ごく稀に針生検時の針を刺したところにがん細胞が曳かれる「がん細胞の播種」が確認されることもあります。「針生検による播種はごく稀です。心配される方も多いですが、それよりもがんを早期に見つけて治療することのほうが極めて大切です」(増田さん)
注目のテレパソロジー導入で診断の質を確保
画像検査技術の進歩に伴い、乳がんも早期がん、非浸潤性がんがたくさん見つかるようになってきました。非浸潤性がんの割合は以前10%くらいだったものが今は全国で14%くらい、がんの専門病院などでは20%くらいといわれています。
一方で、乳がんの病理診断は病変の良し悪しの鑑別が難しい領域の上、早期がんは小さな検体で診断しなければならず、診断はより困難になっています。また、現在病理医不足は深刻化しています。このような状況への支援策の1つとして注目されているのが、通信回線を利用して、病理画像で診断を行う「テレパソロジー(遠隔病理診断)」です。テレパソロジーを活用し、他病院の専門医の診断を受け、診断の質を確保しています。
また、最近は、午前中に採取した組織をその日のうちに病理診断し、患者さんに説明する「当日病理診断(ワンデイパソロジー)」の実現化も期待されています。まだ普及はしていませんが、病理診断の目指す方向性の1つと考えられています。
乳がんの治療は専門医と病理医がいる病院を選ぶ
患者さんがより良い乳がん治療を受けるには、「病院の選び方が重要」と増田さんは言います。
病院選びは、①乳がん治療の専門医がいること②常勤の病理医がいることの2点がポイントとなります。
「乳がんの専門医と常勤の病理医がいる病院を受診すれば、一定の診療の質は保証されていると思います。また、より良い治療を受けるために必要に応じてセカンドオピニオンを求めるのも良いでしょう。患者さんは納得のいく乳がん治療を受けてください」(増田さん)
同じカテゴリーの最新記事
- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!
- がん情報を理解できるパートナーを見つけて最良の治療選択を! がん・薬剤情報を得るためのリテラシー
- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ
- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識
- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!
- 術前、術後治療も転移・再発治療も新薬の登場で激変中! 新薬が起こす乳がん治療のパラダイムシフト
- 主な改訂ポイントを押さえておこう! 「乳癌診療ガイドライン」4年ぶりの改訂
- ステージⅣ乳がん原発巣を手術したほうがいい人としないほうがいい人 日本の臨床試験「JCOG1017試験」に世界が注目!
- 乳がん手術の最新情報 乳房温存手術、乳房再建手術から予防的切除手術まで
- もっとガイドラインを上手に使いこなそう! 『患者さんのための乳がん診療ガイドライン』はより患者目線に


