乳がんホルモン療法の最前線 サンアントニオ乳がんシンポ2011の成果を中心に 乳がんも個別化治療の時代に閉経後乳がんのホルモン療法最新情報
BMIの違いにアロマターゼ阻害剤の効果の差
"アロマターゼ阻害剤3剤の効果は同等"というのが現在の見解ではありますが、今回サンアントニオ乳がんシンポでは、BMI(体格指数)の違いによってアロマターゼ阻害剤の効果の出方に違いがあるのでは? ということを示唆する報告もありました。
これも日本発の試験で、アロマシンを術前ホルモン療法として使用し、BMIの違いによって効果に違いがあるか検証した結果、BMIが中くらい(22㎏/㎡以上、25㎏/㎡未満)から高い方(25㎏/㎡以上)のほうが、低い方(22㎏/㎡以下)に比べてアロマシンの効果が高い可能性がある、という結果がでました。このデータだけから治療方針を決定するのは尚早ですが、このようにより良い治療をするための研究は日々積み重ねられています。
乳がんは研究が盛んな疾患の1つです。自分にあった治療を選択するために医師とよく相談するとよいですね。
副作用の特徴を知ることも大切
"効果が同等"といっても副作用の特徴まで同じとは限りません。効果だけではなく、副作用の特徴を知ることも重要です。先にご紹介した術後ホルモン療法におけるアロマターゼ阻害剤を比較した試験では、総合的にみた副作用の発現率は、アロマシンとアリミデックスでほぼ同程度でしたが、発現した副作用には特徴がみられました。
アロマシンではアリミデックスに比べて骨粗鬆症、性器出血、高トリグリセリド(*)血症、高コレステロール血症が統計学的な有意差をもって少なかったのに対して、アリミデックスでは肝機能障害、ざ瘡、男性化、心房細動の発生が低かったとされています。これらの副作用は全ての患者さんに起こるわけではないので、効果と副作用の発現が同等ということから考えると、3剤にあまり大きな違いは感じないかもしれません。
しかし、1つのアロマターゼ阻害剤が効かなかったり、副作用で続けられなかったりしても、他のアロマターゼ阻害剤が有効なことも、副作用が出ない(軽い)こともあります。ここに同じ分類の薬剤でも、複数の選択肢があるということの意義があります。患者さん個々の症状や��度、また薬剤への感受性(効果や副作用の出方)は様々です。したがって、QOL(生活の質)を良好に保持しつつ、病態をうまくコントロールするためにも、医師とよく相談して自分に合った治療を選択することが重要になります。
*高トリグリセリド=血液中にトリグリセリド(中性脂肪)が多く存在する脂質異常症
アロマターゼ阻害剤の安全性は?
アロマターゼ阻害剤の安全性について、いい目安となるデータが今回のサンアントニオ乳がんシンポで発表されました。乳がんリスクを有する閉経後女性に対して、予防的にアロマシンを投与した群とプラセボ(薬と形は同じだが薬効成分が入っていない)を投与した群を比較し、QOLへの影響を検討したものです。結果、アロマシンはプラセボと比べてQOLにほとんど影響を及ぼさず(図5)、早期の治療中止例を増加させることもありませんでした。
薬ですのでやはり慎重に投与し、効果と副作用のチェックをきちんと行うことが基本であることは言うまでありませんが、このような効果も副作用も出ないプラセボとの比較から、薬の特徴がより明確に把握できると思います。
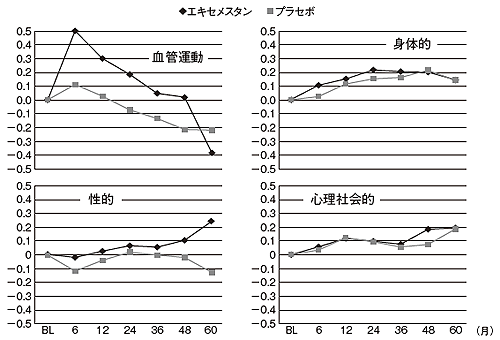
医療者によく相談し、よりよい治療を
患者さん個々にあった治療を行うためには、病気の症状や程度の把握はもちろん、患者さんやご家族と医師がよく相談しながら治療に臨む必要があります。そういう意味では患者さんご自身が症状や変化について医師にきちんと伝えることも重要です。たとえば「気になる症状が少しあるが、この程度で医師に伝えるのは悪い」などといったことをうかがうこともありますが、より良い治療につなげるためにも医師にはきちんと情報を伝えるようにしましょう。
今回のサンアントニオ乳がんシンポでは、アロマシンの治療で副作用について悩んでいた患者さん、とくに関節痛で悩んでいた患者さんは、早期に治療を中断してしまうという結果も発表されました。
このような場合、医師にきちんと相談して下されば、副作用の対処も可能ですし、薬を変えるという選択肢もあります。相談せずに自己判断で調整をするのではなく、医師によく相談してください。
さらなる個別化医療の推進に向けて
今回のサンアントニオ乳がんシンポでは、遺伝子を解析することにより、より詳細に病気の質を把握するための研究、また予後の予測をしたり、治療の効果を予測したりするための研究発表が多くなされました。このような遺伝子研究は、更なる個別化医療を推進することに繋がりますし、新しい薬剤の開発にも大きく寄与します。
これまでお話してきたように、より良い治療をするための研究は日々積み重ねられ、情報は常に更新されています。その時々の状態について医師とよく相談し、共に自分に最も適切な治療を見つけ継続する。当たり前のことですが、これが1番重要なことだと思います。
同じカテゴリーの最新記事
- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!
- がん情報を理解できるパートナーを見つけて最良の治療選択を! がん・薬剤情報を得るためのリテラシー
- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ
- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識
- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!
- 術前、術後治療も転移・再発治療も新薬の登場で激変中! 新薬が起こす乳がん治療のパラダイムシフト
- 主な改訂ポイントを押さえておこう! 「乳癌診療ガイドライン」4年ぶりの改訂
- ステージⅣ乳がん原発巣を手術したほうがいい人としないほうがいい人 日本の臨床試験「JCOG1017試験」に世界が注目!
- 乳がん手術の最新情報 乳房温存手術、乳房再建手術から予防的切除手術まで
- もっとガイドラインを上手に使いこなそう! 『患者さんのための乳がん診療ガイドライン』はより患者目線に


