乳がんホルモン療法の最新動向 SABCS 2009より さらに広がる選択肢。最適の個別化治療をみつけるために
副作用の違いなど各治療法の特徴が徐々に明らかに
前回のSABCSでは、フェマーラのイニシャルアジュバント治療とフェマーラからタモキシフェンへのスイッチ、タモキシフェンからフェマーラへのスイッチアジュバント治療も同様の成績であったことが報告されています。したがって現在、術後ホルモン療法には、アロマターゼ阻害剤5年間、アロマターゼ阻害剤からタモキシフェンへのスイッチ、タモキシフェンからアロマターゼ阻害剤へのスイッチという選択肢があるということになります(図5)。
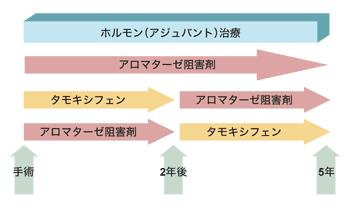
では、患者さんそれぞれに合った治療法は、どのように選べばいいのでしょうか。
今回TEAM試験の結果を発表したバーミンガム大学のダニエル・リーさんは、「今回の結果から、アロマシンは、タモキシフェンからのスイッチアジュバント治療、イニシャルアジュバント治療、いずれの治療法においても、術後のホルモン療法として有用であることが示されました。これら2つの治療法で異なるのは副作用の特徴です。治療選択は、むしろ副作用をもとに決めることが適切かも知れません」と述べています。
つまり、その患者さんにとって同じように有用であると考えられるいくつかの治療選択がある場合、副作用をはじめとする効果以外の特徴を十分に考慮して治療法を選択すべきだということです。
また副作用に関して山下さんは、「乳がんの患者さんにとって、再発しないというだけでなく、よりよく生きること、つまりQOL(生活の質)がとても大切です。したがって予想される副作用に対して適切な対策を行いながら治療を行っていく必要があります」と述べています。
TEAM副作用発現状況
TEAM試験で認められた副作用は、いずれもタモキシフェン、アロマシンについて既に知られているものでした。治療法別では、タモキシフェンからアロマシンへのスイッチアジュバント治療では、ほてり、腟出血、腟分泌、静脈血栓、筋痙攣、アロマシンイニシャルアジュバント治療では骨粗鬆症、骨折、関節痛、高血圧、高脂血症が、もう一方の治療法よりも多く認められました。
生存期間の延長も認められたアロマシンの有効性と安全性
ここ数年で、ホルモン療法に関するさまざまな知見が積み重ねられてきました。これまでに行われた試験については、その後も追跡が続けられて、長期間での効果や副作用が検討されています。それによって各治療法の特徴も、さらに明らかになってきました。
今回のSABCSでも、アロマターゼ阻害剤の試験として、唯一、統計学的に有意な生存期間の延長が認められているIES試験について、試験開始から中央値で91カ月(7年7カ月)経過した時点における解析の結果、タモキシフェンからアロマシンへのスイッチアジュバント治療を受けた患者さんで、骨転移症例が少ないことなどが報告されました。
山下さんは「ホルモン受容体陽性の乳がんでは、骨は遠隔転移の好発部位です。遠隔転移は生存期間に影響することから、骨転移が少ないとすれば、アロマターゼ阻害剤の好ましい特徴の1つになりえるでしょう。
また、生存期間が延長しているということは、アロマシンが有効かつ安全に使える薬剤であることを示すものといえます」と述べています。
さらなる個別化を目指した試験や研究が進行中
アロマターゼ阻害剤に関してはこれまで、大きな集団を対象として、治療法の優劣を研究することに力が注がれてきました。現在は、その中で得られた多くの貴重なデータから、1人ひとりの患者さんにもっとも適した治療(個別化治療)のために有用な情報を得るべく、閉経の状態や遺伝子といった患者さんの特徴や、ホルモン感受性やHER2の状態といった乳がんの特徴と、薬剤の効果や副作用との関係について、さまざまな解析が行われています。
たとえばフェマーラとタモキシフェンを比較したBIG 1-98試験では、リンパ節転移、腫瘍の大きさ、HER2の状態、腫瘍周囲の脈管浸潤、ホルモン受容体の状態、バイオマーカーなどを段階的な数値にして、再発のリスクを計算し、ホルモン療法の効果との関係を検討しています。低リスクであれば、タモキシフェンのみの治療でもアロマターゼ阻害剤を含む治療と同等の効果だが、リスクが高い場合にはアロマターゼ阻害剤5年間の治療で効果が高かったことなどが報告されました。
TEAM試験でも今回、4598名から採取された試料の解析結果として、HER2/3(ヒト上皮増殖因子受容体2型と3型注2)陰性の患者さんでは、タモキシフェンよりもアロマシンを投与したほうが、2.75年の時点における再発や転移が少ないことなどが報告されました。解析は現在も続けられており、今後、アロマターゼ阻害剤による治療にもっとも適しているのはどんな患者さんであるのかが、より詳細に解明されることが期待されています。ほかに、アロマターゼ阻害剤同士の効果を比較する試験(MA-27)や、より長期間のホルモン療法を継続することの効果を検討する試験(MA-17R)も進行中です。
さらには、同じ薬剤を継続して服用することによって効果がなくなってくる「耐性」のメカニズムについても、徐々に明らかになってきています。
注2 ヒト上皮増殖因子受容体2型と3型=ヒトの上皮増殖因子受容体に似たがん遺伝子で、HER2は分子標的薬ハーセプチンの標的分子
よりよい治療を受けるために医師とのコミュニケーションも大切に
ホルモン療法は、タモキシフェンによる治療しかなかった時代から、いくつもの選択肢の中から、それぞれの患者さんに合った治療を選ぶ時代へと、着実に進歩しています。
「ホルモン療法の効果を得るためには、5年という長い期間、きちんと治療を続けることが重要ですが、副作用が軽減されれば、治療継続は多少なりとも容易になるでしょう。
そのためにも医師や看護師とのコミュニケーションが大切だと思います。
今回の発表の中には、アロマターゼ阻害剤による筋関節症状がどのような患者さんに出やすいのかを遺伝子レベルで解析した報告もあり、今後は、効果だけではなく副作用についても、それぞれの患者さんで予測できる時代となってくるでしょう。
個別化のための情報は、まだ明らかになり始めたばかりですが、少しでも多くの患者さんが、現時点においてもっとも自分に合ったホルモン療法を受け、再発や転移なく、良好な生命予後を得られることを願っています」(山下さん)
同じカテゴリーの最新記事
- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!
- がん情報を理解できるパートナーを見つけて最良の治療選択を! がん・薬剤情報を得るためのリテラシー
- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ
- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識
- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!
- 術前、術後治療も転移・再発治療も新薬の登場で激変中! 新薬が起こす乳がん治療のパラダイムシフト
- 主な改訂ポイントを押さえておこう! 「乳癌診療ガイドライン」4年ぶりの改訂
- ステージⅣ乳がん原発巣を手術したほうがいい人としないほうがいい人 日本の臨床試験「JCOG1017試験」に世界が注目!
- 乳がん手術の最新情報 乳房温存手術、乳房再建手術から予防的切除手術まで
- もっとガイドラインを上手に使いこなそう! 『患者さんのための乳がん診療ガイドライン』はより患者目線に


