アロマターゼ阻害剤で有効性を示す新たな結果も 再発を防ぐために――乳がん術後治療の最新トピック
5年以上続けたほうが効果的という結果
かつて術後のホルモン療法は5年間が標準で、エストロゲン受容体が陽性なら、閉経前でも閉経後でも、タモキシフェンによる治療が行われていた。
「エストロゲン受容体陽性の人は、陰性の人に比べ、5年を過ぎても再発が起こりやすい傾向があります。そのため、本当にホルモン療法は5年間で十分なのだろうか、という議論は以前からありました」
そこで、MA-17という臨床試験で、次のような比較が行われた。タモキシフェンを5年間服用した後、フェマーラに切り替える群と、偽薬を服用する群(つまり無治療群)に分け、その結果を比較したのだ。
「この比較試験も、フェマーラを飲んでいるほうがいいということが途中でわかってしまい、盲検解除となっています。偽薬を飲んでいた人も、希望すれば途中からフェマーラに変えていいことになったのです」
この試験では、すでに次のようなことが明らかになっている。
タモキシフェンを5年服用した後、閉経していたら、無治療でいるよりフェマーラを飲んだほうが再発予防効果は高い。また、タモキシフェンの治療が終了した後、しばらく間隔があいてしまっても、フェマーラを服用したほうがいい。
これらに加え、新たな解析が行われ、興味深い結果が導き出されている。タモキシフェンによる術後治療を始めた時点で、閉経前だった人と、閉経後だった人に分け、再発予防効果の違いを調べているのだ。
この解析の対象者は、術後治療開始時点で閉経前だった人が約900人、閉経後だった人が約4300人いた。そのどちらもがタモキシフェンを5年間服用し、その後、フェマーラか偽薬を服用しているわけだ。
「解析を行った結果、治療開始時点で閉経前だった人は、治療開始時点で閉経後だった人より、フェマーラによる再発予防効果が大きい、ということが明らかになっています」(図5)
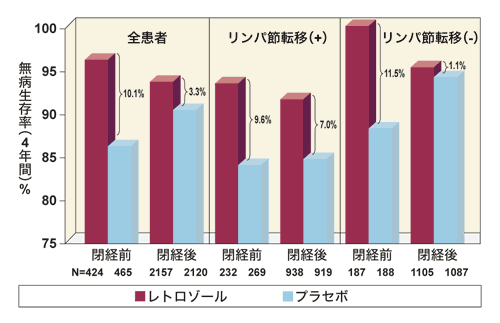
治療開始時に閉経��だった群では、その後フェマーラを服用した場合と偽薬を服用した場合で大きな差が出ている。それに対し、治療開始時に閉経後だった群のほうが、差が小さくなっているのだ。
「たとえば、閉経前の人が乳がんの術後治療でタモキシフェンを5年間服用したとします。その時点で閉経していたり、数年経ったのちに閉経したりした場合には、タモキシフェンだけで治療を終了するより、さらにフェマーラによる治療を続けたほうが、再発を予防する効果が高くなるということです」
副作用の関節痛などは運動や薬で乗り切る
フェマーラなどのアロマターゼ阻害剤には、特徴的な副作用がある。1つは関節痛や筋肉痛、もう1つは骨が弱くなって起こる骨折だ。BIG1-98試験でも、表に示したような副作用が現れているが(図6)、実際に治療を進めていく上で、とくに問題になることが多いのは、前述した2つの副作用である。
| 主要解析(%) | |||
|---|---|---|---|
| 主要解析(%) | タモキシフェン | P値 | |
| ホットフラッシュ(ほてり) | 32.8 | 37.4 | <0.001 |
| 性器出血 | 3.8 | 8.3 | <0.001 |
| 寝汗 | 14.2 | 17.0 | 0.007 |
| 血栓寒栓イベント | 2.0 | 3.8 | <0.001 |
| 関節痛(関節症状) | 20.0 | 13.5 | <0.001 |
| 筋肉痛(筋骨格筋系障害) | 7.1 | 6.1 | 0.19 |
| 脳卒中/一過性脳虚血発作 | 1.4 | 1.4 | 0.90 |
| 心関連 | 5.5 | 5.0 | 0.48 |
| 骨折 | 8.6 | 5.8 | <0.001 |
| 高コレステロール血症 | 50.6 | 24.6 | <0.001 |
「関節痛や筋肉痛は、痛みが最も出やすいのは治療開始後1~2年で、それ以降は少なくなると言われています」
対処法としては、痛みが軽症の場合、運動が効果的だという。
「動かしていると痛みが軽くなるという人は多いですね。朝がとくに痛いという人は、起床前に布団の中で関節を動かしておくのもいいでしょう。日常生活の中にうまく運動を組み入れていくことがすすめられます」
中等症から重症では、当然薬による治療が必要になる。非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)が使われることが多い。
副作用で骨粗鬆症が進行し、骨折が起きることもある。これを防ぐためには、定期的に骨塩量の検査を受け、骨にどのような影響が現れているかを明確にしておく必要がある。
骨粗鬆症が進行していることが明らかになれば、ビスホスホネート製剤による治療が必要になる。
「アロマターゼ阻害剤の副作用は軽視できませんが、副作用で薬を継続できなくなる人は、それほど多いわけではありません。例外はありますが、多くの患者さんは、さまざま対処しながら、服用を継続しています」
ホルモン療法の治療期間が今後の課題
最後に、術後ホルモン療法の今後の課題について話をうかがった。内海さんがあげたのは、「ホルモン療法の最適な治療期間」と「アロマターゼ阻害剤のベストな使い方」を明らかにすることだった。
「現在、臨床試験が進行中ですが、治療期間は5年がいいのか、10年がいいのか、あるいは患者さんによって違うのか、明らかにする必要があります。また、どういう人にアロマターゼ阻害剤を使うのが効果的なのか、ホルモン感受性だけで十分に分かるわけではありませんからね」
こうしたことが明らかになることで、さらに効率のよい治療が行えるようになるはずである。
(構成/柄川昭彦)
同じカテゴリーの最新記事
- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!
- がん情報を理解できるパートナーを見つけて最良の治療選択を! がん・薬剤情報を得るためのリテラシー
- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ
- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識
- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!
- 術前、術後治療も転移・再発治療も新薬の登場で激変中! 新薬が起こす乳がん治療のパラダイムシフト
- 主な改訂ポイントを押さえておこう! 「乳癌診療ガイドライン」4年ぶりの改訂
- ステージⅣ乳がん原発巣を手術したほうがいい人としないほうがいい人 日本の臨床試験「JCOG1017試験」に世界が注目!
- 乳がん手術の最新情報 乳房温存手術、乳房再建手術から予防的切除手術まで
- もっとガイドラインを上手に使いこなそう! 『患者さんのための乳がん診療ガイドライン』はより患者目線に


